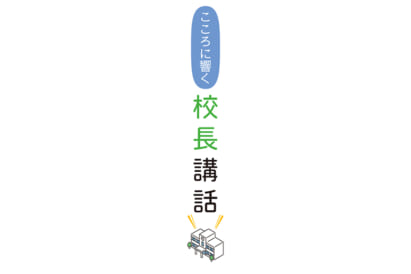一刀両断 実践者の視点から【第674回】
NEWS
生き残る大学
京都ノートルダム女子大学(京都市左京区)は、本年度から学生募集を停止することを、25日付のウェブサイトで公表した。だが、これは同大学に限った決定ではなく、他の大学へと波及する前兆と言える。
学生数が定員に満たないと、教員数が学生数に対して過剰となる「教員の過員問題」を引き起こす。そしてその傾向は今後、年々加速度を増していくだろう。なぜなら、学生数の減少はもはや避けられないからだ。
では今後、生き残れる大学とはどのようなところか。とりわけ短期大学や女子大学は、厳しい状況に直面することが予想される。系列校であればある程度持ちこたえられると考えられていたが、ノートルダム女子大学でさえ、その流れに抗えなかった。
千葉県に目を向けても、定員をかろうじて満たしている大学はごくわずかである。そうした中で、千葉工業大学の志願者増は際立っている。受験制度の柔軟さと実績が、志願者のニーズをしっかりと捉えているためだろう。
一方で、定員割れが続く大学は、いままさに存続をかけた瀬戸際にある。ここで必要になるのは、大学経営陣の柔軟で現実的な戦略だ。しかしながら、しばしば見られるのが、学者と経営者との間にあるビジョンや行動力のギャップである。
このような局面を乗り越えるには、「生き残り」を賭けた実践的な知恵と覚悟が求められる。平時の肩書きやプライドではもはや通用しない。とはいえ、経営をビジネスに傾けすぎると、大学本来の理念や軸を失ってしまう危険性もある。
いよいよ、大学間での「生き残りを賭けた本格的な戦い」が始まったと言えるだろう。
(おおくぼ・としき 千葉県内で公立小学校教諭、教頭、校長を経て定年退職。再任用で新任校長育成担当。千葉県教委任用室長、主席指導主事、大学教授、かしみんFM人生相談「幸せの玉手箱」パーソナリティなどを歴任。教育講演は年100回ほど。日本ギフテッド&タレンテッド教育協会理事。)