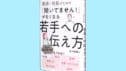子どもをあらわすということ
16面記事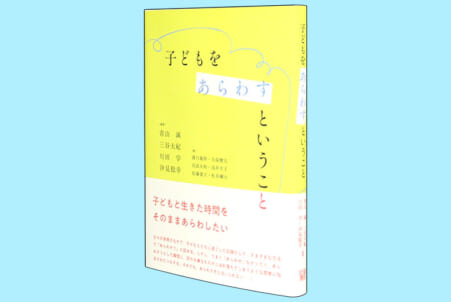
青山 誠・三谷 大紀・川田 学・汐見 稔幸 編著
遊び、主体性…意味を考える
本書は、乳幼児期の子どもの姿を長く表し続けている実践者や研究者10人が、子どもを表す意味や表し方等についてさまざまに「あらわして」いる。読みながらはっとしたのは、遊びはそれ自体が目的であり、遊びそのものが自由で歓喜に満ちた生成体験なはずなのに、事例やエピソード記述を「教育的」な意味や価値にまとめてしまう矛盾(第1章の保育が変わるということは身体が変わるということで、「見る」というより「見えてくる」。第3章の「瞬時を生きている」ことを「PDCAに基づいて行うことは不可能」)。
さらには、小・中学校等の授業研究で「どうすれば子どもの主体性をもっと発揮させることができるか」「授業で主体的対話的で深い学びを展開するために教師はどのような仕掛けができるか」と議論することが多いが、果たして子どもの「主体性」は、大人が発揮「させる」ものなのか(第4章のA感じる主体性とB考える主体性)。
特に興味深かったのが、第7章の「一緒にパパを探す」「入れ替わった二人」の二つのエピソード。保育者が子どもの姿や子どもとの関わりを面白がって生活することで、子どもの声が聴こえてくるとともに、温かい集団が生まれることに気付かせてくれる。
小学校の校長が読めば、幼保小連携・接続の必然へのヒントが満載である。
(2530円 北大路書房)
(重森 栄理・広島県教育委員会乳幼児教育・生涯学習担当部長(兼)参与)