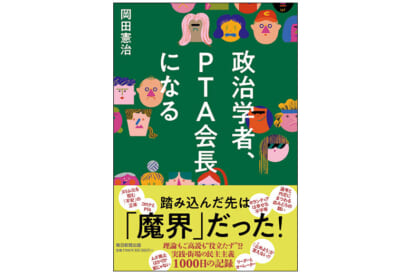教師の資質・能力を高めるリスキリングを支援!変化の激しい社会に対応した指導力を身につける
17面記事技術革新や急速に変化する社会環境に対応した人材育成には、その担い手となる教師も常に学び続ける姿勢を持ち、自身の知識・技能の質を高めていく必要がある。こうした中、現職教師が働きながら教科・校種の免許を取得できる「大学通信教育」は、教職経験を考慮した複数免許取得や、新しい知識やスキルを身に付けるリスキリングを図る場としてより一層重要な役割を担うようになっている。ここでは、その魅力とともに時代が求める新しい教師像について紹介する。
質の高い教職員集団を目指す
社会変化が激しく予測困難な時代を迎える中、わが国が将来に向けてさらに発展し、繁栄を維持していくためには、さまざまな分野で活躍できる質の高い人材育成が不可欠になる。こうした人材育成の中核を担うのが学校教育であり、中でも教育の直接の担い手である教師の資質・能力を向上させることが最も重要になっている。
では、具体的にどんな資質・能力が求められているのかというと、(1)環境の変化を前向きに受け止め、教職生涯を通じて学び続けている。(2)子ども一人ひとりの学びを最大限に引き出している。(3)子どもの主体的な学びを支援する伴走者としての能力も備えている、教師ということになる。すなわち、小中学校では、すべての子どもたちの可能性を引き出す、ICTを活用して個別最適な学びと協働的な学びを実現する力。義務教育9年間を見通して指導できる幅広い知識・技能や高い専門性を備えること。高等学校では、社会に出て通用するスキルや技術を指導できる力ということになる。
その上で、学校全体としては、教員養成、採用、免許制度も含めた方策を通じ、多様な人材の教育界内外からの確保や教師の資質能力の向上によって、質の高い教職員集団を実現することを目指していくことが必要になっている。
多様化・複雑化する教育課題
しかし、教育課題が多様化・複雑化する中で、教師に求められている資質・能⼒は⾼度化しており、個人の努力だけで対応することが難しくなっているのも事実だ。例えば、⼩学校英語教育の早期化・教科化に伴う英語専科教員の加配は思うように進んでいない。デジタル人材の育成に欠かせない高等学校の「情報」は、今年1月の大学入学共通テストから新設教科として追加されるなど、ますます重要な教科となっているが、大半は「免許外教科担任」が担当している。
幼稚園教諭も、専門性向上に向けて努力義務化されている一種免許状への上進や、「幼保連携型認定こども園」の設置に伴い、原則となっている「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」の両方の免許・資格を促進していく必要がある。あるいは、特別支援学校・学級に通う子どもが年々増える中で、当該障害種の免許状を保有している教師の割合は87・2%にとどまっており、新規採用等教師の免許状保有率もこれを下回っている。
教科以外でも、不登校児童⽣徒数は⼩・中学校で約35万⼈にのぼり、外国籍など日本語指導が必要な児童生徒が26万人を超えるなど、抜本的な対策が必要になっている。しかも、日教組の調査によれば、教師の実質的な残業時間が平均で過労死ラインを大幅に超過しているなど、早期の働き方改革の実現が不可避になっている。
学びの質の向上に向けた取り組み
こうしたことから、文科省ではさまざまな施策を打ち出している。その一つが小学校における外国語(英語)、理科、算数、体育などにおける教科担任制の拡充(+2160人)だ。学びの質の向上と教師の持ち授業時数の軽減のため、令和4年度から推進してきた高学年に加え、3・4年についても教科担任制を推進する。併せて、英語専科教員の加配措置(+3千人)も強化する。
教師の資質・能力を伸ばすため、免許状上進や複数免許取得の促進にも力を入れている。「教師の養成・採用・研修の一体的改革推進事業」では、(1)免許外教科担任の縮小に必要な教科等に関する認定講習等の開発・実施。(2)小中学校免許状併有のための認定講習等の開発・実施を公募し、現職教師の新たな免許状取得を促進している。
また、教員研修やリスキリングの機会を強化するため、「全国教員研修プラットフォーム(Plant:プラント)」を新たに構築し、大学や専門職大学院でのリカレント教育プログラムを拡充。大学等が行う実践的・専門的なプログラムを「職業実践力育成プログラム(BP)」として認定し、実践的なスキルを習得できる教育課程(認定課程数は令和6年12月時点で462課程)を提供している。
さらに、教師の学び続ける姿勢が自身のキャリア形成に直結するよう、職務や勤務の状況に応じた処遇改善にも着手。そこでは学級担任や管理職の職務の重要性や負荷を踏まえ、処遇の改善を図る。教諭と主幹教諭の間に新たな級(ミドルリーダー)を創設し、教諭よりも高い処遇とすることなどを取り入れた。
多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成に向けても、特別免許状などを活用した外部専門人材の教師への入職を積極的に採用することや、大学等における通常の教員養成のコースを歩んできたか否かを問わず、教員として必要な資質・能力を有すると認められた者に教師への道を開く「教員資格認定試験」では、幼稚園・小学校に加え、2004年度以降休止していた高等学校(情報)を再開した。
「大学通信教育」で複数免許取得やリスキリングを
このように教師の資質・能力の向上が、自身のキャリア形成を築く上でも欠かせなくなっている中で、現職教師が自分に合ったスタイルで多様な教科・校種の免許を取得できる「大学通信教育」は、教職経験を考慮した複数免許取得や、新しい知識やスキルを身に付けるリスキリングを図る場として、より一層重要な役割を担うようになっている。
現職教師が通信教育を利用するメリットには、次のようなものがある。
(1)時間の柔軟性:インターネットを活用したメディア授業が主体となる通信教育は、忙しい教員でも仕事の合間や自由な時間に学習を進めることができる。
(2)アクセス可能なリソース:オンライン教材・映像授業・双方向コミュニケーションなどが充実し、その中で最新の教育技術や方法論について学ぶことができる。
(3)経済的負担の軽減:通学する必要がないため、交通費や宿泊費がかからず、経済的な負担を軽減できる。
(4)キャリアの発展:新たな資格やスキルを習得することで、キャリアの幅が広がり、昇進や転職のチャンスが増える。
中でも大きな魅力になっているのが、教員としての実務経験があれば、通信教育課程で新しい単位を取得して教員免許を増やせることだ。例えば、高校の免許(専修または一種)のみ取得している人が中学の免許も取得する場合は、高校の実務経験3年+新たな単位習得(9単位)によって、隣接する中学校の同一教科、または関連教科の二種免許が取得できる。
また、教員免許以外にも、学校の教育活動をより充実させるために役立つ資格を取得することも可能だ。例えば、児童生徒や保護者とのコミュニケーションに心理学の専門知識を活用する、認定心理士や臨床心理士。学校教育を地域に開く活動に貢献する社会教育主事。児童生徒の生活支援や進路指導、保護者との連携強化につながる社会福祉主事。特別な配慮が必要な児童生徒が普通学級でも増えている中で、知的障害者福祉司や障がい者スポーツ指導員のニーズも高まっている。
現代の多様な学びのニーズに応える教育方法
ICT技術の進展はオンラインを活用した学習への敷居を低くするとともに、現代の多様な学びのニーズに応える教育方法として、今後さらに普及していくことが予想されている。大学においても、柔軟な学び方の一つとして通信制課程を併用するところも増えている。通学・通信の併修によって、自分の究めたい専門性に追加する形で、異なる分野の免許を取得できるなどの利点があるからだ。
こうした中、「大学通信教育」はメディア授業における独自のガイドライン(自己点検・評価、認証評価、情報公表)を制定し、各大学がより高い水準の教育に取り組むよう努めてきた経緯がある。すなわち、教育の質の担保についても一日の長がある。だからこそ、時代の変化を受け止め、教師自身が自律的に学ぶ機会やスキルアップを図る場として、「大学通信教育」を活用することをお薦めする。
私立大学通信教育協会「令和7年 秋期合同入学説明会」を開催
8月23日から、全国4都市で
公益財団法人私立大学通信教育協会では、大学通信教育を実施している大学・大学院・短期大学による「令和7年(2025年)・秋期合同入学説明会」を、東京・名古屋・大阪・福岡の全国4都市で8月23日~9月6日にかけて開催する。参加申込・費用はいずれも不要。大学・大学院・短期大学別のコーナーで具体的な講義内容や学習方法などについて直接相談できるため、興味のある人や詳しい内容について知りたい人は、ぜひ、この機会を活用することをお薦めする。
詳細=電話03・3818・3870 http://www.uce.or.jp/
2025年 秋期合同入学説明会
東 京 8月30日(土)11:00~16:00 新宿エルタワー30階
名古屋 8月24日(日)11:00~16:00 名古屋サンスカイルーム
大 阪 8月23日(土)11:00~16:00 梅田クリスタルホール
福 岡 9月6日(土)11:00~16:00 アクロス福岡