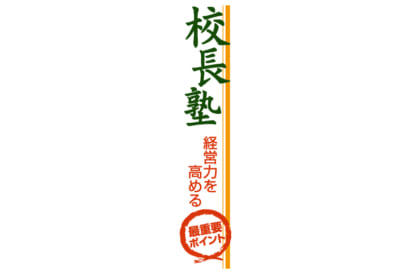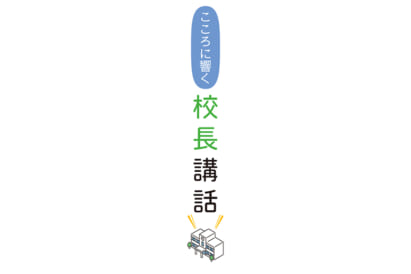寄稿 オランダなどの対策から考える児童虐待問題
NEWSオランダ・デンハーグ在住でフリーランスライター・薬剤師の島崎由美子さんから「日本の児童虐待、未然予防への課題~移住先オランダ・居住歴のあるアメリカと比較して~」を主題とした論考が届いた。現在、オランダで環境問題や教育制度、特に児童虐待に対する取り組みを取材・調査している。
オランダなどの対策から考える児童虐待問題
最近、移住先のオランダでは、日本の児童虐待事件報道を見聞きする頻度が増えています。日本に限らず、児童虐待の未然予防に意識が払われている中、その問題が深刻化してきました。そして、児童虐待が報道される度に、百家争鳴の如く、児童虐待対応のあり方が議論されています。
報道によれば、自治体が児童虐待の疑いを持ち、児童相談所等の専門機関が関与していながら、転居などで情報支援が途絶え、事件が浮上し、家庭内では夫から妻へのドメスティック・バイオレンス(DV)による暴力が存在するなどの共通点がみられます。
筆者の目(外視鏡)には、児童虐待がある種、衝撃的ないじめや少年犯罪などが生じさせるmoral panic(モラルパニック:特定の人に対して発せられる多数の人々により表出される激しい感情)と類似しているように映ります。
なぜなら、児童虐待は、少年法やいじめ防止対策推進法などに比べて、子どもが加害者ではなく“被害者”として位置づけられているのですが、虐待する者への処罰や責任を追求するよりも、子どもが健やかに育まれる権利保障がもっと強調されるべきではないかと考えているからです。
世論の中には、“保護されるべき子ども”を救えなかった児童相談所をはじめとする専門機関・専門職や暴力を傍観していた親も含めた保護者への厳しい批判や責任追求の機運が高まっているのではないでしょうか。
さらに、専門職が家族を引き離す際に困難が伴うことや、その際に専門職が親権を適切に行使できない家庭に代わって子どもの親権代行者となる自覚を持つ事の重要性も指摘されています。
深刻さを増すばかりの児童虐待は、いまや世界中で無視し得ない社会現象の一つですが、そもそも、この現象は今に始まったことではありません。
古くは、貧困のため子どもを育てられずに子殺しや子売りなどの形で日本に存在していました。明治期の日本では、親による子殺しをきっかけに、被虐待児保護に着手しつつ、諸外国の児童救済運動に学び、失業や貧困による児童売買、盛り場での児童労働などの防止のため、1933年に児童虐待防止法が制定されています。
しかし残念なのは、戦後の日本では、かつての児童虐待防止法が児童福祉法として吸収されてしまい、消滅してしまったことです。さらに、高度経済成長以降の産業構造の変化に伴って、地域社会の地縁的関係が薄まり、核家族化が進み、社会で子どもを育てる関係性が徐々に後退しました。
国際的な動向として、国連子どもの権利条約が1989年に採択されると、やがて日本でも子育て困難による児童虐待に焦点を絞った立法の必要性が議論されました。それに続いて、虐待の防止等に関する法律(通称、 児童虐待防止法)が2000年に新しく制定されるに至ったのです。
2004年の同法改正では、対象児童を“虐待を受けたと思われる児童”まで拡大解釈しつつ、子どもの前でDVを行うことが子どもに心理的ダメージを与え、発達に悪影響を及ぼすことから、これを心理的虐待とする虐待の定義変更も行いました。
2007年の児童虐待防止法改正では、親権者の意に反して一時保護する職権一時保護や、児童相談所の保護者に対する一時保護、児童養護施設等の入所施設への面会制限等を設けて親子分離を強化しています。
2016年の乳児家庭全戸訪問は、全国1741市町村内1702箇所、実施率97・8%(厚生労働省:乳児家庭全戸訪問事業の実施状況調査より)を占めるまで徹底され、訪問を拒否する家庭こそが最も困難なケースであるとの認識が広がりました。
やがて、虐待する親が、一方的に“子どものために”と語り出したのです。勉強を無理強いする教育虐待や、法律には定義されない大人の不適切な関わり、maltreatment(マルトリートメント:不適切な養育)などが話題となりました。
このように、2000年代以降の児童虐待に対して防止対策を強化してきた日本においても、重大な虐待事件が再現する度、その実態に対して対策が上手く機能していないことが嘆かれています。
日本における児童虐待の実態とは、全国208箇所の児童相談所への年間相談件数が年次推移と共に分析されたものです。児童虐待件数が毎年集計されはじめたのは1990年度からで、統計を取り始めてから毎年連続で増加しています。
国際的にみると、児童虐待への対応は国や地域によって違いが認められます。日本は、アメリカなどと同様、通告と調査に重きを置いた対策を取り入れており、日本での虐待件数の増加もその重点対策と関連があるかもしれません。
子どもを虐待する親から守るために引き離すという重点対策は、一見、“良いこと”のように思われますが、児童虐待の防止対策を最も先駆的に推し進めてきたアメリカでさえ、この通告と調査に基づく政策や実践に対して1970~80年代から批判的な議論が相次いできました。
その議論が導き出したのは、“食物・住居・教育と医療”の基本的に必要なものを適切に提供することなしには強制的な通告の効果が上がらないだろうという警告でした(Sussmanand Cohen, 1975)。
つまり、専門家たちと市民からの通告の奨励によって虐待を未然に防ぐ方法が効果を発揮するためには、何よりも社会保障の整備による保育と医療保険などの基本的なサービス提供が前提とされなければならない(Lindsey; 2004, Gil; 1985, Pelton; 1989)ということなのです。
ですから、日本の児童保護システムの課題は、ケアの脱家族化を軸とした社会保障を整備することが急務ではないかと考えています。
現行のシステムにおいては、養育者が相談に行くこと自体がリスク要因と見なされており、相談に真摯に対応するよりも、“子どもの保護”のための仕組みづくりが作動されがちではないでしょうか。身に覚えのない虐待を理由として子どもを公権力で連れ去られたことを“拉致”されたと思う両親が頻出する恐れがあるのではないかと思っています。
このように、現行の児童保護システムの核心とは、子どものケアの“責任主体は親である”という思想なのです。
それゆえ、介入の対象は、子育てに不都合な社会制度や社会福祉の不足などではなく、親個人ということになってしまいます。この発想そのものが、社会が親を外側に追い詰めたり、子育てに高度のスキルを要求しています。
児童虐待事例を見ると、児童相談所や乳児院での一時保護措置そのものは、親のレスパイトケアになったり親が自分の子育てを相対化できたり、決して一方的に悪くはなかったのですが、親が虐待者として強いスティグマを貼られ続けてきたことが問題なのではないかと考えています。
2015年から、子育て家庭を対象に、幼児教育、保育、地域の子ども・子育て支援の質と量の拡充を図ることを目的に、子ども・子育て新支援制度(内閣府:「子ども・子育て支援新制度」http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/sukusuku.html 2023年1月30日閲覧)が施行されています。
この制度には、保育を必要とする事由に“虐待やDVのおそれがあること”が明記されました。ただし、基本的には働く女性や親族の介護をする場合の子育てを支援するための制度のようです。
養育者側の事情や子どもへの虐待の有無にかかわらず、全ての養育者が制度利用できるように、保育士の労働条件の向上、生活給の保障がなされたうえで普遍主義にもとづいた低価格で良質な保育の選択肢を増やすことなどをさらに進めなければなりません。
保育に欠く、経済的に困窮している、劣悪な住宅に住んでいる等々、児童虐待リスクとして養育者に帰属させられている現在要因の中には、社会政策で改善できることが多いのです。
最近、著者は、児童虐待問題を専門に扱う機関で働くオランダ医師とソーシャルワーカーにインタビューすることができました。オランダにおいてもここ数年間、児童虐待問題に対する政策やサービスの改革が積極的に進んでおり、最新の情報を得ることができました。
通常、こうした機関は、児童虐待というデリケートな問題を扱っていることもあり、外部からの見学やインタビューを受け入れていません。しかし、著者が日本の児童虐待に問題意識を持って取り組んでいることを知ると、わざわざ医師のリストから虐待問題の専門医師を探し出し、その人に連絡をとって私の訪問を計画してくださったのです。
オランダ社会も、児童虐待の問題は深刻に受け止めています。しかし、オランダと日本では、この問題の捉え方や対応の仕方がかなり異なっています。
日本では、例えば深刻な虐待ケースを扱う場合、子どもを保護して施設や里親へ措置しますが、オランダでは、深刻なケースであっても、できるだけ子どもが家族と生活できるよう援助しています。
オランダの社会は、虐待する側の親を犯罪者と見るのではなく、状況によってそうせざる得なくなった“社会的な被害者”と捉えており、その親に対して支援または治療していくことが徹底されているのです。
すなわち、オランダは子と親の家族の繋がりを何よりも重視しており、家族による子育てや生活を社会全体で支援していくことが中心的な理念となっています。
自分たちのあるべき家族や子育ての価値観に基づいて、コミュニティから子どもを簡単に引き離してきたという痛烈な批判がなされてきました。
現在のオランダは、個々の養育者に“理想の親像”を押し付けるのではなく、子どもの成育が直面する困難のひとつひとつを社会で対応していくことが何よりも子どもの養育環境を確実に改善する方策であるという社会全体の変容を成し遂げたのです。
日本における虐待の予防と発生リスクの判定は、単親家庭がリスクであるとされている観点や、あるべき母親像が強く押し出されている点において、特定の家族モデルに基づくものではないでしょうか。
昨今の虐待事件をめぐる世論を分析すると、家族支援の軸となる児童相談所等への激しい批判は、家族と向きあう専門職のパワーを奪ってバーンアウトを誘発したり児童相談所の勤務がきついとのイメージを強固に植え付けてしまうのではないかと考えると、著者の胸中に痛みが走ります。
児童相談所がブラック職場のイメージ化に繋がり、その担い手を減少させてしまい兼ねません。また、虐待が生じた家族への強い批判と犯罪認識は再び子どもと向きあっていく親のパワーをも奪いかねません。
仮に、子どもを何とか保護したいとの思いが専門機関・専門職、親批判へと向かっていくと考えれば、その正義感がさらに虐待問題にかかわる人々を追い込み、事態を悪化させるリスクがあることを鑑みる必要があります。
そのためには、虐待の実態を正しく読み解くリテラシーが求められます。そして、虐待の実態をいかに見つめるべきかを概観しつつ、虐待の未然予防に効果を上げている事例からその教訓を正しく抽出していかなければなりません。
さらに、複合的要因が絡み合って生じる虐待ケースを早期に察知して予防していくには、複数の気がかりな観点について各専門機関・専門職の役割分担によるチーム支援が求められます。
加えて、貧困と虐待との関連を指摘する家族にも目を向け、長期的には支援を受ける側の視点に立って、子育て支援や就労支援等を含めた社会保障、社会政策に厚みを持たせることも求められます。
日本社会には、「最近の子育ては甘い」とか、「以前は悪いことをしたら殴られてしつけられた」との世論が根強く存在しています。「殴ってしつけられた経験」を肯定し、世代間を伝達されてきた側面もあります。
子どもが安全に生活する権利の観点から、暴力を否定し、暴力状況から「SOSの声」を上げること引き出すChild Assault Prevention(CAP)や、関連付けた学校での暴力予防教育も必要でしょう。“罰に頼らない子育て社会”を創出しなければなりません。
最後に筆者が強調したいのは、日本のネグレクト問題です。虐待の内訳に目を転じると、虐待種別では心理的虐待が54%、身体的虐待24.8%、ネグレクトが20%弱となっており、近年では以前トップであった身体的虐待よりも心理的虐待が半数を占めています。
ネグレクト:neglectは、無視する・怠る・疎かにするなどと和訳され、子どもに対するネグレクトは育児放棄や育児怠慢と言われる児童虐待の1つです。具体的には、食事を与えない、不潔にする、病気やケガをしても病院に連れて行かないなどがネグレクトに該当します。
ネグレクトだけをみても、2009年度から2018年度の10年間で、相談件数が2倍に増えています(平成30年度の児童相談所での児童虐待相談対応件数(速報値)|厚生労働省より)。
ネグレクトが子どもに与える影響は一人ひとり異なります。環境的な要因で一概に言うことはできませんが、ここでは、ネグレクトが子どもに与える影響の例をいくつかご紹介します。
まず、食事を与えないことは栄養失調や脱水症に繋がりますし、身体が適切に成長しないことにも繋がります。また、愛情を与えないことは、好奇心や学習意欲の低下、愛着障害や情緒が不安定になることへ繋がります。
他にも、必要な教育を受けさせないことで言語発達の遅れや学力が定着しない可能性があったり、医療ケアや親や養育者の監督が不十分だったことで病気やケガをしたり、事故に巻き込まれる可能性も考えられます。
ネグレクトが原因で、2017年度の1年間で20人の尊い命が失われています。また、大人になってからもネグレクトや虐待の経験がトラウマになり、長い間苦しむことになります(児童虐待による死亡事例の推移(児童数)|厚生労働省より)
一方、オランダ社会においても、ネグレクト問題は深刻に受け止められています。親と子どもが家で一緒に過ごす時間は伸びているのに、ネグレクトを受ける子どもがますます増えているのです。
ネグレクト問題は、どうしてここまで大きくなってしまったのでしょう。この問題を防止していくには、私たちはどのように考え、どのように行動していくべきなのでしょうか。
友人の在米日本人が、「ゆみこ、アメリカでは親子で10歳の娘とお風呂に入ったら逮捕されるのよ。乳児の蒙古斑を虐待の痕だと勘違いして通報されたり、知り合いの父親が人前で娘をげんこつで叱って留置所行きよ」と言っていました。
国を挙げてネグレクト防止策を講じている現在のアメリカ社会は、それだけ児童虐待に目を光らせているという証なのであろうと思います。
アメリカにも、医師や教師、警察官、聖職者ら、子供と日常的にかかわる職業の専門家には罰則付きの通報義務があります。妊娠中と生後2年間は、看護師が定期的に子どもを訪問するなどの外部機関のチェックにも余念がありません。
“National Incidence Study of Child Abuse and Neglect” によれば、身体的・精神的・性的な虐待を受けているアメリカの被虐待児童数は、1993年から2005年の間に26%減少した(性的虐待は38%減、身体的虐待は15%減、精神的虐待は27%減)と報告されています。
まさに、アメリカ式の「親子監視システム」は上手くいっていると言えなくもありません。しかしネグレクトの実態は、同様の報告書によると、1993年のネグレクト被害子ども数が87万9千人、2005年には77万1700人と、増加してはいないがほぼ横ばい状態にあることが明らかとなりました。
ネグレクト問題は、欧米諸国では厳格に処罰を受けます。例えば、米国では州や市によって、対象年齢はまちまちですが、一般的に子どもだけで留守番をさせたり子供だけで町を歩かせるなどの行為は児童虐待に該当し、逮捕・拘留の対象となります。
欧州においても、一般的に12歳以下の子供だけで留守番をさせる、自動車内で待たせる、学校に行かせる等々は違法となり、アメリカ同様、逮捕・拘留の対象となります。
現在日本に居住している欧州の友人は、公園で子供たちだけが遊んでいるとか、子供が1人で電車・バスに乗っているとか、学校に親が送り迎えに来ない日本社会の日常に大変驚いていました。
日本が平和な国だと言う海外の友人がたくさんいます。けれども、これからはアメリカのように、地域全体で親の子育てに目を光らせるような社会にならないといけない時代が訪れるのでしょう。
そうなると、さらに息苦しい社会になりそうですが、そこまでしないと救えない命もあると考えるべきなのでしょうか。
子どもを物凄い剣幕で叩いたり蹴ったりしている親を見つければ通報することは、誰にでもできる児童虐待防止策であると思います。子どもに直接危害を加えるような積極的な虐待は周囲の人でも発見できるからです。
しかし、ネグレクトは、社会との接点がありません。閉鎖された家庭内というプライベート空間で行われるので、行政や民間が努力したところで直接の防止策とはならないことが大きな課題となります。
むしろ、国として取り組んでいかなくてはいけない防止策とは、もっと根本的な部分かもしれません。それは世界的に言われていることなのですが、格差社会における“貧困と孤立”という問題です
アメリカでは、健康保険制度が充実していないことに加えて、ティーンエージャーの望まない妊娠問題などが顕在化しており、貧困率と犯罪率は共に先進国のなかでもトップクラスです。日本においても、母子家庭の貧困率は66%と突出しています。
フィンランド国立健康福祉研究所は、母親が支援なく放置されると子どもを虐待する傾向があることを指摘し、大変危惧しています。
もちろん、“母子家庭=虐待”とする安易な結びつけは全く間違っています。しかし、閉鎖的な家庭の中では、育児の重荷を分かち合うことができず、働けど働けど金銭的にも精神的にも苦しい親が現実に存在しているのです。
対策として虐待されている子を発見するのではすでに遅いのでしょう。“貧困と孤立”の問題が増えている社会こそが大問題なのです。
ですから、著者は、我が子をネグレクトしてしまうような余裕のない親たちを作らない社会づくりこそが大切ではないかと考えています。
悲しい現実が指摘されています。子どもの頃に虐待やネグレクトを受けて育つと、その子が大人になっても、ずっと心に深い傷を負って生きることになることです。
虐待を受けた子の70%は、自身が親になったときに子に虐待してしまうとも言われています。さらに、社会において暴力・ドラッグ・犯罪の増加、精神疾患罹患の増加やSafe sex(セーフセックス:性感染症HIV発症を予防した性行為)の減少へ連鎖することが指摘されています。
現在、オランダは、労働政策や育児政策の効果により、全体として女性の社会進出がかなり進んでおり、国連開発計画(UNDP)によるジェンダー・エンパワーメント指数(GEM: 政治・経済での女性進出度)において、109か国中の第5位です。
Gender Gap Reportによれば、オランダの男女格差の少なさに対するオランダの世界ランクは全体の中で11位です。
オランダ社会が伝統的な性別役割分業意識の変革を受け入れ、女性の労働市場への参画を推進させたのは、パートタイム労働制度の好影響でしょう。
オランダ社会のライフ・ワーク・バランスは、Wet Onderscheid Arbeidsduur: 労働士官差別禁止法(1996)、Wet Aanpassing Arbeidsduur:労働時間調整法(2000)、Wet Arbeids en Zorg:労働とケア法(2001年)、Wet Kinderopvang:育児法(2005)ともリンクしています。
日本の現況はどうでしょう。日本の育児政策では、産前産後休暇は14週間です。給与の67%が健康保険より給付されますね。また、育児休暇は1年間で給与の50%が保障されているようです。
育児休業改正法(2008)によって、3歳までの子がいる労働者に対しては、一日6時間までの短時間勤務制度設けられています。父親の育児休暇は1年から1年2か月へ延長されており、パートナーの夫が専業主婦でも育児休暇が取得できるようになっています。
しかし、育児と仕事を両立できるはずのパートタイム労働の環境にいまだ多くの問題が存在しています。ですから、労働意欲はあるのに働かない(働けない)日本女性も多いのでしょう(男女協働参画社会に関する意識調査より)。
女性の離職理由として出産や結婚が大きな割合を占めています。このことは、日本女性が育児だけでなく家事労働も賃金労働と両立しがたいと感じているからなのでしょう。
すなわち、日本では、労働継続の希望と現実に差異が存在しているのです。オランダと比較すると、日本における育児政策や女性対象の労働政策は、まだ不十分であるといえそうです。
欧州は比較的性別分業体制が強く、オランダでさえ、以前は女性の労働にほとんど配慮してきませんでした。だからこそ、現在のオランダにおけるジェンダーおよび家族、労働などの先進的な政策は、近未来の日本においても、一つの新しいモデルになる可能性を秘めています。
このような視座から、著者はオランダと日本を比較して考えることに多くの意義を感じています。オランダ社会の急激な変容は、日本を勇気づける多くのヒントを持っています。
社会には、保護者が一人親であったり、所得が低いだけでなく、社会的に“孤立”している場合が多く見られます。また、母子家庭で“貧困”な状態にあるのに生活保護を受給していないなど、社会に頼ること自体に罪悪感を抱いている人もいます。
法整備で親を責めたり縛ったりしても虐待は決して減っていません。必要なのは、家族を支える社会の資源です。
ネグレクトは、子どもの命を失うことになりかねません。ただし、親や養育者だけに責任を押し付けていいものではないのです。
ネグレクトの実態を考えると、社会を構成する私たち一人ひとりが、何ができるかを考えながら実際に行動を起こすことが大切です。
日本も、そのことに気づいたようです。“子育て”は、家庭内で抱えるものではなく、社会でシェアすべきものであり、虐待防止のためには、社会が子育てをシェアすることが不可欠であると、著者は確信しております。
社会で子育てをシェアするとは、どうしたらよいのでしょう。虐待が起こってしまった時、親を責めてもむしろ、自己責任論が強くなればなるほど家庭で完璧に子育てをしなくてはならないという社会的な“孤立”を促してしまいます。そうなれば減るのは虐待件数ではなく子どもの数です。
児童養護施設には虐待を受けた子どもたちが暮らしています。その中には、乳児期に虐待にあい保護されたものの何度も施設や里親の間をたらい回しにされ、大人や社会への信頼を完全に失ってしまった子どもたちがいます。
子ども側から見れば、虐待から逃れられても大人の都合で居場所をなくした子どもの心の傷が消えることはないでしょう。虐待が起こり、保護して里親や施設に委託すれば、その問題が永遠に解決するということは決して起こらないのです。
著者の思いは、子ども側が社会の主体として尊重された生活を送れることが大切であるということです。そのためには、大人中心の一方的な子育て支援から脱却し、子どもと親が一緒になって遊んだり、多様な大人が日常的に相談に乗り合うことで、子育て負担をシェアできる社会のコミュニティを広げていくことが必要です。
例えば、日本にも子どもを遅い時間まで預かるトワイライトステイ(家族安心センターなど)があります。さらに、放課後児童の居場所づくり、学習支援や食事の提供、保護者などの養育相談などの場が増えることを願っています。
そのほか、野外活動や演劇などを通した交流プログラムや家庭への訪問活動、人材育成の場としての機能も大切でしょう。
日本社会の表側に、開かれた明るいテラスのような空間が拡がり、カフェに立ち寄るような気分で大人と子どもが気軽に立ち寄り交流できる日常的な場が増えていくことを願っています。
やがて、虐待にあったかわいそうな子どもだけが行く場というような、児童養護施設に対するマイナス・イメージも減ることでしょう。「子育てや教育を頑張りましょうということではなく、大人も子どももみんな、一緒になって育っていきましょう」という、著者からのメッセージを送ります。

【筆者紹介】
薬剤師(日本)。1989年渡米。1997年帰国。三井記念病院勤務などを経て2015年渡蘭。ALS女性の在宅介護を経験。2000年、コロナ禍に一時帰国。ユマニチュードを学んだ経験から(写真1)、認知症の父を在宅ケアしていた(写真2)。父の施設入所を経てオランダへ戻る。フリーライターとして執筆や取材が多い日常を過ごす。言語学者(エスペラント語)の祖父、高等学校英語教師の父を持ち、語学・教育・医療・介護に造詣が深い。
アクセス先:yoomee.0126@gmail.com

写真1 右は島崎由美子さん、左はフランスのジネスト・マレスコッティ研究所創設者で所長を務めるイヴ・ジネスト特任教授(2013年当時、東京)

写真2 コミュニケーションにおける出会いの準備とケアの準備、そしてケア行為を始めた島崎由美子さん。着衣・排泄ケアへと身体的負担が続く