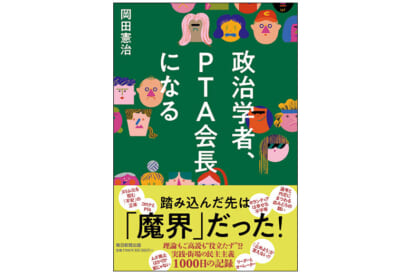一刀両断 実践者の視点から【第691回】
NEWS
児童・生徒の学習評価、何のためか問い直せ
文科省が、児童・生徒の学習評価のうち「学びに向かう力・人間性等」について、目標との比較ではなく、その子ども自身の成長に注目した「個人内評価」とする方針を示した。ようやくここまで来たか、という印象を持った。
この個人内評価を前向きに受け止める教師がいる一方で、苦手とする教師もいるのが現実だ。ある学生が、こんな話をしてくれたことがある。担当の大学教授が「どんなひどいレポートを書いてきても、私の給料には関係ないから」と言ったという。その教授は元高校教諭で、県の教員採用にも関わった経験があり、大学でも長年教えてきた人だった。それでも大学では、こうした教員に対して誰も指導しない。
もしこのような人間性の教師が個人内評価を行うとしたら、形式的・事務的な記述しかできないだろう。そんな姿が目に浮かぶ。
また、不登校の児童・生徒に対しては、今でも通知表に斜線が引かれることが多い。これを見て「頑張ろう」と思える子がいるだろうか。そもそも、評価は何のためにあるのか。そこを改めて問い直す必要があるのではないか。
フィンランドでは、評価が本格的に始まるのは高校段階からだという。それに比べて、日本のように、まるで烙印を押すかのような評価が今も続いているのはなぜなのか。本来、評価とは子どもたちにやる気を起こさせ、励まし、成長を支えるためのものではないのか。
現場を知らない学者が制度を決めているから、こうした問題が繰り返されるのではないかと感じる。
(おおくぼ・としき 千葉県内で公立小学校教諭、教頭、校長を経て定年退職。再任用で新任校長育成担当。千葉県教委任用室長、主席指導主事、大学教授、かしみんFM人生相談「幸せの玉手箱」パーソナリティなどを歴任。教育講演は年100回ほど。日本ギフテッド&タレンテッド教育協会理事。)