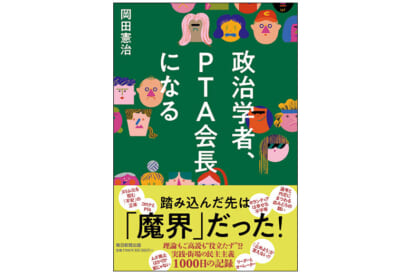一刀両断 実践者の視点から【第692回】
NEWS
溺れている人を助けるには
14日から「子どもの事故防止週間」が始まる。今年は「水難」に焦点を当てるという。警察庁の集計によると、昨年は中学生以下だった28人が水難による死亡や行方不明となったとのことである。この数をどう見るか。
28人の一人一人に家族や友達が居るし、恩師やご近所など多くの人々が関わって来たはずである。日本は海に囲まれ多くの川が生活とつながっている。
川で溺れて亡くなったという話は何度も耳にした。水の怖さは知られているものの、「自分ごと」に出来ない甘さが不幸な事故を生む。
実際に水難事故に巻き込まれたり見聞したりするとその悲惨さが焼き付いて離れなくなる。単に「気をつけましょう」では、言葉だけが上滑りしやすいものである。
ある意味、溺れる苦しさを知る事も必要に思える。すなわち自分の息の限界を知ると言う事である。
溺れている人を発見すると助けたいと思い飛び込もうとする人は多い。だが、浮きそうなものを投げ込むなどして対処しなければならない。飛び込んで、相手にしがみつかれたら並の泳力では対応できない。
私のバッグには、買い物に使用したビニール袋、ヒモ、ペンライト、笛、タオルなどを常備している。いざとなった場合、タオルであれば、持って近くまで泳ぎ、投げ拡げて捕まらせるのである。手繰り寄せたらすぐ離してを繰り返して牽引するのである。
笛で多くの人を呼び寄せる事も出来る。草笛も得意である。飛び込むのは最後の方法と捉えている。
(おおくぼ・としき 千葉県内で公立小学校教諭、教頭、校長を経て定年退職。再任用で新任校長育成担当。千葉県教委任用室長、主席指導主事、大学教授、かしみんFM人生相談「幸せの玉手箱」パーソナリティなどを歴任。教育講演は年100回ほど。日本ギフテッド&タレンテッド教育協会理事。)