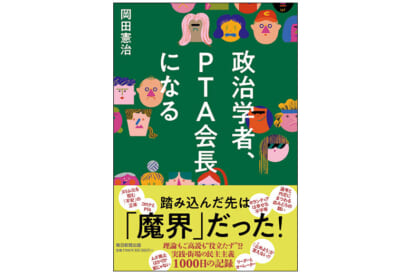クロスロード 交差する視点(8)地域大学の存続 支える社会を
8面記事
大森 昭生 共愛学園前橋国際大学学長
今、地方にある大学のことが注目されている。各種の報道、国の審議会で、これほどまでに地方の大学にスポットライトが当たったことがあっただろうか。文科省には「地域大学振興室」も新たに設置された。地方に大学があることの価値が「ようやく」社会に理解され始めたことはうれしい。
しかし、この動きは地方の大学の危機の裏返しでもある。筆者が座長を務める文科省の「地域大学振興に関する有識者会議」では地方の学生を特別委員に任命した。本学から参加した学生は「地元国立大に合格できず本学に入学したが、本学がなければ進学を諦めていた」と述べた。大変優秀な学生である。このような学生が大学に行けなくなる未来を創ってはいけない。
これまで地方の大学は地域と一体となって学生を育ててきた。本学もその一つであり、地域に必要とされ、学生数も確保してきた。多くの大学が地元の若者の定着や社会基盤を支える働き手の育成に貢献をしていることは言うまでもない。その努力は今後も当たり前に続けられていくだろう。
一方、「知の総和」答申を境に、地域での連携は次の段階に移行したともいえる。個々の大学の努力だけではあらがえないという認識がそこにはある。自分の大学の存続という思いにふたをして、大学同士が国公私立の壁をも超えてタッグを組み、地域の若者が地域で学べる環境を維持するための取り組みが求められる。その際、地域の役割も重要となる。これまで、大学のことは地域の「自分ごと」ではなかった。しかし、地域の大学の課題はそのまま地域課題なのであり、地域がどのように大学を支えるかを真剣に考える時が来ている。
いまだ中央では恣意的な資料を基に「定員割れ大学」の私学助成を減ずる議論がなされたりしている。むしろ定員割れだからこそ助成されるべきではないのか。地域のために歯を食いしばって頑張っている大学たちが称賛され支援される社会になることを望みたい。