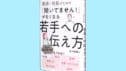授業づくりの言い換えことば 「うまくいかない」に効くフレーズ
16面記事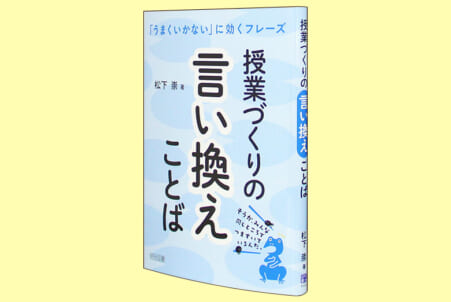
松下 崇 著
無理なく始める改善の提言
現在、各学校では、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善が求められている。だが、授業の中で、子どもたち一人一人に合わせたケアなど、教員の行う業務が格段に増えていることも事実である。
そのような状況下、著者は「授業改善は自分のできる範囲で行っていくのが現実的」であると考え、言い換え言葉に視点を当てた授業改善を推奨している。特に、序章の「『言い換え』るために、知っておくべきこと」では、教師の子どもたちに話す言葉を「発問」「説明」「指示」に分け、それぞれの特性を生かしバランス良く指導することの重要性が書かれている。著者は「このことを意識するだけで、授業が格段に改善される」と述べているが、著者同様、このことを授業改善の新たな視点と捉える読者も多いのではないだろうか。
第2章の「『うまくいかない』に効く!言い換えフレーズ」では、「授業スタート時に子どもたちがバラバラ」な場面、「授業と関係のないことをしている子どもが増えてきた」場面など、それぞれの状況に応じた言い換えフレーズが示されている。だが、それでも改善ができない場合を想定し、「それでもうまくいかないときは…」というコーナーも用意されており、日常の授業につまずきを感じている読者にとって、大いに参考になる一冊と言えるであろう。
(2090円 明治図書出版)
(小山 勉・東京未来大学特任教授)