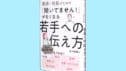「愛と知の循環」としての保育実践 多様で豊かな世界と出会い、学び、育つ
16面記事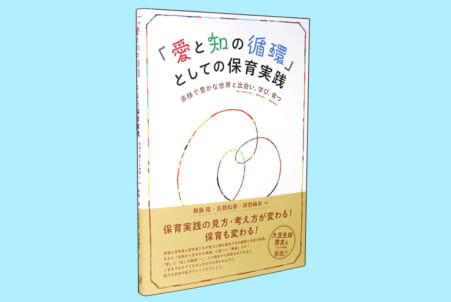
無藤 隆・古賀 松香・岸野 麻衣 編著
遊びを楽しみ 世界を開く
日本の幼児教育・保育の実践を研究者と実践者が対話しながら「愛と知の循環」という理論で捉えようと試みた。
「愛と知の循環過程」について「遊びの楽しさはその活動と対象を肯定し、繰り返しの中で好きになり、言い換えると愛することとなる。それは対象を詳しく知ることと相まって、続いていく過程となる」との解説は「愛」と「知」の関係についての読者の理解を助けてくれる。
本書の約4分の3を占める各園での実践の記述(第Ⅱ部第4~12章)は、幼児がさまざまな「遊び」に没入していく姿を見取ったものだ。のめり込む心の動き、遊びの世界を増幅する周囲の幼児の言動。共に遊びを楽しみ、共感できる指導者の姿がある。幼児の好奇心や疑問が大切にされ、やりたいことを実現できる空間の心地よさが心を育み、世界と出合う。
第Ⅰ部の理論編には、園の運動会のために幼児らがポーズを考えながら体操を作っていく活動を見た小学校教師の「こんなにも子どもたちと共に作るのかと驚き、いかに小学校の運動会が逆算的な思考で、過程より結果に重点を置いていたか」という反省の弁が紹介されている。
幼児に関わる指導者には有用な書であるのはもちろん、教えることの多い小学校以後の学校に知の循環はあっても、そこに「愛」を育てる環境はあるのかと、問い掛けてくるような一冊である。
(2750円 北大路書房)
(矢)