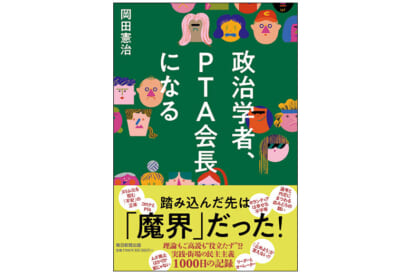一刀両断 実践者の視点から【第696回】
NEWS
学校管理職に法教育セミナーを
法務省が来月、「学校現場と法律実務家との連携」を主題とする法教育セミナーを開催するという。これは非常に有益な取り組みだと思う。
学校現場では、法解釈が学校風土の中で誤って理解されたり、「教育的配慮」という名のもとに法の解釈が歪められることが少なくない。
教育関係の法規集は存在するが、そこには最新の判例などが反映されていない場合も多い。
以前、「動く六法全書」と呼ばれた人物と対話する機会があったが、その際に強い違和感を覚えた。理由は、判断の視点や解釈に一貫性がなく、結果として誤った判断が繰り返されたことだ。
専門用語を多用し、周囲に「わかったふり」を見せていたが、それは単に法学部出身であり司法試験を受けていたという噂によって「法に詳しい人物」というイメージが作られていただけだったのだろう。
法的知識と実際の判断力とは別物であり、その違いが学校現場では十分に理解されていない。
そうした意味でも、今回の法教育セミナーは「必須」と言っても過言ではない。特に管理職にとっては、法の理解を中途半端な知識で済ませることが許されない時代になっている。
(おおくぼ・としき 千葉県内で公立小学校教諭、教頭、校長を経て定年退職。再任用で新任校長育成担当。千葉県教委任用室長、主席指導主事、大学教授、かしみんFM人生相談「幸せの玉手箱」パーソナリティなどを歴任。教育講演は年100回ほど。日本ギフテッド&タレンテッド教育協会理事。)