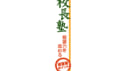校長塾 経営力を高める最重要ポイント【第543回】
4面記事堀越 勉 千代田区立麹町中学校校長(東京都中学校長会会長)
授業は教師の生命線
「研究」で学校を立て直す
学校を立て直すには、教員が一致団結して取り組む「何か」が必要だ。
授業研究は、外部からの指導・助言を受けながら教員の指導力が向上できるとても有効な手だてである。
教員研修は、学校教育の質的向上を図るためにも重要であり、法令に定められた行為だ。本校では、全校組織での研修の脆弱さが課題であった。研修とは、「研究」と「修養」である。修養ばかりを行い「研究」が定着しない経緯が続いてきた。個人や一部の教員による研究はあったが、共通テーマの下での全教員挙げての研究授業が行われてこなかった。
本校に着任以来、一度も研究授業を公開していない、あるいは学習指導案すら書いていない教員が大半であった。「学習指導案は必要ない。楽しい授業をすればよい」といった妙な理屈がまかり通る学校だと伝わってきた。
千代田区には、幼、小・中が連携して研究を行う「教育会」という自主研究組織がある。これにさえ、本校教員は、長期にわたり離脱してきた。
令和4年度、私は区内の別の中学校で校長をしていたが、長田和義前校長と相談し「新教育会」として中学校の授業研究組織を改めて立ち上げた。令和5年度からスタートできるよう、年間2回の全教科にわたる研究授業・研究協議会を設定した。学習指導案検討は、リモートを活用し、区内の中学校籍の教員が意見を交わし合う仕組みをつくった。本校が長年鎖国状態であったことから脱却する大きな一歩目となった。
昨年度、学校運営協議会委員の学識経験者から授業研究の必要性の指摘を頂いた。令和6年度からの区の研究協力校の指定を申請した。テーマを「授業で学校を立て直す」とした。研究指定であるから、本来は先進的な教育を導入して「未来」を見せていくのが使命なのかもしれないが、本校は真逆だ。長年にわたる授業研究の軽視が、教員の指導力の低下、生徒の学力の低下、そして学校の荒れへと連鎖してきた一因と考えられる。この現状に正対し、授業研究を手掛かりに一から学校を立て直す決意である。
研究指定を受けるに当たっては、2学期の自己申告前に、令和6年度の学校経営方針と研究の在り方を明示した。研究から逃避傾向の教員もいるので、後出しではなく、事前に理解を深めることがポイントである。
生徒全員が安心して意欲的に授業に臨むことができる学校を目指し、授業規律の在り方から取り組んでいく所存である。