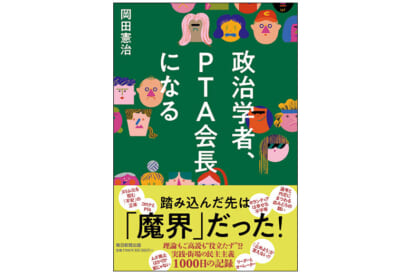理科における生成AIの活用 問いを深め、学びを広げるパートナーに
11面記事
生成AIは社会生活のあらゆる分野に浸透している
社会生活へ影響する存在に
生成AIの急速な進化は、私たちの社会や仕事、生活のあらゆる側面に大きな変化をもたらしている。仕事面では、文章作成やデザイン、データ分析などの業務が効率化され、特に単純作業の自動化によって生産性が向上。これにより、人手不足の解消やコスト削減が期待される一方で、一部の職種では代替の可能性も指摘されている。
生活面では、AIによるパーソナライズされたサービスが普及し、買い物や学習、医療などがより便利で快適になっている。例えば、個人の好みに応じた商品提案や、健康管理のサポートなどが挙げられる。
社会全体としては、創造性の拡張や新たなビジネスの創出が進む一方で、偽情報の拡散や著作権、倫理的課題といった新たな問題も浮上している。
学校現場も例外ではない。一般向けの汎用的な生成AIサービスが利活用可能な状況にあるだけでなく、1人1台端末の標準仕様であるブラウザや学習支援ソフトウェア、普段利用する検索エンジンなどにも組み込まれるようになっているからだ。
生成AIを有用な道具として活用する
こうした実態が見られる中で、文科省の「初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン」では、「生成AI自体を学ぶ場面」、「使い方を学ぶ場面」、「各教科等の学びにおいて積極的に用いる場面」を組み合わせたり往還したりしながら、生成AIの仕組みへの理解や学びに生かす力を高めることをポイントに挙げている。
その上で、これからの情報社会において求められる資質・能力の育成として、「生成AIをはじめとするテクノロジーをツールとして使いこなし、一人一人が才能を開花できるようになることは重要であり、生成AIの学校における利活用は、そのための助けになり得るものである」としている。
理科における生成AIの活用例
GIGAスクール環境を使った効果的な実践を集めた文科省の「リーディングDXスクール」では、全国の小中学校での生成AI活用事例が多数紹介されている。それを見れば、理科に限らず、生成AIを使った仮説検証・レポート作成・観察記録の整理など、さまざまな授業での応用が進んでいることが分かる。
その中で、理科の授業においては次のような生成AIの活用が考えられる。
【小学校】
①身近な生き物の生態を調べる(文字生成AI):児童が生き物の生態に関する疑問を質問し、AIの回答をもとに図鑑やインターネットなどで照らし合わせて調査。探究心と情報の信頼性を見極める力を育成する。
②理科観察記録の要約(文字生成AI):児童が記録した観察メモをAIに要約させ、日ごとの変化を整理。記録の振り返りと要点整理の力を育てる。
③動物の生態イラストを生成(画像生成AI):「夜行性の動物のすみかがどうなっているか」を生成AIにイメージしてもらうためのプロンプトを入力し、画像を生成する。視覚的理解と想像力の育成を図る。また、低学年でも、児童が親しみやすい生成AIと接続されたロボット教材を使って質問し、回答をもとに考察を深める授業が行える。
【中学校】
①実験レポートの構成支援(文字生成AI):1年の単元「物質のすがたと変化」などで行った実験結果を入力し、AIにレポートの構成案を提案させて、論理的な文章構成力を育成する。
②化学反応のアニメーション生成(画像生成AI):2年の単元「化学変化と原子・分子」などで、生成AIに「酸とアルカリの中和反応の様子」を描かせ、視覚教材として活用。抽象概念の可視化を図る。
③気象データの可視化プログラム作成(プログラム生成AI):3年の単元「天気の変化」などで、AIにPythonコードを生成させ、気温・湿度のグラフを自動作成。データ活用とプログラミング的思考を育成する。
【高校】
①生物多様性に関する英語資料の翻訳(文字生成AI):生物基礎の教科などで、英語の科学資料をAIで翻訳し、内容理解を深める教科横断的な学びに活用する。
②地震被害の仮想シナリオ作成(画像生成AI+文字生成AI):地学の教科で、架空の地震被害を生成AIで文章・画像生成し、防災意識を高める教材を作成。防災教育と創造的思考の融合を図る。
③実験手順の自動生成(文字生成AI):化学の授業で、活用目的と使用薬品を入力し、AIに実験手順を提案させる。これにより、手順の論理性と安全性の検討を学ぶ。
④プログラムによる物理シミュレーション(プログラム生成AI):物理の授業で、AIに「斜面を転がる物体の運動シミュレーション」をPythonで生成させ、実験と比較。数式と現象のつながりを体感する。
探究・可視化・論理的思考を深めるために
これらの事例から分かるように、生成AIは「答えを教える道具」ではなく、問いを深め、学びを広げるパートナーとして活用し、理科の本質的な学び(探究・可視化・論理的思考)を深めるものにすることがポイントになる。