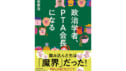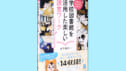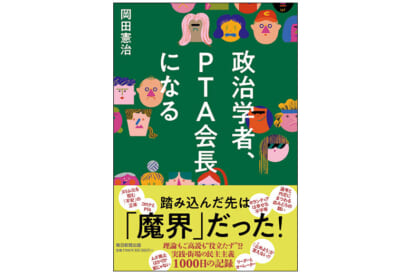初任大学教員と熟達大学教員の協働的メンタリング研究 教員養成カリキュラムの社会科授業科目を事例に
18面記事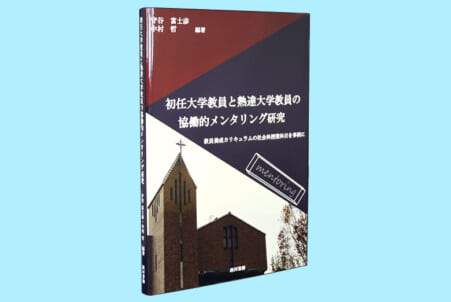
守谷 富士彦・中村 哲 編著
若手の実践変容の背景を分析
大学の教育改革といえば、教授内容の改善に重点が置かれ、カリキュラムや授業実践に研究の関心が向けられがちだが、本書は、それらを計画・実践する人、主体である教師・教育者に焦点を当てた研究をまとめたもの。
桃山学院教育大学(4月から桃山学院大学人間教育学部に改組)教員養成カリキュラムの持続的構築シリーズの第6巻に当たり、第5巻「教員養成カリキュラムの持続的構築―教育大学としてのメンタリングの方法と意義」の続編に位置付く。
教員養成大学の教員で、本書の編著者である守谷氏(初任大学教員、メンティ)と中村氏(熟達大学教員、メンター)が4年間にわたり協働的メンタリングを実施し、計87回に及ぶ対話を行った。それにより、初任大学教員のカリキュラムは次第に変容し、自身の教師教育観や研究者としての学問観も変容した。本書では、その変容の具体的事実と、その背景にある対話が生々しい姿で開示され、理論的根拠の解明に迫っている。
初任大学教員も4年間の指導経験を積めば、意識的・無意識的に授業を変化させていくが、それは漠然としたカリキュラムの変容にすぎない。本研究は、変化の事実、その背景、今後の課題を明確化したところに意義がある。学問的共有化を図り、個別大学から大学全体のカリキュラム向上、組織的教師教育の変革や創造につながることが期待される。
(2200円 銀河書籍)
(規)