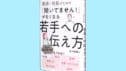統治機構改革は教育をどう変えたか 現代日本のリスケーリングと教育政策
17面記事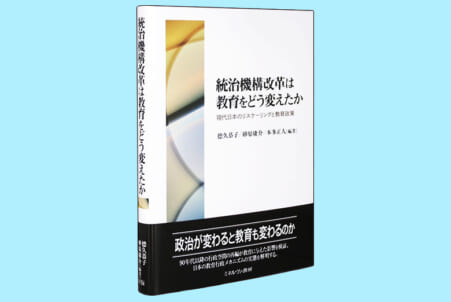
德久 恭子・砂原 庸介・本多 正人 編著
分権以降の枠組みが与えた影響
「政治学、行政学、教育行政学を専攻する研究者」が主に地方分権改革以降の統治の変化をにらみながら、「統治空間の構成の『スケール(水準)の引き直し』」という「リスケーリング」を切り口に教育への影響を論じた。
本書第Ⅱ部第7章「イギリス教育政策におけるリスケーリング」は二大政党の政権交代のたびに「政治主導的改革」によって省庁の構成を含め、様変わりする教育の姿が提示されている。本書の意味する統治が与える教育の変化を端的に示し、分かりやすい。
ここまで劇的ではないにせよ、わが国でも、標準化を志向する「教育の論理」の貫徹を旨とする文科省などとは別に、「市場の論理」や規制緩和を背景にして、教育を変えようとする動きは活発化した。
第Ⅰ部「教育・市場・政治」では政治改革と教育改革などで、こうした流れを解説し、第Ⅱ部「リスケーリングと教育」ではアンケート調査を基に教員人事や教育事務所を取り上げ、その変化などを論じた。
首相直属の諮問機関である臨時教育審議会(臨教審)の設置や、首長主導の地方発の教育改革など「教育の論理」とは趣を異にする軸の出現に、当時の「教育の論理」順守派は「黒船」や「対岸の火事」と評した。いずれにしても、“外圧”と感じた人が少なからずいたという印象がある。
政府間関係、首長など、教育を論じる枠組みの変化に着目し、意欲的な一冊だ。
(4180円 ミネルヴァ書房)
(矢)