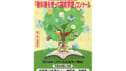卒業記念品選びに必要な視点とは
14面記事
「今の時代にふさわしい」卒業記念品を選びたい
寄贈品のトレンドは学習支援や防災対策
卒業記念品を贈る意義
卒業記念品とは、子どもが学校生活を終え、新たな一歩を踏み出す節目に贈られるものであり、教育現場において重要な役割を果たす存在である。単なる物品にとどまらず、学校で過ごした日々の思い出、仲間とのきずな、教員との関わり、そして自身の成長を象徴する「記憶のメディア」として位置づけられている。
その意義の1つは、卒業生の歩みに対する「祝福と励まし」である。記念品は、新たな環境への期待と不安の入り混じる中で、過去を肯定し、未来への力を与える装置となる。例えば、校章入りの文房具や辞書などは、卒業から何年が経過しようとも、日常に寄り添いながら自分のルーツを思い起こすきっかけとなるものだ。
2つ目は、「学校文化の継承とアイデンティティの形成」である。記念品は、その学校が大切にする価値観や教育理念を反映するものであり、子どもにとって「自分はここで育った」という自覚を促す。特に長い歴史を持つ学校では、代々の卒業生に受け継がれてきた記念品のスタイルや伝統が、学校の文化的アイデンティティを形成する重要な要素の一つとなっている。
3つ目は、「社会との接続と持続可能性への配慮」である。昨今では環境負荷や実用性を考慮した選定が求められており、地域産品や福祉作業所との協働による記念品制作などが注目されている。これは、単なる贈り物を越えて、子どもたちが社会とのつながりを意識し、持続可能な価値を理解する教育的機会ともなる。卒業記念品は、そうした社会的・環境的配慮を体現する教材にもなり得るのだ。
子ども主体で選定するケースも
卒業記念品の選定は、学校の卒業対策委員会やPTAが中心となって行われることが一般的だ。特に小・中学校ではPTAが主導し、保護者の代表が集まって話し合いを重ね、候補となる記念品を選定することが多い。一方で、近年では子どもが主体的に関わることを重んじ、高校などでは生徒会が中心になって選定するケースも増えている。
選定の流れとしては、まずアンケートや意見交換を通じて卒業生や保護者の希望を集める。その後、予算や納期、実用性、記念性などを考慮しながら候補を絞り込み、最終的に業者と相談して発注に至る。現在はオンラインでのカタログ閲覧や見積もり依頼が可能になり、選定の効率化が進んでいるのも特徴だ。
大半の学校では、秋から冬にかけて(9月~12月)卒業記念品の選定が行われる。特に名入れやオリジナルデザインを施す場合は制作に時間がかかるため、この時期に選定を始めることで、納期に余裕を持って発注することができるからだ。
卒業記念品の予算
卒業記念品の予算は、学校の規模や地域、学年によって異なるが、おおよそ小学校1~3千円、中学校3千~5千円、高校5千~1万円が目安になっている。ただし、都心部の私立学校の場合は、これを超える金額を設定しているケースもある。予算は、PTA会費や卒業対策費から捻出されることが多く、全員が負担可能な金額であることが求められる。また、名入れや包装などの追加費用も考慮する必要があるため、複数の業者から見積もりを取ることをお薦めする。
このほか、近年では少子化や教育熱の高まりにより、学校全体での記念品とは別に、クラブ活動やクラス単位で卒業記念品を用意することも多くなっている。クラブ活動では、ユニフォームや部旗をモチーフにしたグッズ、集合写真入りのフォトフレーム、部員全員の名前が入ったタオルなどが人気となっている。クラス単位では、オリジナルなデザインのTシャツや文房具、寄せ書き入りのアルバムなどが選ばれている。これらの記念品予算は1~3千円程度で、クラス費や部費から支出されることが多い。
卒業記念品のトレンド
近年の卒業記念品は実用性や個性化が好まれる一方で、環境に配慮した商品やデジタル時代に即したアイテムも人気になっており、従来の定番品の中でも多様化が進んでいる。
【小学校】
卒業生に贈る記念品では、安全性と実用性に配慮したモノが中心になる。文房具やマグカップなど日常で使えるアイテムが人気で、校章や名前入りにして特別感を演出するケースが多い。また、思い出を共有するアイテムとなるクラス写真入りフォトフレームや寄せ書きアルバム。環境配慮型グッズでは、リサイクル素材のエコバッグや竹製の文具なども。
学校に寄贈する記念品では、在校生の学びや生活環境の改善に役立つ設備が主流になっている。中でも増えているのが、電子黒板やプロジェクター、カラープリンターなどのICT機器になる。また、式典・イベントに使う講演台や大型テント、音響機器も根強い人気を誇っている。
【中学校】
卒業生に贈る記念品では、学習支援や成長に合わせて使える実用的なアイテムが人気だ。例えばステンレスボトルやモバイルバッテリー、電子辞書などのほか、複数のアイテムから選べる「セレクト式記念品」も導入されつつある。加えて、間伐材・リサイクル素材などを使った木製の時計やフォトフレームなど、地球にやさしい素材で作られたエコな記念品の需要も高い。
学校に寄贈する記念品では、探究学習支援機器:理科実験用センサー、顕微鏡、理科実験用ガスコンロなど。ICT環境の拡充:タブレット保管庫、Wi―Fiルーター、長尺印刷機など。防災・衛生設備:冷水機、サーキュレーター、備蓄用品など災害対策を意識した寄贈が増加している。
【高校】
卒業生に贈る記念品では、印鑑・印鑑ケース、名刺入れ、ブランド文具など、進学や社会人生活を意識したアイテムが選択されるようになる。また、クラウドを活用した学校活動や学習データの蓄積が進んだことで、記念動画やデジタルアルバムといった思い出コンテンツを作成する学校も増えている。
学校に寄贈する記念品では、教育の質向上を支える設備:3Dプリンター、ロボット教材、映像編集や英語学習ソフトなど。校内環境の整備:スピーカーシステム、空調設備、照明機器など。
新たな視点で選定する工夫を
卒業記念品は、単なる贈り物ではなく、「感謝」「祝福」「未来への応援」を形にするものだ。最近では、子どもの個性や進路に寄り添ったアイテム選びが進み、学校への寄贈品も「後輩のため」「地域のため」といった視点が加わり、より社会的な意味を持つようになっている。
その中で、選定にあたっては、保護者・教職員・生徒の意見を丁寧にすり合わせ、「思い出に残る」「役立つ」「心がこもっている」という3つのポイントを意識することが、満足度の高い記念品につながると考える。