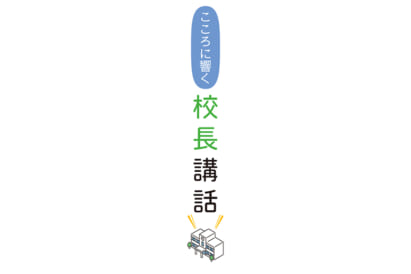哲学のたねを蒔く学校
14面記事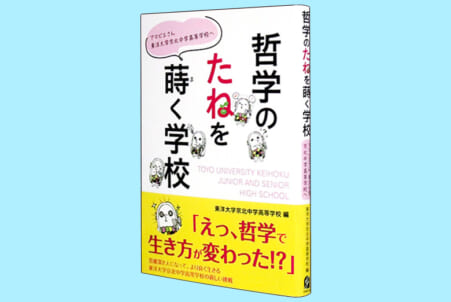
東洋大学京北中学高等学校 編
思考のトレーニング法を模索
「三田の理財、早稲田の政治、白山の哲学」と称されたことがあったという。慶應義塾の福沢諭吉、早稲田の大隈重信はそれぞれの大学の創始者であることはよく知られている。東洋大学が「白山の哲学」と言われたのは創始者・井上円了が哲学者であり、大学の前身が哲学館として出発したためだ。大学では創立125周年を機に、基本方針の一つに「哲学教育」を打ち出している(『井上円了 「哲学する心」の軌跡とこれから』講談社編)。
その附属校である京北中学高等学校が平成27年4月、男子校から男女共学へと衣替えし、6年間一貫の「哲学教育」のカリキュラムを模索し、進行中の実践を報告したのが本書である。
中学では必修科目の「哲学」や「国語論理」で、高校では「公共」で哲学思想史、必修科目「倫理」で『夜と霧』などの名著精読を取り入れ、学んでいる。これ以外にも、中1の哲学堂公園散策、中1から高2の生徒対象の「哲学エッセーコンテスト」、高校生全員が「生き方講演会」を聴講する。
希望者が参加する「哲学ゼミ(合宿)」や「刑事裁判傍聴学習会」なども用意する。
現実に向き合う中で、自分の頭で考えること、他者の声を聞くことなどを大切にする。
学校紹介本としての側面は色濃いが、効果的な思考のトレーニング法を提示したカリキュラムと、その方法論は他校にも参考になる点もあるのではないか。
(2200円 学事出版)
(吹)