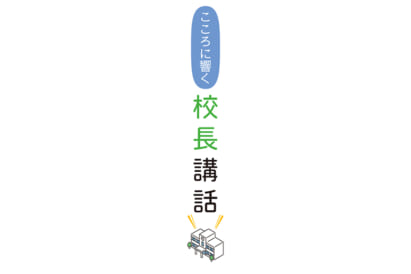子どもが自ら学ぶ力を育む「NARA GIGA X」~奈良県が描く、次世代の学びのかたち~
10面記事
GIGAスクール構想の第1期で課題になった「ICT活用の地域間・学校間の格差」を解決するため、第2期では都道府県単位での「共同調達」により、すべての学校に共通のデジタル学習基盤を整備し、教育の質と公平性を担保することが進められている。こうした中、第1期から県域でのICT環境整備を一体的に進め、GIGAスクール構想の成果が見え始めているのが、奈良県の「NARA GIGA X」だ。そこで、第1期で県教育委員会に所属し、共同調達を牽引した小崎誠二教授と、実践を進めている奈良市内中学校2校に、これまでの取り組みや成果について聞いた。
教員間の連携と意識の変化を引き出し、次のステップへ
全国に先駆けて「共同調達」を実施した理由
奈良県では、GIGAスクール構想の第1期から、県内全市町村と連携しながらICT環境の整備を一体的に進めてきた。具体的には、共通研修体系の構築、ネットワーク環境、デバイス及びクラウド環境の統一、教育データの活用基盤の整備などを通じて、教員の意識の向上と教育の質の均質化を図る「NARA GIGA X」を推進してきた。
奈良教育大学大学院の小崎誠二教授は、この取り組みの出発点として、教員のICT指導力が都道府県別ランキングで最下位だったことを挙げている。県内の教育委員会を対象にアンケート調査を実施した結果、ICT環境の整備状況も全国平均を大きく下回っていることが明らかとなったため、まずは環境整備から着手する方針を立てた。
デバイスの調達にあたっては、2019年12月に文部科学省が示した標準仕様書において、「都道府県単位等複数自治体での共同調達を検討することが望ましい」とされたことを受け、奈良県では県域での共同調達に向けた準備が本格化した。
具体策としては、奈良県域GIGAスクール構想推進協議会を設立し、デバイス本体に加えて、保守業務、ヘルプデスク、通信役務なども含めた包括的な調達を実施。これにより、大きな自治体も小さな自治体もスケールメリットを活かしたコスト削減が可能となり、各市町村の調達・契約事務の負担が軽減。結果として、自治体はデバイスの活用に向けた体制整備に集中できるようになった。
また、各市町村との調整に関しても、既存のICT基盤が少なかったことが有利に働いた。小崎氏は「更地に新築を建てるようなもの。既存環境がないことが強みになって合意が進み、その結果、2020年7月には調達が完了した」と振り返る。
統一でシステムを採用した利点
そのほか、県域で統一したシステムを採用した効果を3つ挙げた。1つは、県内全域で安定した通信環境が確保できたことである。現在でも、隣の教室でインターネットを使用すると通信が不安定になる事例も散見されるが、奈良県では地域による通信格差がほとんどなく、教員は接続を意識することなくICTを活用できている。2つ目は、共通でシステムを利用するため、自治体の枠を越えた教員同士の情報交換や相談が可能になったことである。教育実践の交流が促進され、教育委員会への問い合わせも少なくなる。3つ目は、県全体で統一されたセキュリティポリシーが適用されていること。データの安全性が高く保たれ、教員はセキュリティ面に過度な不安を抱くことなく、教育活動で思い切りよく使える環境が整っている。
さらに、県域契約のメリットは、教員研修の充実だ。奈良県では、39の自治体を対象に、2年間で延べ約400回に及ぶ教員研修が実施された。これは、年間数回の研修が一般的な他県と比較して、非常に手厚い支援体制であったことを示している。
「県域公用アカウント」で円滑なデータ連携を
こうした中、教員のICT利活用の促進に向けては、教員に共通のID(県域公用アカウント、奈良県では「いいネットなら」という呼称)を付与し、異動時の業務継続や情報共有の効率化を図っているのが大きな特徴だ。小崎氏は「当時は、教員が仕事用のメールアドレスを持っておらず、情報伝達の基盤が必要だった。そこで、安全かつ便利に教職員間で情報を共有するための、公用アカウントの導入が大前提だった」と説明する。
このアカウントは、児童生徒にも小学校から高校まで継承可能な形で付与されており、クラウド環境を活用して学習履歴を参照しながら、「主体的に自分で学べる」力を育む環境が整えられている。
学校現場の受け止めと導入後の変化
奈良県が県域でICT環境整備を一体的に進めたことについて、学校現場ではどのように受け止められているのか。若草中学校の小山篤史校長は、コロナ禍を契機に1人1台端末が一斉に導入された当初、多くの教員が戸惑いを感じていたと振り返る。しかし、「教員が研修や教え合いを通じて、校内に少しずつ活用の輪が広がっていった」と語る。
登美ヶ丘北中学校の加々見教諭も、紙媒体で行っていた業務がデジタル化されていくことで校務の効率化が進み、現場でも肯定的に受け止められるようになったとし、「例えば、デジタル学習基盤を活用することで、従来は紙で集めていた課題やノートの提出・回収がクラウド上で完結するようになったことは画期的だと感じた」と具体的な変化を挙げている。
こうした変化は、教員間の連携や意識にも表れている。登美ヶ丘北中学校の吉川校長は、「教員がそれぞれに工夫を凝らすようになった」と語り、加々見教諭も「教科や校種の垣根を越えた教員間の交流が活発になった」と実感を示す。
また、小崎氏は「管理職の世代交代も進み、現場のICT活用に対して『何かあったらどうするのか』という懸念よりも、前向きに取り組もうとする姿勢は着実に広がっている」と述べ、ICT導入が学校文化そのものに変化をもたらしていると感じている。
互いに成長するためのオープンな学習活動
児童生徒によるICTの活用は、学びの質と主体性を高める取り組みとして着実に広がっている。加々見教諭は、「生徒は目標設定や振り返りをスプレッドシートに記録し、クラスメイトと共有している。これにより、他者の考え方や表現を参考にしながら、互いに刺激を受けて学びを深める姿が見られるようになった」と語る。
さらに、単元ごとの課題、提出物、参考資料(YouTube動画など)を一つのパッケージにまとめて提供することで、生徒は学習内容の全体像を把握しやすくなっている。「単元の構造と自分の進捗を可視化することで、計画的に学習を進める力が育まれている」と手応えを示す。
こうした環境の中で、小学校からICTに親しんできた中学生のスキルは大きく向上している。クラウド上で自分の学習状況が可視化されることにより、生徒の「分かりたい」という意欲を引き出すきっかけとなっている。小山校長は、「このような協働的な学びの積み重ねが、教員主導から子ども主導の学習への転換を着実に後押ししている」と話し、ICTを自然に活用できるオープンな学習環境が、生徒同士の相互成長を促す有効な手段となっていることがうかがえる。
第2期に向けたアクション~教員へのスマートフォン配布や生成AI活用も視野に~
奈良県では、すでにGIGAスクールデバイスの更新がはじまっている。また同時に、次世代型の校務支援システム「デジタル校務基盤」の導入もはじまった。現在は、県内統一仕様の策定や、生成AIを活用した文書作成支援の実証が行われているところだ。
「目指すのは、情報の一元管理と、どのデバイスからでも安全に業務データへアクセスできる環境の整備。校務の効率化を図り、AIによって成績処理や通知文書の自動生成、保護者対応履歴を整理することなど、教員の事務的負担感を軽減したい」と小崎氏。
また、生成AIの活用は、すでに学校現場でも広がりつつある。子ども全体の課題傾向や個々のつまずきの分析、大量のアンケート結果の要約、指導案作成の参考など、教育活動のさまざまな場面で利用されている。奈良県では、生徒自身がGoogleのGeminiなど無料の生成AIツールを使う試みも始まっている。
「今後、AIはさらに進化する。教員には、生徒がAIを自然に使いこなし、自らの学びに活かせるような授業設計が求められる」と吉川校長。小山校長も、「高度な生成AIを制限なく使える環境が必要になる」とした上で、「重要なのは、教育の根幹である“どのような子どもを育てたいか”という目標を共有し、その達成のためにテクノロジーを手段として活用する姿勢である」と強調した。
小崎氏は、こうした変化に対応するため、教育委員会には次のような役割が求められると指摘する。「データサイエンスや生成AIの活用など、教員に求められるスキルは明らかに高度化している。だからこそ、教員が自分にあった環境で学び続けるための時間と機会をしっかりと確保し、継続的な教員の学習環境を整備することが重要。また、これからは、教員のAIをうまく使いこなすことなど、専門性が益々重要になることを認識した上で、タスク・オーディットを断行し、非中核的業務の外部化・廃止を大胆に進めながら、それぞれの思いを汲みとった優しい支援をしてほしい」と述べた。

奈良市立若草中学校校長 小山 篤史氏(左)、奈良教育大学大学院教育学研究科教授・奈良市教育CIO補佐官兼スクールDXプロジェクトマネージャー 小崎 誠二氏(右)

奈良市立登美ヶ丘北中学校教諭 加々見 良氏(左)、奈良市立登美ヶ丘北中学校校長 吉川 守氏(右)