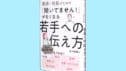特別支援教育の技法 特別支援教育コーディネーターのための「合理的配慮」の技法
14面記事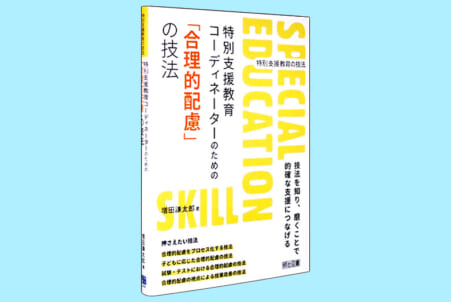
増田 謙太郎 著
学級づくりにつながる視点
「特別支援教育の技法」シリーズの一冊。令和6年に「障害者差別解消法」が改正され、合理的配慮の提供が「努力義務」から「義務」となったことに焦点を当て、学校での合理的配慮に対する考え方のズレや誤解をひも解き、通常の学級に在籍している発達障害の子どもの事例を主にしながら、学校や教職員がどう対応していけばいいかを解説した。
「合理的配慮と特別支援教育は別物である」というのが「一番伝えたいメッセージ」。九九を覚えられないまま小学3年生になった知的障害のある子どもへの対応を例にとりながら、「九九表」を掲示して算数の授業に参加しやすいように「変更・調整」するのが「合理的配慮」。だが、これは学力の向上を完全に保障するものではなく、子どもの「聴覚優位」や「視覚優位」など、特性に応じた教材を活用して力を高めるための指導が「特別支援教育」であると位置付け、「特別な配慮が必要な子どもへの支援を学校が考えるときには、合理的配慮と特別支援教育が両輪だと考えるとよい」と提案する。
合理的配慮が求められる背景に、社会にある事物、制度、慣行が障害者にとっての「社会的障壁」であれば、それを除去していくという「障害の社会モデル」の考え方があることなども平易に述べられている。
教室内などでの合理的配慮を他の子どもに「ズルい」と思わせないような学級、学校づくりにも言及しており、全ての教職員に理解が深まるといいのではないか。
(2156円 明治図書出版)
(矢)