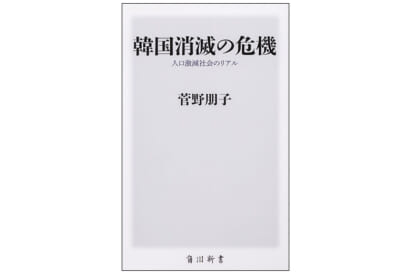教員の勤務時間は「おかしい」? 法律・実態・改革の現状と解説
トレンド
日本の公立学校教員の勤務時間は「おかしい」と指摘される状況が続いています。文部科学省による勤務実態調査やアンケートでも、長時間労働が常態化している実態は明らかです。
こうした状況を改善するために、学校現場だけでなく、地域や教育委員会が一体となって取り組む「働き方改革」が求められています。本記事では、学校現場の実態や改善に向けた取り組みと今後の展望を解説します。
教員の勤務時間と仕事内容
2024年のOECD国際教員指導環境調査(TALIS)によると、日本の教員は国際的に見ても長時間労働であることが示されています。
例えば、日本の中学校教員の仕事時間は27ヶ国・地域の平均に比べて約14時間も長く働いていることが分かっています。
出典:国立教育政策研究所『我が国の教員の現状と課題-TALIS 2024結果より-』
法律で定められている勤務時間
公立学校の教育公務員の勤務時間は、「教育職員給与特別措置法(給特法)」および「労働基準法」をもとに各都道府県および政令市の条例等で「1日7時間45分(週38時間45分)」と定められています。
文部科学省は令和2年1月、公立学校の教育職員の業務量を適切に管理するための「指針」を示し、時間外労働の上限を月45時間以内・年360時間以内と定めました。
また、業務の持ち帰りは原則行わないことを明記し、教員の長時間労働の是正を求めています。
現在、国・自治体・学校現場が連携して「学校における働き方改革」を推進し、勤務時間の適正化と教員の健康確保に向けた取り組みが進められています。
出典:文部科学省『教育公務員の勤務時間について』『公立学校の教育公務員の勤務時間等について』『公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針』
教員の仕事内容
教員は、授業だけでなく学校運営や地域との連携など日々の教育活動を支えるためにさまざまな役割を担っています。
▽主な仕事内容
・児童・生徒の指導にかかわる業務:授業、授業準備、成績処理、生徒指導、部活動など
・学校の運営にかかわる業務:部下職員・初任者への指導、校内巡回、環境設備など
・外部対応:保護者・PTA対応、地域対応、行政・関係団体対応など
これらに加えて、修学旅行、遠足、体育祭、文化祭といった行事やその準備も教員の重要な業務の一つとなっています。
出典:文部科学省『教員勤務実態調査(令和4年度)の集計(確定値)について』
日本の教員が長時間労働になる理由
教員の長時間労働は、成績処理や報告書作成といった事務作業、児童・生徒一人ひとりへの指導のほか、校外活動への対応が多いことが要因と考えられます。
特に中学校では部活動指導の負担が大きく、休日に練習や大会に参加することが一般的です。教員不足によって専門外の教員が顧問を担当する例も増えており、現場の身体的・心理的負担は一層深刻化しています。
こうした多重業務の積み重ねが、教員の勤務時間が「おかしい」と指摘される現状を生み出しています。
出典:文部科学省『教員勤務実態調査(令和4年度)の集計(確定値)について』
教員勤務実態調査から分かる現状
教育現場では、長時間労働が深刻な課題となっています。ここでは、文部科学省の令和4年度教員勤務実態調査の結果をもとに、教員の勤務実態と現場の声を紹介します。
教員の勤務実態
令和4年度の調査によると、前回(平成28年度)と比べて平日・土日ともに全職種で在校等時間(※)は減少したものの、依然として長時間勤務が常態化しています。
▽教諭の平日平均在校等時間
・小学校:10時間45分
・中学校:11時間1分
・高等学校:10時間6分
※在校等時間:在校時間を基準とし、休憩や業務外の作業を除いた実働時間
学校での業務に加え、持ち帰り業務や休日出勤も見られ、1週間あたりの在校等時間が週50~60時間という教員も多く、法定の週38時間45分との差は依然として大きい状況です。
出典:文部科学省『教員勤務実態調査(令和4年度)の集計(確定値)について』
教員の本音・現場の声
調査では、多くの教員が「プライベートの時間を充実させたい」「授業準備や教材研究に時間を使いたい」と回答しています。
また、働き方に関する満足度調査では「雇用の安定性」「仕事のやりがい」「福利厚生」などに満足している教員の割合が高い一方で、「仕事と生活のバランス」については満足していない教員の割合が高く、心身の疲労や家庭生活への影響を訴える声も少なくありません。
教育現場では「教育の質を保ちながら労働時間を減らすにはどうすべきか」という課題意識が強く、現場の教職員・管理職・保護者が一体となった改善が求められています。
出典:文部科学省『教員勤務実態調査(令和4年度)の集計(確定値)について』
改善に向けた動き・施策
国・自治体・学校現場では、教員の長時間労働を是正するための改革が進められ、多角的な取り組みが展開されています。
▽働き方改革の主な取り組み内容
・学校閉庁日の導入
・ノー残業デーの徹底
・部活動の地域移行
・ICT活用による業務効率化
文部科学省は各教育委員会に対し、業務改善方針の策定や在校時間の公表を推進し、校長・教頭といった管理職による勤務時間の把握と管理を徹底するよう求めています。
今後は、学校ごとの実情に応じた役割分担の明確化や外部人材の活用による業務削減をさらに進め、教員の健康維持と教育の質の向上を両立できる、持続可能な学校運営体制の構築が期待されています。
出典:文部科学省『教員勤務実態調査(令和4年度)の集計(確定値)について』『令和6年度 教育委員会における学校の働き方改革のための取組状況調査【結果概要】』
教員の働き方改革は「教育の質」を守るため
教員の勤務時間の問題は、単なる「長時間労働」という労働環境の課題にとどまらず、教育の質や子どもたちの学びの環境にも直結する社会的課題です。教員が安心して働ける環境を整え、教育の質を維持・向上させることが何よりも重要です。
現場の声に耳を傾け、子どもたちと真摯に向き合う時間を確保できる持続可能な教育現場の実現に期待が高まります。