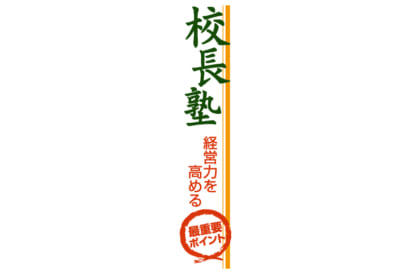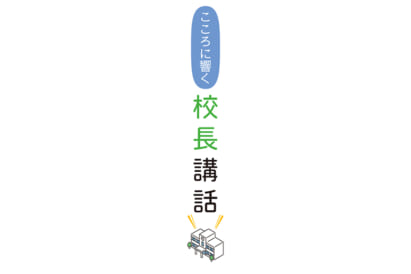課題解決型の体験活動でデザイン思考を育む
10面記事
聖学院中学・高等学校
自ら考え、判断し、他者と協働しながら問題解決を導く実践力を身に付ける―。私立聖学院中高(東京)は、そうした21世紀型能力の育成を、授業だけでなく教育旅行においても定着させようとしている。プロジェクト型の体験活動を経験した生徒たちは、進んで個人探究のテーマを見いだし、自ら創造する学習の楽しさを発見しているという。
2012年から探究型に
東京・駒込にある私立聖学院中学・高等学校(角田秀明校長、生徒数900人)は、「Only One for Others(他者のために生きる人)」を教育理念とする男子校だ。2012年から教育活動に「Project Based Learning(PBL)」の手法を導入。プロジェクト活動を通して、能動的、協働的な学習者を育てる改革に挑戦中だ。
現在は、中学の数学、国語、理科、高校の日本史や現代社会、情報など、多くの授業をPBL化しているが、最初は学校行事や校外学習、宿泊行事をPBLとして再構成することから始まった。
登山をプロジェクト化
中学2年時の「夏期学校」は、北アルプスで登山とテント生活を体験する3泊4日の宿泊行事だ。標高約2600メートルの蝶ヶ岳登頂を成功させるには、どのような計画や準備が必要か、生徒自身が調べて実行する、という形にした。山道の歩き方や服装、持ち物などを調べる「登山プロジェクト」、登山中の栄養補給や野外調理の方法を教える「食事プロジェクト」、テントの設営方法や宿泊方法を伝える「生活プロジェクト」など、生徒は必ずどこかのプロジェクトに所属する。出発前には学年集会を開き、各プロジェクトマネージャーが全員の前で調べたことを発表し共有する。これは事前説明会も兼ねた行事だ。
登山時の「パーティ」は、各プロジェクトから1人ずつで構成されるため、それぞれの責任は重い。役割を担い、仲間と協力しながら登頂を果たしたときの達成感はひとしおだという。
社会課題に目を向けるチャンスを作る
高校1年時の5月下旬に、神奈川県湯河原町を拠点に実施する2泊3日の「ソーシャルデザインキャンプ」も、大胆に改革をした。以前は親睦を深める意味合いが強かったという。
同行事をPBL型にシフトする上で、教員間で話し合ったのは、
・自己肯定感を育む
・他者と協働する精神を持つ
・社会の興味関心を持ち、課題を自分ごと化する
・情報を入手し、考え、アウトプットするスキルの向上
・グローバルな視点への展開
―という同校が描く生徒の成長ストーリーに貢献する行事に転換することだった。
「中学3年で農村体験学習をするのですが、そこで開かれた社会への興味関心を、さらに社会課題の発見と解決に向かうよう連続性のある内容にしたかった」と話すのは、同校の21教育企画部部長の児浦良裕教諭だ。
生徒は湯河原町周辺エリアで、伝統工芸、観光、地域活性、漁業、農業などの部門に分かれてフィールドワークをする。朝3時に漁港に向かい、競りを見学する班もある。
そこで働く人たちへのインタビューを通して課題を見つけ、情報を整理して、解決の方策を練り上げていく。最終日にはプレゼンテーション大会を開催し、最優秀チームを決定する。
各産業が抱える課題と、ありたい姿をつなぐ「解」を見いだす作業は、理想論ではすまされない。宿舎では生徒たちが夜まで真剣な議論を交わす姿が見られるという。
校内プロジェクトが派生
探究型のソーシャルデザインキャンプに変えてから、同校では「持続可能な社会の構築」に関心を持つ生徒が増えている。
もともと部活動や生徒会活動のほかに放課後の有志の活動が盛んだが、そこに「社会課題の解決」の視点が持ち込まれ、活動に奥行きが出てきたのだ。
パラスポーツのプロジェクトでは、地域の高齢者施設に生徒が出向き、ボッチャを紹介して健康増進に役立ててもらう企画が実現した。環境改善のプロジェクトに所属していた生徒は、工業系の大学が主催する地域プロジェクトに個人参加し、まちづくりを学ぶなど、卒業後の進路を見据えて動く生徒も出始めた。
学校にも探究学習のパートナーが必要
教育旅行の改革にあたり、児浦教諭は同様の取り組みをする全国の公立高校の先進事例を見学している。
リアルな社会課題を扱う場合、「教育的見地から現場を調整してくれるコーディネーターと、生徒の活動を支援するサポーターが欠かせない」という。
同校の場合、地域の事業者をコーディネートするリディラバと連携できたのが成功への突破口になった。学校という組織にも探究学習を協働できるパートナーがいれば心強い。
今後の課題は、生徒発の自発的なプロジェクトを「総合的な探究の時間」における、個人の探究活動へと引き上げることだ。教育課程に位置付ければ、十分な時間が確保でき、より多面的な評価も可能になる。
その際も、学校や学年内部の企画にとどまらず、複数の学校が連携するなどして「生徒が出会う世界をどれだけ広げられるかがカギになる」と、児浦教諭は話している。