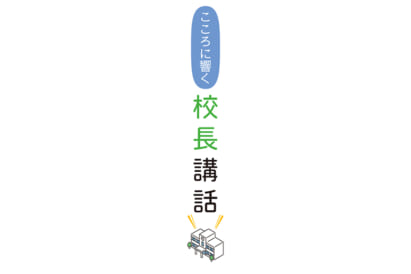「実態と乖離した実践」 見直しへ
4面記事千代田区立麹町中―この1年 (上)
昨年3月から6月にかけて本紙に掲載した千代田区立麹町中学校(堀越勉校長)の現状を伝える記事に対し、さまざまな反響があった。堀越校長はその後も関係者へのヒアリングを続け、過去の諸課題と現在の学校経営の姿を講演や視察の場で発信し続けている(1月20日付で一部既報)。今回から3回にわたり、前校長の長田和義・武蔵野大学教授の取り組みを含めた諸活動とこの1年の動き、同校卒業生で学校運営協議会座長の中村一哉・実践女子大学教職アドバイザーへのインタビューを掲載する。
長田前校長
授業は「参加が基本」 生徒の問題行動を指導
同校の元校長が、著書で紹介した取り組みには、宿題や定期テストの廃止、全員担任制の導入などがある。全国から注目を集め、各地で著書を参考に学校づくりをする動きがある。
堀越校長は昨年度に赴任し、教職員に実情を尋ねたところ、宿題は実施されており、「課題」と呼んでいただけだと分かった。本紙から、長田前校長に確認したところ「全ての宿題を廃止するものではなかった」と証言した。
堀越校長は、他にも対外的な発信と実態に乖離があるものを見つけると、一つ一つ点検し、課題があれば改善策を打ち出した。学校づくりのキーワードを「整える」と掲げ、実際の姿と日々の取り組みを学校便りで広く伝えるようにした。
令和2年度に赴任した長田前校長も、元校長の時代の取り組みについて、成果と課題を検証しながら、見直しを図ってきた。
コロナ禍の休業期間が明け、学校を再開すると、生徒の髪形や服装は「バラエティーに富んでいた」という。前年度まで標準服だったが、元校長から年度末に「私服可」と伝えられ、一気に私服に変わっていった。生徒と教員の距離感は近く、友達のような雰囲気を感じた。「生徒の中には何をしても叱られることはないと解釈し、言葉遣いも友達感覚のように感じるものもあった」という。
長田前校長が任期の3年間で力を注いだことは、こうした空気を徐々に改めつつ、
(1)授業は「参加を基本」にする
(2)生徒が問題行動を起こしていたら機を逃さず指導する
(3)出前講座などが一部の生徒向けのものになっていないか効果を見極め整理する
―などだ。
(1)については、授業に参加できない生徒がいればクールダウンさせた後、授業に出るように指導した。また、職員室からも近く教員の目の届くところに生徒が過ごせる場所を設けた。(2)は「指導をすると生徒の自律が奪われる」と捉え、教員が生徒への指導をためらう姿を目にしたためだ。(3)については、特色とされた各種活動の中には、教育課程上の位置付けやねらいが不明瞭なものがあったと振り返る。
長田前校長に、学校経営は大変だったのではないかと尋ねたところ、「コロナ禍の中での学校経営でもあり、大変でした」と返ってきた。元校長については、「公立中学校であっても、校長が判断し実践できることは多数あり、大きな裁量があることを全国に示した」点を評価している。
堀越校長
学力低下、不登校増の情報発信 ボトムアップ型組織に転換
堀越校長も実態把握に努め、生徒の学力が大幅に低下する傾向にある、不登校の割合が他校と比べて多い―などの課題が分かり、学校運営協議会や保護者に対してデータとともに情報を伝えた。
昨年度1年間の改善に向けた取り組みは、学校便りや本紙連載「校長塾」で発信している。
(1)単元テストの在り方を見直し、全教科のテスト範囲を示し、勉強して臨めるようにする
(2)全員担任制の運用を見直し、相談を我慢していた生徒を減らし、担任の責任の所在も明確にする
(3)トップダウン型の組織構造をボトムアップ型に変える
―などだ。
(1)の単元テストは、最大で25分であったため50分の試験に耐えられない生徒がいた。過去には、再テストを複数回受けられるため問題と解答がSNSで出回ることがあった。
学習指導要領の運用にも課題を感じたため、45分授業を50分に戻すとともに標準授業時数を確保した。
改善策を講じる中で、過去の同校の課題がさらに明らかになっていった。校内の複数の施設・設備の破壊や授業中にゲームをしたり土足で授業を受けたりしている場面、儀式的行事や学年集会の場などで列に並ばず車座になってしゃべっている姿などの写真が出てきた。