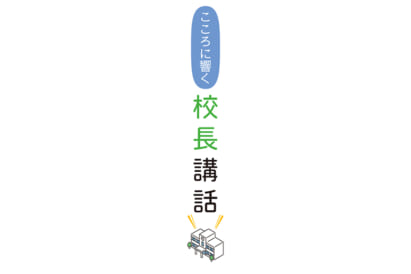元校長の理念や手段「目的化」 理想論でなく目の前の子の「具体」が大事
4面記事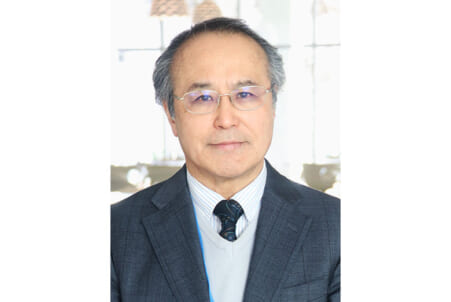
千代田区立麹町中―この1年 (下)
中村 一哉・学校運営協議会座長に聞く
千代田区立麹町中学校の現在の姿を描く記事のまとめとして、同校卒業生で長田和義・前校長の時代を含めて4年にわたって学校運営協議会座長を務める中村一哉・実践女子大学教職アドバイザー(元東京都中学校長会会長)に、協議会での活動を通して感じたことを語ってもらった。
まず卒業生の一人として麹町中の発展を心から願っている。学校評価アンケートを見ると、保護者や地域住民、生徒の満足度は高く、学校全体が落ち着き、生徒が学びに向かえる体制が整ってきていることがうかがえ、うれしく思う。
協議会の座長として心掛けてきたのは、公平中立な立場で委員の話に耳を傾け、学校運営に反映させること。
座長就任当初、「最先端の教育を行う元校長による麹町中のブランドを変える必要はない」という、一部ではあるが、以前の学校への思いが強い委員の発言が影響力を持ち、協議会で課題改善の取り組みが協議されることは少なかったように思う。当時は理念を優先する傾向が強く感じられた。おそらく過去には必然性があった理念だと思うが、時の変化とともにいつしか理念や手段が目的化し、現実の課題との不一致が生じていたのではないか。
学校は1年ごとに生徒も教員も変わる。その変化に対応するのは学校の責務。協議で多様な意見が出るのは当たり前で、それを発言するのも自由だが、最終的に生徒への責任が取れるのは現在の学校であり、現職の校長しかいない。常にそのことを意識して協議を進め、協議会の席で元校長の名前が出たときには、その必要がないことをはっきりと伝えた。中には教育課程の承認の挙手を最後までしなかった委員もいたが、委員の多くは地域に住む卒業生。麹町中の実情はよく理解している。現在の学校の落ち着きは、そうした地域の支えに負うところが大きいと感じる。
その中で長田前校長も現在の堀越勉校長も、それぞれの課題に真摯に向き合い、強い信念で頑張ってきた姿を私は見てきた。
確かに、マスコミ等による麹町中の評判は聞いてはいたが、実際に私が見たICTを活用した授業では、タブレットでゲームをしたり、眠っていたり、廊下に出ているなど、学びに向かえていない生徒が目に付いた。以前ならば別室にいた生徒なのかもしれない。「授業に参加しないのも、生徒の主体的な選択肢」とのことのようだった。そうした生徒に教員が働き掛けをしない理由もまた「主体性を損なわないため」。私自身の経験を振り返っても、教師は生徒との関わりの中で成長するもの。関わらなければその機会は奪われる。協議会で研究校としての教員研究を提案した背景も、そこにあった。
麹町中は東京の中心地にあり、社会的にも経済的に恵まれた家庭が多い。しかし、思春期の中学生の課題はどこも同じ。生徒の成長や発達には差があり、デリケートな問題を抱えている生徒も一定数いる。だからこそ、全ての生徒に細やかな目を向け、一人一人を丸ごと受け止め見守っていくことが、中学生の自立の支援には必要。「一般論」や「理想論」のみでは学校は硬直する。目の前の全ての生徒の「具体」と関わってこそ、学校は子どもが育つ場となる。
事実踏まえぬマスコミ SNSでの批判は残念
この4年間で最も心を痛めたのは、マスコミやSNS等による麹町中に対する無責任な意見や誤解。どこが発信源かは分からないが、現実の学校の姿と乖離した誹謗とも思われる批判的な意見が流布し、そのイメージがあたかも真実であるかのように広がったことは本当に残念だった。最も傷ついたのは在校している生徒のはず。しかも、元校長を引き合いに出して現在の学校を批判することなど、本来あり得ないことで、元校長に対しても失礼なことだろう。
公務員には守秘義務があり、内部で起きた課題を包み隠さず語ることは難しい。しかし、地域の住民や協議会のメンバーは、各時代の校内の様子も発生した問題もあらかた理解し、その上で歴代の校長を支えてきたし、現在の堀越校長も信頼し、心から支援しようとしている。そうした大きな力に支えられた麹町中が、今後も伝統校としての誇りを持ち発展していくことを、卒業生として、また協議会の一員として見守っていきたい。