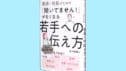子どもを「分けない」学校 「ともに学び、ともに生きる」豊中のインクルーシブ教育
16面記事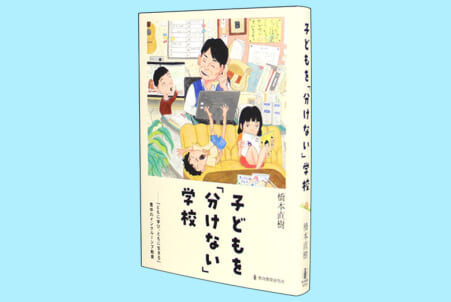
橋本 直樹 著
「特別」でない「当たり前」の支援
キーワードは「当たり前」だろうか。
50年も前から、どんな状況の子どもも入学を望めば絶対に拒否しないことを「当たり前」とする大阪府豊中市の学校の日常を描く。
同市では支援教育、支援学校、支援学級に「特別」を付けない。どの子に対しても必要なことをするのは「特別」なことではないからだ。評者も「特別」には違和感がある。
支援学級に在籍する子どもたちも通常の学級で過ごす。支援学級担任は通常の教室に入り込み、支援学級在籍の子どもを意識しながらも、全ての子どもに必要な支援を行う。
豊中が目指すのは、子どもにどんな障害があっても保護者に特別な負担を掛けないことであり、その子が安心して過ごせる環境整備を行政・学校の責任で行うこととしている。行政の覚悟が学校をしっかりと支えている。
「すべての教職員がすべての子どもの担当」という学校の方針を大事にし、「100人が楽しい、これでいいと言っても、一人が苦しんでいれば、その一人に焦点を当てて進める」ことを教育の原点と考える。
これらが豊中では「当たり前」の対応だ。評者は率直に言って強い憧れを感じる。だが、おそらく多くの自治体や国の「当たり前」は違うだろう。何が本当の「当たり前」か。どういう学校、教育が幸せな社会への道なのか。本書は「当たり前」を問い直す鏡である。
(2530円 教育開発研究所)
(浅田 和伸・長崎県立大学学長)