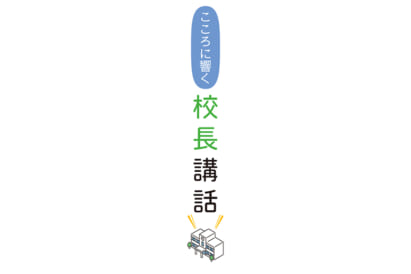スポーツ指導者の熱中症予防に関する実態
10面記事高校生の運動部活動中が6割超
学校関連の熱中症死亡事故は、高校生の運動部活動中が6割を超えて最も多い。昨年、夏の甲子園大会が開幕から3日間、暑さが厳しくなる昼間を避けて午前と夕方に分けて試合を行う2部制を導入したことが話題になったが、野球はもとより、ラグビー、サッカー、柔道、剣道などの激しい運動を伴うスポーツでの発生が目立っている。
これらの活動では、長時間の練習や高温多湿の環境下での運動が原因となり、体温調節が追いつかずに熱中症が進行する。また、ランニングや持久走などの反復的な運動もリスクが高まる。
したがって、指導者は環境条件に応じて運動強度を調節し、適宜休憩をとり、適切な水分補給をとらせることが重要になる。併せて、常に健康観察を行い、体調不良の生徒には適切な措置をとる。個々の運動技能や体力の実態、疲労の状態などを把握する。生徒が心身に不調を感じたら、申し出て休むよう習慣付けることが必要だ。
効果的な身体冷却の導入が課題
こうした指導の実態について、昨年、日本スポーツ協会公認スポーツ指導者を対象に調査した結果によれば、熱中症対策として「水分補給」はほとんどの指導者が実践していたが、「活動時間の変更(45.2%)」「身体冷却(44.9%)」「暑熱順化(22%)」は低かった。また、外部冷却の方法については「頭部・頸部(けいぶ)冷却」が最多であった一方で、全身を氷水につけることで効果的に冷却することができる「アイスバス(11.6%)」は少数だった。このことは内部冷却に効果的な「アイススラリー(13.8%)」にもいえる。
健康チェックについては「毎日行っている」が54.9%といまだに少ない。かつ、その方法も「選手本人にチェックリストへ記入させる(18.5%)」や「体重測定(7.7%)」と少数であったことから、今後も啓発が必要としている。
WBGTに基づく対応では、多くの指導者が「スポーツ活動を中止(24.8%)」あるいは「活動内容を調整している(61.7%)」が、「活動内容の変更は行わない(16.8%)」という回答もまだ多くあり、熱中症予防運動指針やWBGT計の活用をより進めていかなければならない。