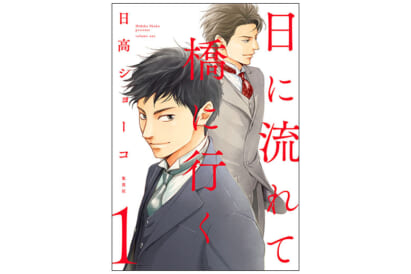一刀両断 実践者の視点から【第676回】
NEWS
大学生にアンガーマネジメントを
大阪で、児童7人が自動車ではねられる事件が起きた。この事件を報じた記事から、私たち教員は何を学ぶことができるだろうか。
被害に遭った児童に、もちろん何の落ち度もない。そこに車で突っ込んだ加害者は、医療従事者であり、大学も卒業している人物だった。
「何もかも嫌になった」と話したらしいが、それが人を傷つける行動に結びつく理由にはならない。
被害者の家族の悲しみや怒りは言うまでもなく深いが、加害者の家族もまた、責められ、そして計り知れない落胆や自責の念を抱えているはずだ。
私は学生に「自分が被害者の家族だったらどうしたいか」と問うことがある。多くの学生は「加害者を厳罰にしてほしい」と答える。だが、「加害者の家族だったら」と問いかけると、皆迷いを見せる。
今回の事件は、まったくの想定外だったのだろうか。そうではないとすれば、加害者がそこに至る前に、周囲が何らかの形で関わり、行動を制御することはできなかったのかと悔やまれる。
大学の学びの中に、アンガーマネジメントや自己制御、孤立を防ぐ実践的な学びを必須とする必要があるのではないか。加害者になってからでは遅いし、被害者が出てからでは、私たち教員も自らの無力さを認めざるを得なくなるからだ。
(おおくぼ・としき 千葉県内で公立小学校教諭、教頭、校長を経て定年退職。再任用で新任校長育成担当。千葉県教委任用室長、主席指導主事、大学教授、かしみんFM人生相談「幸せの玉手箱」パーソナリティなどを歴任。教育講演は年100回ほど。日本ギフテッド&タレンテッド教育協会理事。)