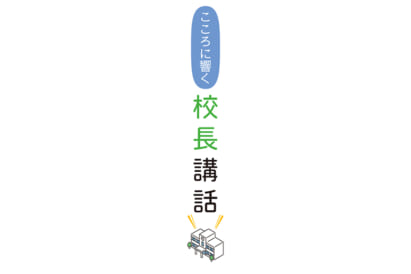一刀両断 実践者の視点から【第678回】
NEWS
「熱血」の指導と自死
6年前に自ら命を絶った少年が、教員から理不尽な扱いを受けていたという記事を読んだ。その教員は、課外活動の指導に熱心だったとされている。
ある出来事を思い出した。以前、私が別の学校へ異動したとき、後任となった若手の教師が、ミニバスケットボール部を市内47校の中で連続優勝に導いた。年々その勢いは増し、部の知名度も高まっていった。
だが、指導方法には問題があり、強圧的だという噂が聞こえるようになった。成果を上げると管理職が管理を緩める傾向があり、指導の勢いは止まらなかった。数年後、退職し、実業団に行ったと聞いた。
それでよかったのだろうか。今でも疑問を感じている。教師としてあるべき姿を身に付けさせることができなかった体制の問題だと思っている。
今回の問題で、なぜ同僚教員の責任は問われないのか。学校という組織の中で、コンプライアンスが機能していないと、負の連鎖が生まれる。今回の件はその典型例だろう。
「熱血」といった聞こえのよい言葉ではなく、「犯罪」とはっきり位置付けるべきではないか。
加害に加担した同僚や指導者たちも、その行為を認識していたとのことであり、責任は重い。亡くなった少年の友人は「担任のせいだと思う」と語ったという。こうしたことが起きないよう、教員を養成する段階から根本的な見直しが必要だと強く思う。
(おおくぼ・としき 千葉県内で公立小学校教諭、教頭、校長を経て定年退職。再任用で新任校長育成担当。千葉県教委任用室長、主席指導主事、大学教授、かしみんFM人生相談「幸せの玉手箱」パーソナリティなどを歴任。教育講演は年100回ほど。日本ギフテッド&タレンテッド教育協会理事。)