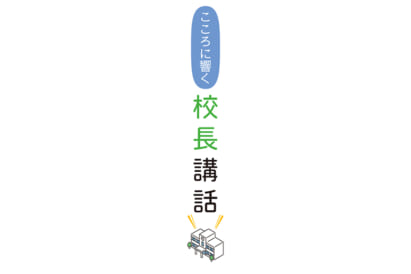生成AIで教育はどう変わる 英文添削、早く正確に 評価基準も提案
10面記事
お互いに聞き取った話を英作文にして提出。AIが添削する=6月18日、九段中等教育学校
近年、急速なスピードで進化を続ける生成AI。教育現場の利用について、文科省は校務や学習場面での積極的な導入を促していく考えだ。学校の生成AI利用の最前線を追った。
「友達の感じている不満を聞いて、その解決策を書いてみて」
東京都千代田区立九段中等教育学校であった5年生の英語コミュニケーションの授業。矢野絢奈教諭が英語で指示すると、生徒たちが隣同士で話し合いを始めた。
ある生徒は「私の友人は傘が何度も盗まれたことに不満を持っている。問題を解決するには折り畳み傘を持った方がよいのではないか」などとライティングシートに手書きで記入し、周りの生徒と交換。英文の誤りなどの指摘をもらって修正した後、教員に提出した。
生成AIを活用するのはここからだ。矢野教諭が生徒の英作文をスキャナーで読み取ると、AIが内容・構成・表現の評価と、文法と語彙の改善案、次回に向けたコメントを瞬時にまとめる。教員は最終的な確認をするだけで返却でき、短時間で詳細な添削が可能になった。矢野教諭は「読み取り精度も非常に高く、丁寧に書かれていれば正確に読み取れる。これなしの授業はもう考えられない」と話す。
国語科では生徒の思考を可視化するのに利用した。教員があらかじめプロンプト(指示文)を設定しておき、AIと対話することで物語の「深い読み」につながるようにした。「生徒のプロンプトを見ることで、何を考えていたか分かる」と廣瀬紘太郎教諭は導入の効果を口にする。
同校でデジタル化を担当する市川淳尉主任教諭は、校内で生成AIが積極的に活用されている背景として「授業改善に使いたいという教員の意欲が高いことに加え、開発側に頻繁に要望や改善点を伝えられることが大きい」と強調する。
現在では多様な学習用AIが登場している。例えば、東進ハイスクール・東進衛星予備校などを運営するナガセは、和文英訳を即時に採点・添削できる「英作文1000本ノック」や、プログラミング演習ができる「情報Ⅰプログラミングノック」などを開発。大学入試に最適化されたAIが添削し、教員個人の努力に委ねられていた個別の添削指導をAIで全ての生徒が受けられるようにした。
志望理由書を添削
教員が授業以外で多くの時間を費やしているのが校務だ。山形県立酒田光陵高校では、生徒の志望理由書の添削で大幅な時間削減に成功した。
卒業後の進路が多様で、大学を希望する生徒もほとんどが推薦入試を受ける。提出書類の作成で進路指導担当の教員にかかる負担は大きかった。
そこで生成AIで読み取り、誤字脱字や論理構成、表現を訂正させることで、これまで40分かかっていた書類の添削はわずか10分に激減した。進路担当の湯澤一教諭は「書類を添削する時間を短くできた分、生徒と相談しながら完成させることができる」と語る。一方、生徒の初稿がAIに丸投げしたものだと、話し合いの場で本人が何も答えられないケースもある。「自分で考えた上で、AIを使うように指導することは欠かせない」
話し合い活動の評価
生成AIを使って、生徒の学習をより丁寧で客観的に評価しようとする試みも始まっている。
東京学芸大学附属竹早中学校ではAIに学習指導要領を読み込ませ、ルーブリック(評価基準表)の作成や実際の学習評価まで委ねてみた。
実践したのは社会と国語。例えば、社会の歴史的分野では「社会的事象を時期、推移などに着目して捉え、類似や差異などを明確にし、事象同士を因果関係などで関連付ける」とする社会的な「見方・考え方」を基に4段階のルーブリックを設定。さらに生徒が答えた文章をルーブリックに照らして評価させた。
社会科担当の上園悦史主幹教諭は「AIが作成したルーブリックや学習評価は教師が行う場合と比べて、ほとんど違和感がなかった。データがたまれば、妥当性のかなり高いルーブリック評価ができるようになる」と驚く。
社会科で書いた文章を国語の観点で評価するなど、教科横断的な学習評価に活用する可能性も模索しているという。
同校では話し合い活動の評価にもAIを取り入れた。グループ内の生徒の声を認識し、それぞれの生徒が話し合いの中でどのような資質・能力を発揮しているかを明らかにしようと試みた。
研究に関わる東京学芸大学教育インキュベーションセンター長の金子嘉宏教授は「これまで対話的な学びが重要だと言われながら、その過程で生徒が何を学んでいるのかを評価できなかった。AIを活用すれば見取れる可能性がある」と話す。
同校の教育AI研究プログラムにも携わる遠藤太一郎教授は「生成AIの導入によって伴走者として教師に求められる資質・能力も大きく変わってくる。そのためのルーブリックも開発していく必要がある」と指摘する。