教職員の時間外在校等時間、上限指針見直しへ初会合
1面記事中教審特別部会 時間外在校等時間の上限などを示す「上限指針」の見直しに向けて、中央教育審議会の「教師を取り巻く環境整備特別部会」は9日、初会合を開いた。改正教員給与特別措置法(給特法)で教育委員会に...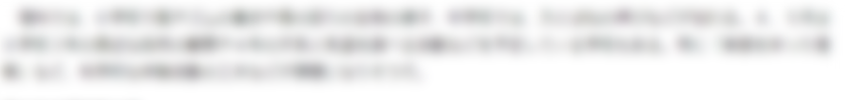
続きを読みたい方は、日本教育新聞電子版に会員登録する必要がございます。
日本最大の教育専門全国紙・日本教育新聞がお届けする教育ニュースサイトです。
先生解決ネットサイトをリニューアル致しました。
リニューアルに際しユーザーの皆様に再登録して頂く必要がございます。
お手数ではございますが、何卒宜しくお願い致します。
中教審特別部会 時間外在校等時間の上限などを示す「上限指針」の見直しに向けて、中央教育審議会の「教師を取り巻く環境整備特別部会」は9日、初会合を開いた。改正教員給与特別措置法(給特法)で教育委員会に...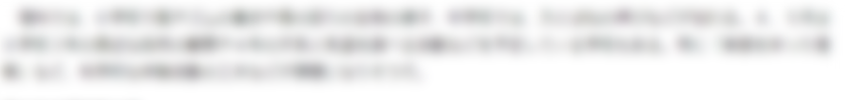
続きを読みたい方は、日本教育新聞電子版に会員登録する必要がございます。