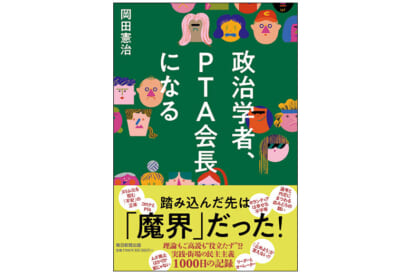科学的に探究する力を育む実験&ICT活用
10面記事
「観察・実験」とICTを組み合わせて探求心を育む
「観察・実験」の結果を明確にするためにICTを活用する
これからの社会変化の激しい、予測困難な時代を生きる子どもたちは、生涯にわたって主体的に学び続け、自らの人生をかじ取りする力を身に付ける必要がある。このため、学校教育では、自分で課題を見つけ、解決に向かう力を育む探究学習が重視されている。そこで本特集では、「科学的に探究する力を育む」をテーマに、理科授業で取り入れたい「観察・実験」×ICT活用を取り上げる。
理科の特質に応じたICT活用が必要
予測困難な時代に活躍できる将来人材を育成するため、学校では従来の「知識を覚える」学習から、答えが決まっていない課題に対して、試行錯誤しながら理解を深める探究的な学びが重視されている。理科においても、自然の事物・現象を科学的に探究する活動へと充実させることが求められている。
その上で、理科への興味関心を引き出し、科学的な見方・考え方を養うために活用していきたいのが、学校現場に整備された1人1台端末とクラウド環境にほかならない。
ただし、ICTは「観察・実験の代替」としてではなく、理科の学習の一層の充実を図るために有用な道具として活用することが大切で、そのためには理科の特質に応じたICT活用が必要といえる。
ICTの特性には、①多様で大量の情報を収集、整理・分析、まとめ表現することなどができ、カスタマイズが容易であること。②時間や空間を問わずに、音声・画像・データ等を蓄積・送受信できるという時間的・空間的制約を超えること。③距離に関わりなく相互に情報の発信・受信のやりとりができるという、双方向性を有することなどがある。
これらの特性や長所を理解した上で授業改善として取り入れていきたいのが、問題解決に向けた活動を重視する理科教育の核となる「観察・実験」と、そこで得た結果を明確にするために活用するICTを組み合わせた学習方法になる。
ICTを組み合わせた学習方法
具体的には、①実験や観察で得られたデータを学習者用端末に記録し、表計算ソフトやデータ分析ツールを使うことで、データの可視化(グラフ作成など)や統計的な分析を行う。②シミュレーションソフトやAR・VR技術を活用することによって、現実では困難な実験(危険な物質の取り扱いや長期間を要する現象など)を仮想空間で再現し、視覚的体験的な理解を深める。モデリングツールで自然現象の仕組みを分かりやすく理解する。③クラウド上に実験結果を保存することで、異なる班の結果を比較し、新たな考察を得たり、フィードバックをもらったりすることで探究を深められる。④学習の個別化・多様化に向けても、教育プラットフォームや学習アプリを利用することで、各自のペースで探究学習を進めることが可能になる。また、多様な学習リソース(動画、記事、シミュレーションツールなど)にアクセスできるため、学びを広げることができる。
学習の場を広げる、学習の質を高める

観察した結果をもとに端末を使って考察する
これらを授業の中に組み込んだ事例としては、次のようなものが挙げられる。
「オンライン気象データと実験の組み合わせ」:地域の気象データを収集できるオンラインプラットフォームを活用し、気温・湿度・風速の変化をリアルタイムで分析。さらに、自分たちで実験して気温と水の蒸発率の関係を調べる。これにより、自分たちが行った実験結果と実際の気象変化を比較しながら考察を深めることができる。
「デジタル顕微鏡と画像解析を組み合わせた細胞観察」:デジタル顕微鏡(デジタルマイクロスコープ)を使って細胞の構造を観察し、撮影した画像をデジタル解析ソフトで拡大・加工しながら詳細を調べる。微細構造を鮮明に観察できるため、通常の顕微鏡では見えづらい細胞内の変化や機能について理解できる。
「超音波センサーを使った水の流れの観察」:水流の動きを測定するために、超音波センサーを活用して実験。異なる流速の水がどのように振る舞うかをリアルタイムで可視化し、流体力学の基礎を理解する。水の流れを数値化できるため、従来の、観察に比べて科学的な考察が可能になり、川の流れや海流の研究にも応用できる。
「AIを活用した植物の成長観察」:植物の成長を長時間にわたって記録・分析するため、スマートフォンやタブレットで写真を撮影し、AI画像認識ツールを使って葉の形や色の変化を解析。目視では分かりづらい変化も検出でき、より詳細なデータをもとに成長環境の影響を考察できる。
「VRによる宇宙の観察」:宇宙の天体観測をVR技術で体験できる授業を実施し、地球上では見えない銀河やブラックホールなどをバーチャル空間で探索する。通常の星図では理解しにくい宇宙の構造や天体の位置関係を、体験的に学ぶことができる。これにより、天文学への関心が高まり、さらに深い探究へとつなげることができる。
実験用ガスコンロ×ICT活用
また、理科の加熱実験で使われることが多い「実験用ガスコンロ」とICTを組み合わせた事例には次のようなものがある。
「水の比熱実験×デジタル温度センサー」:実験用ガスコンロを使って水を加熱し、デジタル温度センサーを利用して時間ごとの温度変化を記録する実験を実施。データはタブレットやPCにリアルタイムで送信され、グラフ化されることで変化を視覚的に捉えられる。手動で温度測定する手間が省けるとともに、より正確なデータをもとに比熱の計算や考察を行うことができる。
また、「水の凝固点降下実験」では、塩を加えた水と純水を実験用ガスコンロで加熱・冷却し、デジタル温度センサーを使って凝固点の変化を測定。温度データをクラウドに記録し、異なる濃度の塩水の凝固点を比較する。各自が異なる条件で実験を行い、全員のデータをクラウドで統合して考察することで、共同研究の要素を加えた探究学習が可能になる。
「沸騰と蒸発の過程×タイムプラス動画」:実験用ガスコンロで水を加熱し、タイムプラス動画を撮影して、沸騰と蒸発の過程を記録。気圧や容器の種類などの異なる条件で撮影し、変化を比較する。短時間で変化を視覚化できるため、物理現象の学習がより直感的になり、観察力が向上する。
「金属の熱膨張実験×デジタル測定ツール」:異なる種類の金属棒を実験用ガスコンロで加熱し、レーザー距離計やデジタルノギスを用いて長さの変化を測定。温度と膨張率の関係をリアルタイムで分析する。熱による膨張を正確に測定できるため、金属の特性の違いを数値的に理解できるとともに、データをグラフ化して視覚的に比較ができる。
「油の酸化実験×化学センサー」:異なる種類の油を実験用ガスコンロで加熱し、時間ごとに酸化度を化学センサーで測定。酸化の進行をデータとして記録し、研究への影響を考察する。肉眼ではわかりにくい油の劣化をデータで可視化し、食品化学の観点から安全性について議論することができる。
このように、観察・実験とICTを上手く組み合わせることで、学習の質が向上し、子どもたちの探究心をより引き出すことができるといえる。
デジタル教科書・教材×ICT活用
そのほか、いわば教科書をICT化したデジタル教科書・教材との組み合わせも、理科の観察し、考察する力を身に付けることに寄与する。
「唾液とでんぷんの反応実験(小6)」:児童が自分の唾液を使い、でんぷん液との反応を観察。ヨウ素液を加えることで色の変化を確認し、消化の仕組みを学ぶ。その際に、デジタル教科書のQRコード付き動画を視聴し、実験の手順や結果を確認。電子黒板で実験結果を共有し、異なる結果の原因を考察する。
「メダカの誕生(小5)」:メダカの卵を観察し、かえる様子を記録。成長の過程を学びながら、生物の生命の営みを理解する。デジタル教科書の動画再生でメダカの成長過程を確認し、観察のポイントを学ぶ。書き込み機能を使い、卵の変化を記録し、比較する。拡大表示で細かい部分を観察し、特徴を詳しく学ぶ。
「電気回路の学習(中学)」:電池、導線、電球を使って直列・並列回路の違いを観察し、電流の流れや電圧の変化を測定しながら電気の性質を学ぶ。デジタル教科書のシミュレーション教材を使い、異なる回路の電流・電圧を比較。デジタルノートで実験結果を記録し、考察をまとめる。オンライン資料を活用し、電気の応用例を調べるなどができる。
「台風と気象情報(中学)」:気象データを分析し、台風の進路や影響を予測。過去の台風のデータを比較しながら、気象の仕組みを学ぶ。デジタル教科書のコマ送りアニメーションで台風の動きを視覚的に理解。気象衛星画像を活用し、雲の動きと降水量の関係を分析。書き込み機能で台風の進路を予測し、考察を深めることができる。
とりわけ、現在「英語」「算数・数学」から先行導入されている学習者用デジタル教科書が「理科」においても導入されるようになれば、より深い理解や主体的な学習が促進することが期待できる。
例えば、今年4月に実施した中学校理科のCBT方式による「全国学力テスト」では、8つの動画、2つのアニメーションが掲載され、これを参考に考察して解答するようにさせていた。動画やアニメーションの活用は、ただの視覚的補助ではなく、科学的な思考力を問う問題の質を高める手段になっている。つまり、ICT活用を取り入れることで、子どもの探究力、観察力、論理的思考力をより深く評価しようとしているのだ。
五感を通した学びが興味関心を引き出す
一方で、理科の学びに対して子どもが探究心を持つためには、最初の動機づけとなる興味・関心を引く必要がある。だからこそ、現行の学習指導要領では実際に子どもたちが体験することを重視し、「観察・実験」の機会を増やすことを求めている。座学では得られない、目の前で起こる事象を経験させ、五感を通して学ぶことが興味・関心を引き出す近道や動機づけになるからだ。
文科省においても、そうした実感を伴った理科教育の機会が増やせるよう、これまで5・6学年のみだった小学校での教科担任制を3・4学年まで拡大したほか、教員業務支援員の配置を拡充することに取り組んでいる。その流れの中で、教員が理科の授業に専念できる環境を整えようと、さいたま市のように観察・実験アシスタントを104人募集する自治体も現れている。
また、中・高校に対しても、ICTを活用した文理横断的な探究的な学びを強化する学校などに対して、そのために必要な環境整備の経費を支援したり、先進的な理数教育を実施する高校をSSHに指定したりする事業を強化している。
大学機関も、将来につながる理工系への関心を高めるため、中・高校との連携を強化。出張授業や各種公開講座への生徒の受け入れ、共同研究などを実施するところが増えている。
GIGA第2フェーズを迎えて
現在、学校現場ではGIGAスクール構想第2期となる端末更新が進められている。そこでは第1期において各教科で利活用したノウハウを活かして、さらに学びの質を向上する使い方へと高めていくことが求められている。
理科においても、観察・実験の結果をより明らかにするためや、児童生徒一人一人の主体的な学びにつなげていくために学習者用端末を活用していくことが必要になっている。そして、こうした学びを理科ならではの深い考察へと発展させていくためには、デジタル理科機器・各種ソフトウェアの充実が不可欠であり、理科の特質に応じたICT活用を支えるツールとなるはずだ。