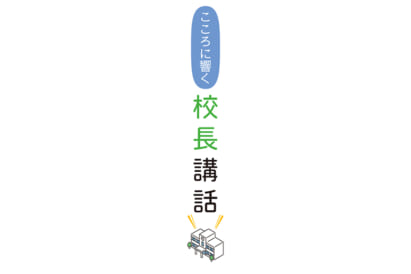学校の戦後史 新版
13面記事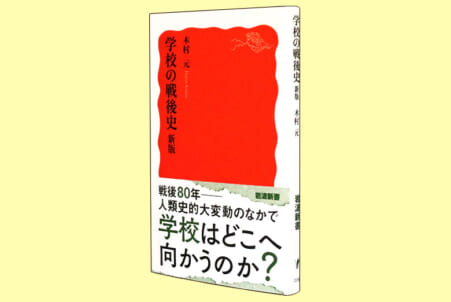
木村 元 著
政・財界、国際情勢との関係浮かぶ
本書の旧版は「戦後70年を迎えた2015年に上梓」され、新版は、戦後80年を迎えた時点での叙述だ。「この10年の動きはあまりにも大きなもの」との認識の下に、「戦後の学校が今後はどこに向かおうとするかをとらえるための一助となれば」との思いで書いたとある。
私は、国公立の小学校現場でのみ38年間を実践者として過ごし、退職後は大学の教員として、20年を経た者である。その身で本書を読むと、私の知る公教育の世界がいかに狭いものであったかと恥じ入るばかりだ。
公教育の現場が、政界、財界、あるいは国際情勢等々との多様な関わりの中で、いかに支えられ、揺さぶられ、求められ、指示され、批判され、期待され、もまれてきたかということを改めて知らされた。本書は、実に多くの教育事例や背景や資料を渉猟し、分析、考察を加え、読者に今後の教育の在り方を問い続けている。
第四章「学校の基盤の動揺」(制度基盤の変容、学力と学校制度の新動向など)、第五章「問われる公教育の役割」(学校の見直しの動向、学校制度の周辺、周縁の活性化、人口減少社会の地域と学校、「教える」ことの岐路など)の両章が格別の説得力で迫る。
本書は、20世紀は「学校の世紀」であり、「共通の内容をみんなに保障」を目指したが、今後は「個性・多様性」との折り合いが大きな課題となるだろうと提言している。
(1100円 岩波書店(岩波新書))
(野口 芳宏・植草学園大学名誉教授)