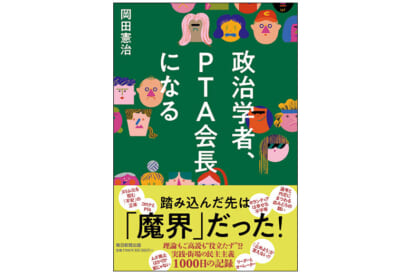一刀両断 実践者の視点から【第702回】
NEWS
リーダーの判断力
相手が嫌がる事はしない。そうした配慮の必要性が共生共存で必要な事とされている。
意見が異なる場合や明らかな間違いがあった場合、さらには相手を陥れる意図のあるデマや噂の類があった場合でも配慮は必要という事だろう。
除籍の後に卒業を認める場合とは、特別な場合に限られる。やむなく通えなくなり、その後大学の名誉となる功績を挙げたとか貢献したなどの場合に審議検討されて認可される場合はあるだろう。
それ以外は厳格に対応されている事になる。
明らかなそして不誠実な言動に対して、厳しい叱責や抑止の出来ない有り様は、秩序の乱れを招いてしまう。
そこへも配慮が必要とした場合は、不信感の増長は避けられない。
こうした対応の場合、自分がどう思われるかを計算に入れると、対応が遅れ私利のために忖度していると指摘されても致し方ない。
学校でも対保護者や生徒さらには職員への対応でも試される事になる。
夏の職員作業を全員で行う時に、校外学習の打合せを入れて作業を抜けた学年があった。その意図がはっきりしていたが、皆は黙していた。
私は教頭として、作業後の職員室で飲み物を配り作業確認をしていた際に、何故この時に打合せをするのですかと問いただした。
その後、校長から期待とは真逆の指導があった。あのような指導はしないようにとの事だった。
呆れた。こうした校長を支えるのは耐え難いが、立場上従うしかない。その時に、こうした校長を選考しないようにと心に決めた。
その意味では、その後の面接で判断力や人物を見定めるのに大変役立った。リーダーの資質や力量は判断力に如実に現れると感じている。
(おおくぼ・としき 千葉県内で公立小学校教諭、教頭、校長を経て定年退職。再任用で新任校長育成担当。千葉県教委任用室長、主席指導主事、大学教授、かしみんFM人生相談「幸せの玉手箱」パーソナリティなどを歴任。教育講演は年100回ほど。日本ギフテッド&タレンテッド教育協会理事。)