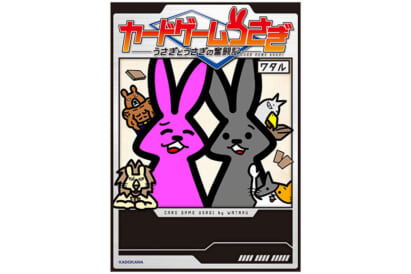交通社会で生きる知恵やモラルを授ける 社会変化に対応した交通安全教育指導を
9面記事
子どもの交通事故は登下校中が約37%と最も多い
子どもの交通事故は登下校中が多く、その大半が急な飛び出しや信号無視などの法令違反が原因となっている。特に中・高校生の自転車通学では、スマホを見ながら、音楽を聴きながらなどの「ながら運転」が相変わらず目立っており、事故の危険性はもとより自らが加害者となる恐れもある。こうしたことから、学校では交通社会で生きる知恵やモラルを授ける教育を重視することが求められている。
車の安全技術は進化しているが
日本の交通事故件数は2004年をピークに減少しており、3年前にはピーク時の3分の1以下にまで減少している。その要因の一つとして挙げられるのが、車の安全技術(ASV:先進安全自動車)の進化だ。例えば、衝突被害軽減ブレーキ(自動ブレーキ)やペダル踏み間違い時加速抑制装置、車線逸脱警報・レーンキープアシスト、死角にいる車両を検知し、ドライバーに警告する装置などである。また、道路交通システムやインフラの改善では、自動車アセスメントやLED信号機や高輝度標識の導入による夜間の視認性向上、環状交差点や右折専用レーンの整備、高齢者・子ども向けゾーンの拡充などが行われている。
さらに、交通違反の厳罰化・法制度の強化として、あおり運転の厳罰化や飲酒運転の罰則強化、高齢者への認知機能検査や運転技能検査の強化などが進められてきたこともある。
このようなクルマ社会の安全対策が進む一方で、子どもの交通事故を分析すると、「登下校」時における「横断歩道横断中」の「飛び出し」が多いことが分かる。中でも、「見通しが悪い場所」での事故は、全年齢の4倍近くに達している。信号機のない横断歩道における事故のうち、自動車が横断歩道手前で減速したケースは1割未満というデータもあり、歩行者を含めた交通ルール順守の徹底が今も課題になっている。また、自転車関連事故も3年連続で増加しており、特に10代は「安全運転義務違反」による事故が目立っているのが特徴だ。
社会環境の変化が生む予期せぬ事故
近年の交通事故の課題では、交通ルールを順守するだけでは回避できない事故が増えていることが挙げられる。その一つが、年々増加する高齢ドライバーの判断力や注意力の低下による予期せぬ事故だ。歩行者や自転車の見落としはともかく、アクセルとブレーキの踏み間違い、路外逸脱や逆走による事故への予測は困難である。また、ドライバーが運転支援システムに依存しすぎて注意力が低下し、事故に至るケースも多いほか、都市部では渋滞回避やナビの指示による急な車線変更が事故の引き金になることがある。特にタクシーや配達車両など、業務中の車両による予測不能な動きが問題視されているところだ。
加えて、2023年の法改正により免許不要で公道走行が可能になった電動キックボードは、歩道や車道を自在に行き来するケースがあり、ドライバーにとっては動きが読みにくい存在となっている。これらの予測困難な事故の背景には、多様化する交通手段と利用者の行動パターンの複雑化がある。従来の「車対車」「車対歩行者」といった単純な構図ではなく、電動モビリティやスマートフォンの普及など、社会環境の変化が事故の構造を変えているのだ。
こうしたことからも、子どもたちには歩行中のスマートフォンの使用を控えるといった、自覚的に交通社会と向き合う力を植え付けることはもちろん、危険を予測し回避する能力を養うための交通安全教育を重視することが必要になっている。
抜けて多い高校生の自転車事故
子どもが通学など日常の足として使う自転車は、事故に遭った際の重症化を防ぐため、改正道路交通法の施行によって2023年4月からヘルメット着用が努力義務化された。しかし、au損保が実施した今年1月の調査では、全国のヘルメット着用率は22・9%にとどまっている。前回調査よりも3・5ポイント高くなっているものの依然として低く、定着するにはほど遠い状況だ。しかも、地域ごとの差が大きくなっており、特に大阪府や千葉県など都市圏で着用率の低さが目立っている。
また、警察庁の統計によれば、昨年の高校生の自転車事故による死傷者数は全年代平均の約4倍に達しており、特に登下校中の事故が多発していることが明らかとなっている。にもかかわらず、高校生の自転車用ヘルメットの着用率は1割程度と改善が見られていない。
ヘルメット着用の義務化に向けた動き
このため、都道府県の中には自転車通学時のヘルメット着用を校則や通学許可条件として義務化する方針を打ち出すところも多くなっている。具体的には、鳥取県、山口県、愛媛県、高知県、大分県、福岡県の6県が、県立高校におけるヘルメット着用を義務化。愛媛県では、約10年前から県立高校に対してヘルメット着用を校則で義務付けており、昨年時点での着用率は全国1位の69・3%に達している。福岡県では昨年4月から、県立高校における自転車通学時のヘルメット着用を義務化し、校則に通学許可条件として明記。県警との連携による啓発活動や、模範生徒による着用促進イベント「高校生自転車ヘルメット着用促進リーダーズグランプリ」なども開催されている。
また、東京都も義務化には至っていないものの、昨年4月から都立高校において自転車通学を許可する条件としてヘルメット着用を必須とするよう、各校に指導が行われている。都内では約5万千人の生徒が自転車通学をしており、着用促進の必要性が高まっているからだ。これらの取り組みに共通するのは、単なるルールの制定にとどまらず、学校・保護者・警察が連携し、生徒の安全意識を高めるための教育的アプローチが重視されている点である。
ただし、全国的な広がりに向けては、義務化することで「教員の指導負担が増える」「家庭の費用負担が課題」といった声があるのも事実だ。したがって、さらなる補助制度の整備や地域全体での支援体制の構築が求められているところだ。
電動アシスト自転車利用の注意点
通学では、全国的な路線バス廃止・減便が支障を及ぼしている。通学手段をバスに依存していた家庭では、授業開始に間に合わない、通学そのものが困難になるといった事態が発生しており、教育機会の平等が脅かされている。こうした中、坂道の多い地域や通学距離の長い高校生を中心に、電動アシスト自転車の利用も広がり始めている。
一部の高校では安全面や公平性の観点から使用を禁止している場合もあるが、申請制で許可している学校も多く存在する。その中で、学校として注意する必要があるのが、昨年の改正道路交通法により、原動機付自転車(原付)の「運転」の定義が明確化されたことだ。
すなわち、電動アシスト自転車であれば運転免許は不要だが、フル電動自転車(モペット)やペダル付き電動バイクなど、モーターだけで走行できるタイプは、原動機付自転車として扱われるため、原付免許や普通免許が必要になる。併せて、これらのタイプはヘルメットを着用し、自賠責保険に加入しなければならない。
なお、電動アシスト自転車においても、アシスト比率や構造が基準を超えるものはペダル付き電動バイクに該当するため、購入する際は「型式認定TSマーク」が表示されていることを確認してほしい。
自転車の交通違反 来年4月から反則金

自転車の逆走の反則金は6千円
自転車の安全対策に向けては、警察庁が16歳以上の自転車運転者の交通違反に対して、来年4月から反則金を科すことにしたのも大きなニュースだ。いわゆる「青切符」制度の導入になるが、例えば信号無視や逆走は6千円、一時不停止や無灯火は5千円の反則金となる。また、高校生がやりがちなスマホ使用・ながら運転は1万2千円、イヤホン・ヘッドフォン使用は5千円、2人乗りは3千円となっている。
これまで注意や指導で済まされていた軽微な違反も、金銭的なペナルティが発生する。したがって、生徒本人だけでなく保護者への影響も大きくなることから、学校では次のような対策が求められるようになる。
1.交通ルールの再教育と啓発活動の強化:最も重要なのは、生徒に対する交通ルールの再確認と意識づけになる。多くの学校では警察署や交通安全協会と連携し、交通安全教室や講話を実施しているが、今後は青切符制度の内容を盛り込んだ特別授業の実施や、学年集会での周知、交通ルールに関する小テストの実施など、より実践的な取り組みが求められる。
2.校則・通学許可制度の見直し:制度施行に伴い、校則や通学許可制度の見直しも必要。具体的には、自転車通学許可の条件として「交通ルールの遵守」「ヘルメット着用」「保険加入」を明記。違反が確認された場合の指導・処分規定の整備。電動アシスト自転車の使用条件の明確化などについて検討し、学校としての指導責任と生徒の自覚を両立させることが重要になる。
3.保護者との連携強化:反則金制度は金銭的な負担を伴うため、保護者への情報提供と協力体制の構築が不可欠である。学校からの文書配布や説明会の開催を通じて、制度の趣旨や違反時の影響を伝えることも大切な役割になる。
自転車通学が6割、命を守るヘルメット着用を徹底
京都府・京田辺市立田辺中学校

自転車用ヘルメットを装着して登校する生徒たち
非着用者の死亡率は着用者の約1・8倍に達する―。この統計からも、自転車に乗る際にはヘルメット着用が不可欠であることが分かる。そこで、約30年前から通学時のヘルメット着用を義務化している、京田辺市立田辺中学校の家村隆宏校長に、交通安全への取り組みについて聞いた。
市教委がヘルメットを無償支給
市域の半分が校区に含まれる同校は、全校生徒が千名を超える大規模校だ。そのうち約6割が自転車通学をしており、今年度の1年生だけでも230名余りが自転車で登校。通学路の起伏が激しいため、約半数の生徒が電動アシスト自転車を利用しているのも特色の一つだ。
「学校は交通量の多い府道に面しているため、日々の登下校は心配が尽きません。だからこそ、ヘルメットは命を守る最も基本的な装備です」と家村校長は語る。
現在、通学時に使用する自転車用ヘルメット(カワハラ製)については、市教委が自転車通学対象者へ小6の卒業前までに無償で支給している。着用義務化に向けては「保護者の費用負担」が一つの障壁となる学校も多い中で、こうした取り組みが他の自治体にも待たれるところだ。
デザインの進化が意識と行動を変える力に
また、以前は「ダサい」「かぶるのが面倒」と敬遠されがちだった自転車用ヘルメットだが、今日ではデザイン性が進化して抵抗感が軽減。それが学生の意識と行動を変える力にもなっている。「安全面とともに通気性などにも配慮されるようになっています」と話すように、日常的なかぶりやすさも着用率を高める大事な要素だ。
同校では、ヘルメット着用と自転車保険加入を条件に自転車通学を認めているが、実際の着用率についても、ヘルメットを着用しないで登校するような生徒は皆無であると自信をのぞかせる。「むしろ、地域の方から“最近の中学生はきちんとヘルメットをかぶっていますね”といった声をかけてもらうことが多くなりました」と話す。
さらに、ヘルメットの着用だけでなく、事故時の重症化を防ぐために重要な「あごひもの正しい締め方」など装着指導にも気を配っているという。
実技練習を通じた安全意識の育成
交通安全指導は年間を通じて継続されており、特に1年生は入学直後に警察署による講習を実施。併せて、自転車通学者は自転車運転に関わる交通ルールの実技練習も行う。校庭に模擬交差点を設置し、実際に自転車に乗って一時停止や後方確認を体験することで、肌感覚でルールの重要性を理解させることがねらいだ。
今後の課題としては、走行中の「周辺への安全の配慮」が欠けている部分が見られることを挙げた。その上で、「自転車は加害者にもなり得る交通手段。交通ルールの順守とともに、交通社会の一員としての責任ある態度を伝えていきたい」と展望を語った。

実技練習の成果を安全走行に活かす