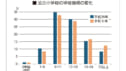2025年共通テストから今後の高校教育を考える 東京・大阪2会場活況、配信も
10面記事
東京で開かれた全体会の会場。東京と大阪ともに、大勢の高校教員が集まった
第12回夏の教育セミナー報告
日本教育新聞社と、東進ハイスクール・東進衛星予備校を運営する(株)ナガセが主催する第12回の「夏の教育セミナー」が8月1日と4日、東京会場と大阪会場で開かれた。現行の学習指導要領の下で今年1月に初めて実施された大学入学共通テストの振り返りや、次期学習指導要領の方向性、生成AIの教育活用の在り方など、バリエーション豊かなテーマで講演や分科会が行われた。全国から多くの高校教員が集まり、大盛況となった。セミナーの様子は後日、オンラインでも無料配信された。

主催の(株)ナガセの永瀬昭幸社長

日本教育新聞社の小林幹長社長
基調講演
将来の選択肢増やす教育を
橋本 雅博 中央教育審議会会長 住友生命保険相互会社取締役会長・代表執行役

東京会場では、中央教育審議会会長の橋本雅博・住友生命保険会長が「社会の変化と教育の役割」をテーマに講演。経済社会や組織経営の視点も踏まえ、文理融合教育や探究的な学びの必要性を訴えた。
橋本氏が委員長を務めた経団連の委員会は今年2月、「2040年を見据えた教育改革」と題する提言を発表した。高度成長期から続いた画一的・一斉型の教育から、多様性や好奇心、探究力を中心に個の力を伸ばす教育への転換を求める内容だ。そのためには教員人材の多様化や専門高校の魅力向上も必要だと説明した。
企業はかつて、社会的責任(CSR)を果たす目的で教育に関与することが多かった。しかし、最近は学校現場に社員を出向させるなど、より積極的に関わる企業が増えており、学校教育への協力機運が高まっているとの見方を示した。
日本が抱える最大の課題として少子高齢化と人口減を挙げ、個々の能力を上げていかなければならないと強調。その上で、中教審が2月にまとめた大学関連の答申で、人口と個々の能力をかけ合わせた「知の総和」の向上を求めたことに触れた。就業構造の変化が進む中、教育は将来の選択肢を増やすことに資するものであるべきだと指摘した。
橋本氏は、文理分断からの脱却や文理融合教育を促し、高校教育を変える最大の要素は大学入試だと訴え、教科学習の知識を基に実社会の課題を見つけ、解決策を導く力を評価する入試が広まることに期待を寄せる。
また、高校教育に期待される役割、使命として「ウェルビーイング」「多様性」の二つを挙げた。
講演の締めくくりに強調したのは教員の労働環境の改善だ。経営者としての自らの経験に触れ、働き方改革では、管理職が率先して業務の廃止や精選を判断することが重要だと訴えた。「現場の裁量や工夫を保証・拡大することが改善につながる。教員が生徒一人一人と向き合う余裕を確保することで、教育の本質に専念できる環境が生まれる」と述べた。
人材需要と教育、乖離解消へ
合田 哲雄 文部科学省高等教育局長 兵庫教育大学客員教授

現在、中央教育審議会で改訂の方向性が議論されている次期学習指導要領は、学校の裁量拡大に向け、過去に例のない規模で見直しが検討されている。大阪会場で基調講演した文科省の合田哲雄・高等教育局長は、これまで2度の改訂に関わった立場から、なぜ次期改訂がこれほど大胆に議論されているのか、その背景について個人的見解を述べた。
合田氏は、学習指導要領が昭和33年に制定されてから7回あった全面改訂と、今回の改訂との決定的な違いは、児童・生徒が1人1台の情報端末を持つ時代になったことだと指摘した。明治時代に学制が始まり教科書が知識を爆発的に普及させたのと同じように、現在の子どもたちは「メディア革命」の真っただ中にいると強調した。
こうした状況で検討されている次期改訂の核心について、合田氏は教科書網羅主義と指導書準拠主義、暗記偏重型の入試という「鉄のトライアングル」をいかに変えるかだと説明した。中教審では、それぞれの教科で「中核的な概念」を中心に目標や内容を整理する「構造化」を進め、網羅主義からの脱却を目指すとしている。
また、高校では多様化する生徒の実態に応じた教育課程を編成できるようにするため、複数の科目を組み合わせた新科目の設定や、学校設定科目の上限単位の引き上げなどが検討されていることも紹介した。
労働市場と教育の乖離の問題にも言及した。専門学科を含めた高校全体の約半数の生徒が文理分断型の文系で学んでおり、この状況が社会の人材需要との乖離を生んでいると指摘した。経産省は今後、事務職や管理職は不要になる一方、AIやロボット分野の専門人材は数百万人規模で不足すると試算している。合田氏は高校での文理分断の弊害が「将来に深刻な影響を及ぼす」と危機感を伝えた。
こうした社会の人材需要を踏まえ、文科省は近く、高校教育に関する方針を策定する見通しで、普通科と専門学科のバランスや文理分断の脱却も盛り込むとみられる。合田氏は、大学と高校が連携して議論を進めると述べた。
特別講演
高大接続の入試改革なお継続
片柳 成彬 文部科学省高等教育局 大学振興課大学入試室長

文科省の片柳成彬・大学入試室長は、今年1月の大学入学共通テストの振り返りと来年度入学者選抜のルールの変更点などを話した。
最初に高大接続改革の歩みの振り返りや、入学者選抜における女子枠の広がりと好事例集を紹介。
今年の共通テストは、現行の学習指導要領に対応した最初の入試で、新科目「情報Ⅰ」等の変更があったが、大きなトラブルなく運営された。片柳氏は、試験全体として設問の文字数の多さを訴える声があったとしながらも「情報の多い現代社会に対応するために必要であった」と振り返った。共通テストは来年からインターネット出願が導入され、受験生が出願手続きを行うことになる。講演では出願の流れについて解説し、専用サイトには8月までに20万人が登録していると紹介した。
一方、個別入試では昨年、一部の私立大学が学力検査を年内に前倒しで実施したとしてガイドライン違反に問われた。しかし、その後、大学と高校の代表者による協議の結果、小論文や面接、実技など2種類以上の評価方法を組み合わせることを条件に学校推薦や総合型選抜の「年内入試」で学力試験を実施することが容認された。片柳氏は、こうした決定が「多面的・総合的な評価をする」という基本原則に立ち戻る大学の考えが反映されたものだと説明した。
講演後の質疑応答では、年内入試への制限が必要だとする意見に対して、「関係者間の議論によって今後、新たなルールが盛り込まれる可能性はある」などと指摘した。
また、共通テストでのCBT(コンピュータ型テスト)実施の見通しを尋ねられると、片柳氏は「大学入試では公正性や公平性が厳しく求められるため、すぐに導入することは難しい。今後数年で大きく変わることはないのではないか」と見解を述べた。
AIでイノベーション起こす
松尾 豊 東京大学大学院工学系研究科技術経営戦略学専攻/人工物工学研究センター教授

AI研究の第一人者である東京大学の松尾豊教授は講演の冒頭、一つの動画を紹介した。まるでSF映画のようなその映像は、最新モデルの生成AIが作成したものだ。今年4月には、複数の生成AIが東京大学の入試問題で理科三類の合格最低点を超える得点を獲得。生成AIが人間と同等か、それ以上の学力を持つことが示唆された。
松尾氏はAIの歴史や鍵となる技術・考え方を説明。その上で、今後の技術進展の見通しについて、与えられた目的に合わせ、自ら計画を立てて作業する「AIエージェント」と、AIを組み込んだロボットが発展し、頭脳労働と肉体労働の両方で自動化が進むと指摘した。
大学ではデータサイエンスやディープラーニングの講義を運営する。講義の多くはオンラインで東京大学以外の学生にも提供している。
自身の研究室から起業する学生も多く、これまで35社のスタートアップが出ている。目指すのは「イノベーションのスパイラル」だ。AI人材を育て、共同研究によって企業の競争力を強化。それをきっかけに新規事業を生み出すサイクル(エコシステム)をつくることだという。東南アジアやアフリカなどにも海外展開をしている。
学校現場では今後、AIの活用を前提とした学びが見込まれているが、松尾氏は「AIを使いこなすだけでなく、法律や経済を理解したり、人の気持ちに共感したりするなど、総合的な力が必要になる」と話した。
授業の対話分析、指導力向上へ
遠藤 太一郎 東京学芸大学教育支援協働実践開発専攻(大学院教育学研究科)教授 (株)カナメプロジェクト取締役CEO

企業へのAI導入サービスを手掛ける「カナメプロジェクト」のCEOで、東京学芸大学教授の遠藤太一郎氏は、教育分野でのAI活用の可能性について講演し、附属学校で試験実施した学習評価のルーブリック作成の取り組みを紹介した。
遠藤氏らは中学校の社会科と国語科で、生成AIに学習指導要領を読み込ませてルーブリックを作成。学習課題に対する生徒の解答も読み取らせ、ルーブリックに照らして自動判定する仕組みを開発した。評価結果を基に、生徒への学習のアドバイスや、教員に指導方法を提案する機能も搭載した。
「実践検証によって、教員が最終的に評価する際の参考にできるレベルにあることが明らかになった」とした上で、これを教員の負担軽減につなげるためには授業の構成などを変えていく必要があると指摘した。
教員の指導力向上を目的に、授業での教員と生徒とのやりとりもAIに分析させた。AIによるフィードバックや教員と生徒の対話記録を教員同士が共有することで、学校全体の指導力の底上げにつながると提案した。
また近い将来、技術的に可能になることを予測し、「デジタル教材とAIの技術を組み合わせることで、日本中の子どもたちに対して、学習の進み具合をリアルタイムで把握したり、データに基づいて個別に対応したりすることが考えられる」などと述べた。
分科会
国語
古文読解、まず欠如部分探して

辻孝宗氏
分科会の冒頭、「国語で世界を変えたい」と熱く訴えた辻孝宗・西大和学園中学校・高校教諭。得意の手品を披露しながら、言葉というのは、味覚や視覚さえ変え、本物に触れるのと同じようなイマジネーションを感じさせるほど強いものであり、それを私たちは扱っていると語った。
古文の解き方の解説では大学入学共通テストや東京大学の過去問を使い、物語の全体像をつかむ方法として、最初に「欠如」した部分を探し、それが「充足」に向かっているかを見る方法を提示。「全体」像をつかんだ上で「まとまり」「部分」を読み解く方法を示した。「欠如」から「充足」に向かうのは、神話と構造が共通しており、世にある大多数の物語も同じ流れにあるという。
今の時代に古文を教えることの意義については、文化を含めて相手のことを理解する大切さを伝えられることにあるとし、一言で表すと、それは「優しさである」と言う。
目の前で起きた出来事は変えられないが、解釈を変えたら、マイナスをプラスに変えることもでき、広い意味で幸せとは何かを教えられる教科でもあると結んだ。【東京会場】
知識構成型ジグソー法 特長は

板谷大介氏
埼玉県立浦和第一女子高校の板谷大介教諭は知識構成型ジグソー法(KCJ)の特長をワークショップ形式で解説した。最初に参加者が近代短歌の魅力を考える教材を使い、
(1)授業前の問い
(2)エキスパート活動
(3)ジグソー活動
(4)クロストーク
(5)授業後の問い
―を体験した。
これを踏まえて、KCJの強みとして、生徒に関しては、他人の発想を学べること、思考力が育成されること、論述力が養われることなどを挙げた。教員については、授業の成否が確認できること、生徒の学びが「見える化」されて指導が最適化することなどを示した。
授業づくりについては、既に作られている教材をそのまま、または自校用にアレンジして使えること、一度作れば再利用可能なこと、教材のPDCAサイクルを回せることを伝えた。何度も使った教材の場合、生徒の論述をルーブリックなどで評価することも可能になるとした。
そして、探究学習のツールとして非常に便利で、養われた学力は国公立大学二次試験に直結すること、学校に「教え合い学び合い、支え合い励まし合う」文化がつくられることを強調した。【大阪会場】
数学
「自分たちで考える」を基本に

堀内陽介氏
千代田中学校・高校の堀内陽介教諭は、学校改革を進める同校での実践を紹介した。
「生徒たちが自分たちで考える」を授業の基本スタイルとし、生徒の学びに対する意欲を引き出しているという。類題・別解・実験・タイムトライアルの各ワークを紹介。数学に苦手意識を持った生徒たちが、仲間と考えを共有しながら正解に至る過程を体験できるよう、工夫を凝らしている。
「丸暗記していた数学を考えるようになった」といった声や、校内アンケートで好きな教科2位になるなどの反応を得たという。
次にカリキュラム・デザインについて解説。数学Cの「ベクトル」を高校2年生の最初に教える指導方法を提案した。「図形と式」や「三角関数」など他の分野の学習に幅広く応用できるためだ。
同校の「研究活動」についても発表した。担当する「数論ラボ」に集まった生徒4人は、数論に関する有名な定理を参考に新しい法則を発見し、今年7月に代表者が海外で発表を行った。最後に「生徒たちが学びを楽しみながら、未来を切り開くための後押しをする教育の原点に返ろう」と呼び掛けた。【東京会場】
生徒と同じ視点で向き合う

喜田英昭氏
広島大学附属中・高校の喜田英昭教諭は「数学を探究し、数学を発見し、数学を創り出す」をテーマに講演した。
ワークを用いたアイスブレイクの後、講演では主に三つの実践事例を発表。数学Aの図形分野では、三角形の垂心の軌跡を考える学習から、外心や重心との位置関係の考察に至るまで、五つの学習活動を説明した。
次に、漸化式を用いた数理モデリングの教材を示した。ある生物の個体数の推移を予測することを主題とした。表計算ソフトを使い、差分方程式に含まれる定数の値を変えた関数グラフが収束する様子を、自然界の現象と関連付けて探究。喜田氏は「数理モデルから何が分かるかを考えることが大事」と強調した。
最後は、生成AIで作成したアプリを使った確率分布の実践。あみだくじの当たりやすさに関する予想が正しいかをシミュレーションを基に考察する。生徒が新たな課題を設定し、発展的に探究した事例も示した。
「生徒が考えたくなるような本質に迫る問いを基に授業を組み立て、生徒と同じ視点で数学と向き合う意識が重要」とまとめた。【大阪会場】
英語
日々の業務、AIで10倍効率化

安河内哲也氏
東進ハイスクール・東進衛星予備校の安河内哲也講師は「ど文系」でもできる教師向けAI活用法を紹介した。「授業も仕事も10倍効率化できる」と強調。分科会のスライド資料はAIで全て作成したことを明かすと、参加者から驚きの声が上がった。
日頃から文字起こし、教材作成、さらには作曲までAIに任せているという。分科会では、AIに作詞・作曲・歌唱させた「英文法完全理解ソング WISH」を流した。普段、生徒たちは曲を口ずさむうちに、自然と仮定法の文法事項を覚えることができると紹介した。
今後重視されるのは「頭と口が動く授業」。例えば、AIを活用し、暗唱やシャドーイングなどを用いたアウトプット中心の活動型授業だ。どのAIを使うかではなく、何を創るかが重要になると強調した。
日々の業務にAIを活用することで、「人間にしかできない創造的な仕事」に時間を割くことができるようになる。「AIを使いこなす司令塔として、創造力を磨く。それがこれからの教師の使命」と締めくくった。【東京会場】
AI活用では遊び心を持とう

武藤一也氏
東進ハイスクール・東進衛星予備校の武藤一也講師は、英語指導資格CELTAの知見を基に、授業準備などでの生成AI活用を解説した。
まず取り上げたのは、東京大学の英作文問題で武藤氏とAIが作成した解答の比較。参加者はペアで話し合い、良いと思った方に投票。武藤氏の解答に軍配が上がった。その理由として、「AIの解答にはない『想像力』や『気配り』が含まれている」と述べ、「これまでの『学びの文脈』『教師の指導経験』が反映されている」とも語った。
生成AIの活用場面として
(1)英文のチェック
(2)英文の作成
(3)CCQs(学習理解を確認する質問)の作成
(4)単語リストの作成
(5)日本語の文書添削
―の五つを紹介。これらの説明を踏まえ、共通テストの過去問を用いたミニ・レッスンを行い、リスニングとリーディングの指導に関する工夫についても解説を加えた。
AIは指示通りに動く。そのため、「遊び心を持つことで豊かな発想が生まれる」と語った武藤氏。最終的に生徒にとって何が必要なのかを判断するのは教師になる。「その作業こそが重要になる」とも強調した。【大阪会場】
探究
積極的に教員が動くこと大切
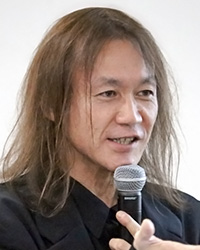
蛭田祥友氏
横浜市立南高校・附属中学校の蛭田祥友主幹教諭は、企業と連携しながら進めている同校の探究学習の取り組みを紹介した。1年生では、クラス単位でプロジェクト型学習を実施。SDGsについて学び、成果は動画などで表現。夏休み中には個人での探究を行い、休み明けに発表する機会も設けている。2年生では小グループで課題解決策の提案に向けた活動に取り組み、SDGsやビジネスプランのコンテストに参加している。
セミナーには同校3年生と、大学4年生の卒業生も登壇し、探究の学びや成果を話した。
3年生の生徒は、事業系の食品ロスの削減に向け、工場の廃棄食品などからできた飼料で育てた豚を使った食堂メニューや、地元の商店と連携してカツサンドを販売したことを説明。卒業生はニュージーランドへの語学留学の際に、現地の生徒と一緒に算数の教材を作り、途上国への教育支援としてバングラデシュへ届けたことを紹介した。
探究学習の推進に向けて、蛭田氏は「積極的に教員が動くことが大事」と強調した。その上で、管理職が覚悟を決めて進めていく必要性も訴えた。【東京会場】
キャリア・パスポートの活用を

酒井淳平氏
探究は実践の質が問われる段階に入ったと強調した立命館宇治中学校・高校の酒井淳平教諭。学習指導要領や大学入試で求められているからだけでなく、卒業後の人生でのテーマ(軸)を築く、教科を超えて成長する貴重な時間だと、探究に取り組む重要性について語った。
国際比較調査から、日本の子どもたちは学力が高い一方、「将来の夢がない」「自分で国や社会を変えられると思えていない」などの課題がある。生徒を管理・指導の対象と見る生徒観からの転換が必要だと指摘し、生徒自ら学ぶ力の育成に向けて探究が重要だと話した。同校では、自ら価値を生み出せる人材の育成に向けて探究を核に取り組んでいるという。
酒井氏は生徒自身が取り組みたいと思えるテーマで、探究的なサイクルを多く回せるかが、探究の質の向上につながると指摘。探究の学びを振り返る際にはキャリア・パスポートの積極的な活用を呼び掛けた。また、「教員の学びと生徒の学びは相似形」であるとして、現場で試行錯誤して学び、成長する教員集団になることが問われていると参加者を鼓舞した。【大阪会場】

探究の分科会の様子。次期学習指導要領でも探究学習の質の向上が目指されている
情報
LANなど本物使い、体験重視

能城茂雄氏
東京都立三鷹中等教育学校の能城茂雄指導教諭は、昨年度の実践の中から、生徒が主体的に取り組めるよう工夫した授業を紹介した。回路を組み立てて学んだり、本物のLANを用意してネットワーク設定をしたり、実際にさせてみることが重要だと強調した。
CPUを学ぶ授業では、導入で中学理科の回路図や高校数学の集合で学んだことが生かせることを示し、情報と他教科とのつながりを説明。
CPUの仕組みや役割は、能城氏自作の回路教材を使って教えた。生徒からは「初めはよく分からなかったが、作っているうちに回路の仕組みが分かるようになった」などと好評だったという。
「全ての高校生がLANの設定をできるようになってほしい」と能城氏。ネットワークの授業では、本物のルーターを1クラス分購入し、能城氏が用意したサーバーに、1人1台端末を接続した。
「知識として教える部分もあるが、生徒が自ら体験することで次の学びに使えるようになる。そのような内容を含めていくことがVUCA時代の学びにつながるのではないか」と訴えた。【東京会場】
言語化させる授業を心掛け

小原格氏
東京都立国立高校の小原格指導教諭は冒頭、大学入試センターがまとめた「問題評価・分析委員会報告書」を基に、今後の共通テストの出題傾向を分析した。「令和8年度の問題作成方針も7年度とほぼ変わらない。学習指導要領解説をいま一度しっかりと確認してほしい」と参加者に呼び掛けた。
授業づくりでは、言語化をさせることで思考力・問題解決力を育成することを心掛けているという小原氏。「情報は目に見えないものなので、言語などに『見える化』する必要がある。共通テストでも言語化する能力が問われている」と指摘する。
また、問題を発見・解決する力を育成するためには、解決(ゴール)を明確化することが重要だという。「本来、何かの問題を解決するためのプログラミングのはずが、ゴールをきちんと示さないと、ただプログラミングを書くだけで終わってしまう」と注意を促した。
小原氏は「授業で取り組んだことが共通テストで生かせれば、こんなにすてきなことはない。そのためにも、われわれ教員が日々アンテナを張っていきましょう」と話した。【大阪会場】
教員の役割変化を実感/生徒の進路実現に生かせる
参加者の声

ワークショップに取り組む参加者たち
【基調講演】教員の役割の変化が明確に伝わってきた(神奈川県・地歴科)
【特別講演】入試を理解する参考となった。生徒の進路実現に生かしたい(鹿児島県・数学科)、AIの最先端の話が大変分かりやすい。これからの時代を予想させてくれた(秋田県・英語科)
【分科会】勉強が苦手な生徒が多い学校なので、参考になった(茨城県・数学科)、探究的で対話的な学びの実際を、惜しみなくご提供いただいた(和歌山県・教育委員会)
夢・志を育む講座
経営者ら 高校生向けに講義
オンラインでは東進ハイスクール・東進衛星予備校が高校生向けに開講している特別講座も限定公開された。国が数兆円規模の支援を行う半導体メーカー・ラピダス会長の東哲郎氏、電機メーカーのコニカミノルタ前社長である山名昌衛氏、筑波大学の東野篤子教授らが講演した。
全国の高校の先生方へ
本セミナーが今後も共に学び合う場となるために、セミナーへの期待やご意見をお寄せください。今後のセミナー企画の参考とさせていただきます。