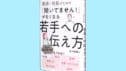社会科「自己調整学習」 学び方を生かした単元デザイン
18面記事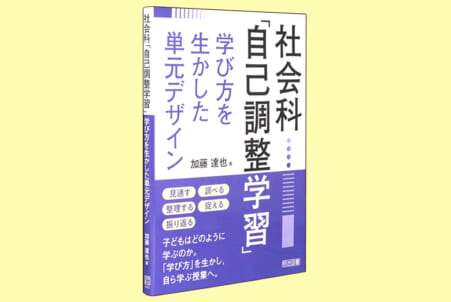
加藤 達也 著
自ら問題解決図る授業提起
「単元末に話し合う授業が終わり、学級全体としては目標が達成されたような結論に至ったにもかかわらず、ある子のノートを見てみると、書いたまとめが何だかちんぷんかんぷん…」。著者同様、こんな経験をされた方も少なからずいるのではないか。
「子どもが問題解決過程の5段階【見通す】【調べる】【整理する】【捉える】【振り返る】を使いこなすことで、学びが自分事になり、『自己調整』につながっていく」と、社会科での学び方の一つの在り方を示したのが、本書である。
「学び方」に着目し、子ども自らが学ぶ授業づくりを提起する第Ⅰ章から、「自己調整学習」を成り立たせる問題解決過程を段階ごとに解説する第Ⅱ章、「『社会がわかる』そして『自己調整』する単元統合型授業」を第Ⅲ章で提案した。
自らの授業実践を用いながら、失敗談も含めて、子どもの学びの姿も浮かぶような第Ⅱ章は、教壇に立つ指導者には理解しやすい。
学び方を子どもと共有することで、子ども自身が「今日はもう1時間【調べる】時間だよね」「まだ仲間分けができていないから、今日の【整理する】時間、頑張らないと」といった会話が交わされる教室に、受け身の学習者はいないだろう。
試行錯誤してたどり着いた「学び方」は、社会科だけでなく、他の教科などにも応用できることは、容易に想像が付く。子どもの学びの姿に立脚して、提案する好著だ。
(2046円 明治図書出版)
(矢)