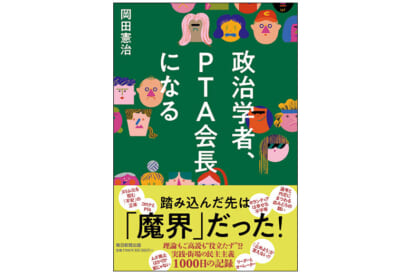指定避難所となる小中学校に災害用マンホールトイレを整備
12面記事
マンホールの上に便座と仮設ユニットを設けてトイレ機能を確保
大阪府高槻市 積水化学工業「防災貯留型トイレシステム」導入事例
災害時のトイレ環境整備に向けた高槻市の先進的取り組み―。災害時に避難所のトイレを確保することは、避難者の健康と尊厳を守る上で極めて重要な課題である。近年、避難所の開設期間が長期化する傾向にあり、従来の仮設トイレや簡易トイレのみでは、衛生的な環境の維持が困難となっている。こうした背景を踏まえ、全国の自治体では災害用マンホールトイレの整備が進められており、大阪府高槻市はその先駆的な事例の一つである。
災害用マンホールトイレの整備とその特徴

「災害用マンホールトイレ」の貯留管の設置工事
高槻市では、平成29年8月に「災害用トイレ対策基本方針」を策定し、令和元年度より市内の指定避難所である小中学校に災害用マンホールトイレの整備を計画的に進めている。採用されたのは、積水化学工業の「防災貯留型トイレシステム」であり、施工性や臭気対策、衛生面に優れ、下水道管路の状況に左右されず一定期間の使用が可能である。
このシステムは、避難所となる学校敷地内に事前に埋設することで、平常時の学校活動に支障を来さず、断水や仮設トイレ不足といった災害時の課題に備えることができる。耐震性にも優れ、一般的な水洗トイレの約5分の1の水量で排水可能なため、避難所で貴重となる生活用水の節約にも寄与する。
都市創造部下水河川事業課の田中幹郎主査は、「使用時には仮設トイレ用の管路に水をためて臭気を抑え、貯留槽の弁を1日1回開放して汚水を一括放流することで、衛生的かつ効率的な運用が可能です。さらに、下水道管路が損傷して放流できない場合でも、約5日分の汚物を貯留できる点が採用の決め手となりました」と語る。
地下式貯水槽を設置、一週間分の水を確保

併せて整備した貯水槽(7.0立方メートル)
同市では、マンホールトイレの整備に加え、容量7・0立方メートルの地下式貯水槽を併設し、約7日分の水を確保している。「これは、学校のプール水を前提とした場合、防火水槽としての利用や、被災により十分な水量を確保できない恐れがあること、さらに設置場所が限定されるという課題を解消するための工夫です。貯水槽の併設により、避難所となる体育館周辺の最適な場所にトイレを配置することが可能となり、要配慮者を含む避難者にとってアクセスしやすい環境が整えられるメリットがあります」と説明する。
令和6年度末時点で、指定避難所のマンホールトイレ整備対象である58箇所のうち39箇所において、計234基のマンホールトイレの整備が完了している。災害用マンホールトイレは、マンホールの上に便座と仮設ユニットを設けてトイレ機能を確保することになるが、各校でのトイレ設置数は6基となっている。内訳は女性用4基、男性用2基で、うち1基はバリアフリー対応の大型ユニットとなっている。
その上で、「設営に必要な資材や貯水槽から水を汲み上げる給水ポンプ一式は、近傍に設置した専用の備蓄倉庫に保管されており、災害時の迅速な対応に備えています」と準備に怠りはない。
地域住民による設営訓練で初動対応力を強化
今後の整備計画の見通しとしては、残りの19箇所(マンホールトイレ:114基)の整備を、令和9年度末までに完了する予定だ。加えて、市では防災訓練の一環としてマンホールトイレの設営訓練を実施しており、避難所運営に関わる地域住民が設置手順を実際に学ぶ機会を設けている。これにより、災害発生時の初動対応の迅速化を図り、避難所における衛生環境の維持につなげる方針である。