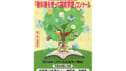実験×ICT~探究力を育む理科授業づくり~
11面記事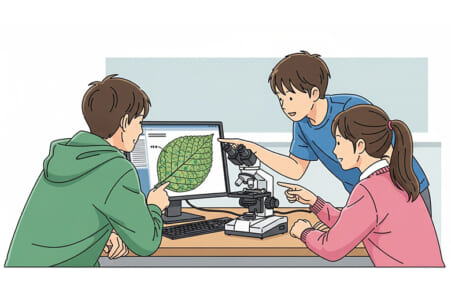
デジタル顕微鏡をPCに接続し、植物の組織を拡大画像にして観察
科学的に探究する力を育てるためには、「観察・実験」による実体験を軸にICTを補助的・拡張的に活用し、子ども一人一人の「なぜ」「どうして」という問いを引き出すことにある。ここでは、そんな子どもの探究する姿勢を引き出す理科授業の事例を紹介する。
小学校 タブレットで見えない世界を観察
「タブレットの拡大撮影+アプリ活用」
「観察・実験」といった体験活動とICTを組み合わせることで、児童の思考を可視化し、探究の深まりを支援する取り組みが広がっている。例えば、4年の授業「もののあたたまり方」では、湯の中で金属棒がどのように熱を伝えるかを調べる実験を行った。児童は湯を入れたビーカーに金属棒を差し込み、蝋(ロウ)を付けた地点が溶ける順序を観察する。
従来は目視による観察に限られていたが、グループごとにタブレットを使って実験の様子を拡大撮影。記録映像をスロー再生することで、ロウが溶ける瞬間の順序が明確に確認できたほか、温度計の数値変化をグラフ化するアプリを用いて、熱の伝わり方を定量的に捉えることができた。
教員は、ICTを「見えないものを見える化する道具」と位置づけ、児童が自分の観察を振り返り、仮説と結果を比較できるように指導するのがポイントになる。実体験とデジタル記録の組み合わせにより、感覚的理解から論理的理解へと発展させる授業になった。
同じく、3年の単元「磁石のふしぎ」における磁石のN極・S極の反発や引きつけを観察する実験も、一瞬で終わってしまうため、児童が見逃しやすい。そこで、児童自身がタブレットで実験を撮影し、スロー再生して動きを確認することで、「いつ反発したか」「どの位置で引きつけが始まったか」を検証しやすくすることができる。
また、3年の「植物の成長と日光の関わり」では、従来、児童は観察カードに手書きで記録を残してきた。しかし、今年度からタブレット端末を活用することで、毎日の成長記録を写真や動画で残す活動を導入した。児童は、日光の当たる鉢と日陰の鉢を比較しながら撮影し、アプリ上で成長の違いを時系列に並べて確認。ICTの活用により、児童は「前より葉の色が濃くなった」「背丈の伸びが速い」といった変化を視覚的に捉えることができるようになった。
・「天気の変化を学校全体で観察・共有する」
5年「天気の変化」において、校舎屋上に簡易気象観測機を設置し、気温・湿度・気圧などのデータをタブレットでリアルタイムに閲覧できるようにした。児童は天気図と合わせてデータを分析し、「気圧が下がると曇ってきた」「風向が変わると雨になることが多い」といった関係に気づくようになった。各クラスが異なる時間帯で観測し、結果をクラウド上で共有する仕組みを整えたことで、児童は他の時間帯のデータと比べたり、週ごとの傾向と見比べたりと自主的に探究が進めるようになった。
中学校 センサー実験で「データに基づく考察」を育む
中学校理科では、自然現象を法則や原理の視点から説明する力を育てることが求められている。そのためには「観察・実験」による体験的理解を土台としつつ、結果を科学的に捉えるための思考の可視化が重要になる。こうした中で、ICTは実験データの収集や共有、考察の深化を支援する手段として活用されている。
・「デジタル温度センサー×クラウド活用」
2年の「化学変化と熱の出入り」の授業では、発熱反応と吸熱反応をテーマに探究学習を行った。生徒は鉄粉と酸の反応、炭酸水素ナトリウムとクエン酸の反応を観察する。従来は温度計の読み取りを紙に記録するだけであったが、デジタル温度センサーを用いてデータをリアルタイムに収集。タブレットに接続したセンサーが温度の上昇・下降をグラフ化し、反応過程の違いを視覚的に理解できるようにした。
生徒たちは得られたグラフを比較し、「発熱反応では急上昇、吸熱反応では緩やかな低下」といった傾向を見いだした。さらに、クラウド上でグループごとのデータを共有し、他グループの実験結果と照らし合わせて考察を深めた。ICTを活用することで思考を可視化することで、「データに基づいて説明する」という科学的な態度を育むことが可能になった。
・「天体観測シミュレーション」
天体の動きを理解するためにICTを活用した授業を行った例では、天候や時間の制約で実際の観測が難しい中、プラネタリウムソフトを使って星座の動きや月の満ち欠けをシミュレーション。生徒はタブレット上で日時や観測地点を設定し、天体の位置や動きを視覚的に確認した。
この授業では、事前に「なぜ月は形を変えるのか」「星座は季節でどう変わるのか」といった問いを共有し、ICTによる仮想観測を通じて理解を深めた。実際の観測と組み合わせることで、理論と体験が結びつき、生徒の興味関心が高まるという効果があった。
・「電流と磁力の関係×書画カメラ」
コイルに電流を流して磁力を発生させる実験を、書画カメラで拡大表示。生徒はタブレットで動画を撮影し、後で再生しながら考察。実験の瞬間を繰り返し確認でき、理解が深まった。
高校 遠隔観察で広がる探究的な学び
高校理科では、生徒が自ら問いを立て、「観察・実験」を通して仮説を検証し、科学的に説明する力が求められている。その中で、センサーやシミュレーション、データ解析ツールの活用によって、生徒は現象を数量的・モデル的に捉えることが可能になっている。
・「IoTセンサー×オンライン会議システム」
高校段階では、ICTの活用がより高度な科学探究に結び付いている。環境科学の授業と連動した授業では、校庭の植物の成長や気温・湿度の変化をIoTセンサーで継続観測。データはクラウド上に自動送信され、教室の大型ディスプレーにリアルタイムで表示される。
生徒は、日射量や気温の変動と植物の成長速度の関係を分析し、仮説を立てて検証を重ねる。さらに、オンライン会議システムを使って他校ともデータ分析方法や仮説の立て方を互いに共有し、地域を越えた学びの連携を実現している。
また、実験室では遠隔操作ができる顕微鏡を導入し、微生物の観察をオンライン配信する授業も行われている。生徒はスマートフォンやPCから顕微鏡の焦点を調整し、撮影画像を共有する。観察対象を複数人でリアルタイムに確認することで、「見えたこと」と「考えたこと」を同時に記録・比較できる。
・「化学反応の速度×デジタルセンサー」
反応の進行を温度センサーと色変化の動画記録で追跡。得られたデータをグラフ化し、反応速度の違いを数値で比較。ICTによる定量的分析が、論理的思考の育成につながった。
・「顕微鏡画像の撮影+クラウド共有」
果物からDNAを抽出する実験の際、顕微鏡画像の撮影とクラウド共有により、抽出条件や構造の違いに着目し、遺伝の仕組みを探究することができた。
科学的な見方・考え方を育てるICT活用のポイント
これらの実践に共通するのは、ICTを「主体的な探究を支える補助装置」として活用している点だ。「観察・実験」を自ら行い、ICTを使って記録・分析・共有する。そのプロセスの中で、児童生徒は科学的に物事をとらえる力を身に付けていく。
ICT活用のねらいは、「見えない現象を可視化し、再現可能な形で考えること」である。「観察・実験」が単なるイベントで終わらず、得られたデータをもとに論理的思考を深めるサイクルを形成することが、理科教育の新たな方向性といえる。
すなわち、ICTの活用では「見える化」と「共有化」がポイントになるが、そのためにも次のような使い方が求められる。①現象の順序や微細な変化を確認するため、タブレットやPCで 「観察・実験」の様子を記録・拡大・スロー再生などで可視化する。②センサーを利用し、定量的データを収集する場合は、目的を事前に共有し、実験が確認でなく、検証になるようにする。③収集したデータをグラフ化・分析できる、アプリやクラウドツールを効果的に活用する。④収集したデータや検証の結果はクラウド上で共有し、グルーブ間・学年間で比較・議論できる環境にする。
教員による評価・振り返りも大事
その上で、科学的な思考力を育むためには、評価・振り返りの仕方も大事になる。したがって、児童生徒が「観察・実験」の結果をもとに自分の考えを説明できているか。グラフや映像などICTで得た情報を、考察に生かしているか。グループ討議や発表で、他社の意見を踏まえて自分の考えを修正できているかなどについて注目すること。
また、教員自身にとっても、ICTは授業改善の手がかりとなる。データを共有し、児童生徒の思考の過程を分析することで、指導法の振り返りや教材研究を深化することができるからだ。つまり、教員は児童生徒の思考過程を把握し、問いを引き出したり、対話を促したりするフィードバックを行っているか。学習の成果が「科学的に考える力」として次の単元へつながるように指導しているか、といった点に注視して授業を進めていくことが大切になる。