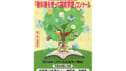「理科」の学習指導要領改訂に向けた改善点
11面記事9月に公表された、中教審「教育課程企画特別部会」による次期学習指導要領改定に向けた「論点整理」では、教科「理科」に関しても具体的な改善方向が示されている。ここでは小・中・高校段階を通じて、理科に盛り込まれた主な改善点を整理した。
1.「中核的な概念・方略」の明確化・構造化
まず理科では、知識・技能のみを伝えるのではなく、「中核的な概念」や「方略(科学的な見方・考え方、探究過程)」を明らかにすることで、学びの深まりや転移可能な理解を重視する方向が示されている。例えば、物理・化学・生物・地学の各領域において、「エネルギー」「粒子」「多様性・共通性」「時間・空間」という視点を共有するなど、領域横断的な見方・考え方を授業設計に反映させることで、生徒が学んだ知識を別な場面でも活用できるようにする。つまり、従来なら実験結果を暗記するだけでよかったが、「なぜそうなるのか」といった概念を理解することが重要になる。
また、学習指導要領そのものを構造化・表形式化・デジタル対応させ、教科・領域・学年がどうつながるかを明示することで、教師が指導設計をしやすくする改善も挙げられている。
2.探究的な学び・実践的活動の強化
理科では、実験・観察・データ分析・考察といった探究的学びをより質高く展開することが求められており、「なぜ」「どうして」「どうするか」を問い続ける学習活動を重視する。これを実現するために、授業時数の弾力化や学校裁量時間(「余白」の創出)によって、探究活動や体験活動などに充てる時間を確保する必要性が指摘されている。
また、特に生命・地球環境分野、科学技術分野との関連など社会とのつながりを意識した学びを展開することで、「生きて働く知識」としての理科を位置づける改善が示されている。
3.多様な子どもたちを包摂する教育課程の実現
理科教育においても、生徒の興味・関心・発達段階・個性・特性(例えば発達障害や外国出身などの背景をもつ子ども)など、多様な学び手を念頭に置いた課題対応が求められている。
論点整理では、教科内容の精選・学年間の系統的流れの見直し・授業時数や学年区分の柔軟化などによって、「誰一人取り残さない理科」への改善が図られるべきとされている。具体的には、「調整授業時数制度」の創設により、各学校や生徒の実態に応じて理科の授業時数や探究活動時間を柔軟に設計できる仕組みが検討されており、多様なニーズに応じる体制づくりが理科にも及んでいる。
4.教科横断・情報活用・デジタル基盤との連携
理科教育も他教科や総合的な学習、探究活動、情報教育との連携が重要視されている。論点整理では、デジタル学習基盤やAIを活用し、理科実験・データ分析・探究活動において、情報活用能力を抜本的に向上させる必要性が挙げられている。例えば、理科においてセンサー・可視化・データ処理を活用する授業の展開や、探究活動でICTを活用した実証学習を促す方向性が含まれており、理科の学びがこれまで以上に「社会・技術とつながる教科」として位置づけられている。
今から、授業実践を
今後、各教科別ワーキンググループが理科の詳細設計を詰め、学校現場ではこの方向性を踏まえて授業実践・カリキュラムマネジメントを検討していくことが求められる。理科を担当する教員としては、これらの改善点を踏まえ、実験設備の活用や探究・ICT統合の授業設計、教材・評価の検討を今のうちから始めることが有効である。