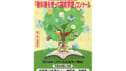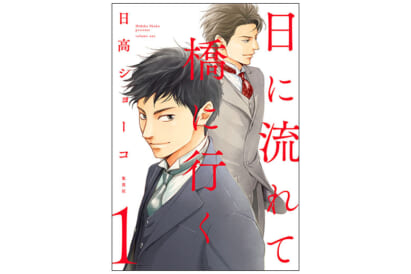学校での集団感染を抑止する、環境衛生機器の活用
10面記事
CO2モニターを使って教室の換気状況を把握する
室内環境を清潔に保つ設備・機器の導入を
冬季は室内の乾燥が進み、学校ではインフルエンザや新型コロナウイルスなど、さまざまな感染症の集団感染リスクが高まる。そこで、今年の傾向を踏まえ、これからの季節に注意したい感染症の動向や、「学びを止めない」ために必要な教室等の環境衛生を向上する設備機器について紹介する。
「環境衛生の質」が子どもの健康を支える
学校は児童生徒が集団生活を営む場所であるため、誰か一人でも感染症に罹患した場合には一気に広がりやすく、教育活動にも大きな影響が生じる。特に冬季はウイルス性疾患の発生率が高まるため、手洗い、マスク、ワクチン接種など基本的な感染対策を徹底して二次感染を防いでいく必要がある。しかし、昨年の冬季もインフルエンザを中心に複数の感染症が同時に流行し、全国で学級閉鎖が相次いだように、人的努力だけでは抑止しきれないのも事実だ。
したがって、文科省では感染拡大防止のための教室の効果的な換気について、補完的な装置も検討し、できる限り1000ppm相当となるよう、二酸化炭素濃度を測定して換気を行うよう求めている。また、そのためには最新の知見に基づいた環境衛生装置の力も借りつつ、持続可能な感染予防に努めていくことが重要になるが、学校の教室におけるCO2モニターやサーキュレーター、HEPAフィルター付空気清浄機の設置状況はいまだ十分とはいえない。
特に、新型コロナウイルスによる活動制限の緩和後は、さまざまな感染症が季節を問わず流行する傾向にあり、学校施設における「環境衛生の質」は児童生徒の健康を支える重要な要素となっている。こうした点からも、室内環境そのものを清潔に保つための設備・機器の導入を加速していく必要がある。
学校の室内環境を守る。
感染症予防に有効な機器・設備
感染症対策の基本は、室内の空気を定期的に入れ替えることが大切になるため、新型コロナウイルスの流行以降、学校施設でも「機械換気設備」の整備が進んだ。これは給気と排気を機械的に行う方式であり、教室内の二酸化炭素濃度を一定以下に保ち、飛沫・エアロゾル感染のリスクを下げる効果がある。
また、整備されていない学校では、窓開けによる換気とサーキュレーターの併用が有効になる。サーキュレーターは空気の循環を促し、部屋の上下温度差を小さくする。とりわけ、冬季は寒さを避けて換気を控える傾向があるため、暖房とサーキュレーターを組み合わせた換気設計が求められるが、CO2モニターで換気状況を「見える化」することで、必要なときに適切な換気を行えるようにしたい。
その際のポイントとしては、①CO2モニターを教室内の見やすい位置(子どもの目線付近)に設置。②数値が目標値を超えたときの教員・児童の行動(例:窓を2つ開ける・サーキュレーターを回す)をクラスルールとして明示。③月次で数値記録をとり、クラス内で「高かった時間帯」「人数が多かった時間帯」を振り返ることで、運用改善に生かす使い方が効果的といえる。ある東京都の専門学校では、Wi―Fi接続可能なCO2センサーを設置し、リアルタイムで測定値を教職員・学生が共有することで安心・安全な学習環境を作り出している。
換気が難しい環境には
換気が難しい環境では、空気清浄機が有効だ。特にHEPA(高性能エアフィルター)を搭載した機器は、ウイルスを含む微小粒子を高い確率で捕集できる。教室の広さに応じた風量を確保し、机や窓際に偏らないよう設置位置を工夫することが重要である。すでに某大手塾では全国校舎に1600台以上の高性能な空気清浄機を設置し、ウイルス・菌の抑制に対応している。
さらに、一部機種では、紫外線照射機能やオゾン低濃度発生機能を組み合わせたタイプも登場している。これらは空気中のウイルス不活化を補助するが、子どもが長時間滞在する教室では安全性を十分に確認した上で運用する必要がある。ただし、フィルターの清掃・交換を怠ると性能が低下し、かえって汚染源になることがあるため注意したい。
CO2モニターやサーキュレーター、HEPAフィルター付空気清浄機などの導入については、「学校等における感染症対策等支援事業」による支援対象としている。また、公立の小中学校における高機能換気設備(全熱交換機等)の導入についても、「学校施設環境改善交付金」の支援対象となっている。学校として検討する際には、設備・機器そのものの仕様だけでなく、運用(設置位置・保守計画・児童生徒への説明)・教育的活用(児童自身が関わる仕組み)・効果測定(数値記録・傾向分析)を併せて検討することが重要である。
接触機会を減らす備え
学校での感染拡大の一因には「共用物への接触」があることから、接触機会を減らす備えも大切になる。手洗い場の蛇口を自動水栓化することは、接触感染を防ぐ有効な手段となることから、老朽化した学校施設の改修とあわせて導入が進められている。非接触型センサーで手をかざすだけで水が出る仕組みは、子どもにも使いやすく、節水効果も高い。石けんディスペンサーも自動式を採用すれば、衛生性がさらに向上する。
手洗い場そのものの数と配置も重要になる。休み時間に児童が集中しないよう、廊下や教室近くへの分散配置が望ましい。衛生陶器メーカーの調査では、従来型手洗い器から自動水栓タイプに更新した学校で、インフルエンザ欠席率が低下した例も報告されている。
トイレは感染経路が集中しやすい場所であるため、近年では学校トイレの洋式化改修に伴い、非接触化(自動洗浄、センサー式照明、ノンタッチドア)と換気の強化が進められている。特に自動洗浄便器と換気ファンの常時稼働により、飛沫・臭気の拡散を抑える効果が確認されている。
また、清掃のしやすさも感染対策に直結する。床や壁の素材を防汚性・抗菌性の高いものに更新することや、便座・ノブなど手が触れる部分の材質を抗菌仕様にすることも有効だ。加えて、トイレ前に手洗い場を設け、児童が自然に手を洗う動線を整える設計にも配慮したい。
日常的に感染リスクを減らす
最近では、机やドアノブ、壁面パネルなどに抗菌・抗ウイルス加工を施した建材が普及している。銅イオンや銀イオンを利用したコーティングは、ウイルスの不活化効果があるとされる。この種の設備は、感染症予防の即効性は薄いものの、日常的に接触感染リスクを減らす対策として有効になる。導入する際は、コーティングの寿命やメンテナンスの周期を確認するとともに、抗菌材だから消毒不要ではないことを踏まえて、清掃・消毒方法にも留意することが重要になる。
さらに、冬季の乾燥は、インフルエンザやRSウイルスなどの感染リスクを高める要因になっているため、教室の湿度を40~60%にして乾燥を防ぎ、粘膜防御を保つことが望ましい。
加湿器を使用する場合は、定期的な清掃と水の交換を徹底することが前提になる。こうした不便さを解消し、効率的な加湿を実現するために、校内の空調システムに加湿機能を組み込む方式や、美観性に優れた天井埋め込み式の加湿器を導入することが、今やスタンダードになっている。湿度と温度を自動制御することで、子どもが快適に過ごせる学習環境を維持しつつ、感染予防にも寄与することができるからだ。
教室以外の換気対策やICTによる「健康状態管理」も
教室以外にも、体育館・更衣室・多目的ホールといった「密になりやすい」「複数学年が交錯する」「換気しにくい」場面において、換気・空気清浄・空気循環の強化を行う必要がある。例えば、体育館に大型換気扇や吸排気ダクトを設置し、授業や部活動時に常時換気を実施。更衣室では脱衣後・着替え中の密集を避けるため、パーテーション+空気清浄機+換気扇の併用を行うなどの工夫が求められる。
近年、学校現場では感染症の流行や体調不良の早期把握、欠席者対応の迅速化が求められており、校務支援システムやICTアプリを活用した「児童生徒の健康状態を可視化・管理」も進みつつある。これまで紙の健康観察票や担任の個別記録に依存していた健康情報を、デジタル化して一元管理することで教職員間での共有が容易になり、教育活動の安全性と効率性が向上している。
具体的には、朝の健康チェックを児童生徒または保護者が端末やスマートフォンから入力し、出欠情報と連動して校務支援システム上に自動集約される仕組みである。体温、咳・喉の痛み、頭痛、倦怠感などの症状が入力されると、担任や養護教諭の画面にアラートが表示され、体調不良者の早期対応が可能となる。
また、感染症の集団発生傾向を分析し、学年やクラスごとの罹患状況をグラフ化する機能を備えるシステムも増えている。これらのデータを蓄積・分析することで、予防的な措置(給食後の手洗い徹底・部活動の時間調整等)につなげていくこともできる。