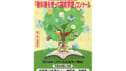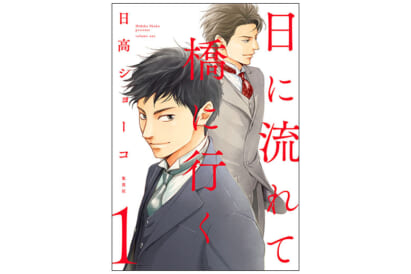今年の冬、学校で注意したい感染症と対策
11面記事
学校閉鎖になるような感染拡大は未然に阻止したい
インフルエンザ、マイコプラズマ肺炎、ノロウイルスなど
近年、地球温暖化などの影響により季節の移り変わりが不明瞭になりつつある。その結果、これまで冬に流行のピークを迎えていた感染症が、季節を問わず発生する傾向が見られるようになっている。こうした状況を踏まえ、これからの時期に注意が必要な感染症と、学校現場で実践できる予防対策について紹介する。
季節を問わず流行する傾向に
今年の春以降、日本国内の感染症情勢は「RSウイルスなど、一部の季節病が季節的ピークをずらして出現する」「消化器系ウイルスの局地的な多発」という特徴を示している。呼吸器系では、RSウイルスの流行期が従来の冬型から変化し、夏季~秋に高い流行を示す地域があった。加えて、半年余りで昨年の10倍となる感染者を出したのが、激しい咳が長期間続く「百日咳」だ。かつては子どもの病気というイメージがあったが、近年は大人の感染例も増加している。初期の症状は風邪の症状に近く、高熱が出ていないため、学校に登校することで感染を拡大する要因になった。
また、ノロウイルスなどを含むウイルス性胃腸炎が早期から増加し、特に保育所・幼稚園・小学校での集団発生が散見された。例えば、仙台市では2月に市立小学校で感染性胃腸炎の集団感染が疑われる事例が発生し、児童と職員含めて108名が発症した。感染拡大は数日間で急速に進行し、学校は学級・学年閉鎖を余儀なくされた。しかも、例年なら減少する3月~5月にかけても高い報告数を記録した地域があり、季節に関わらず流行する傾向が見られている。
一方で、新型コロナウイルスは落ち着きを見せつつも散発的な感染が続き、変異株の監視や医療体制の確保などに対し、引き続き警戒が必要になっている。このような状況から、学校現場では例年と異なる感染症の動きが見られていることに注視しなければならない。

人的努力だけでなく、感染拡大を防ぐための備えが必要だ
インフルエンザが1カ月早く流行
では、今年の冬に注意したい感染症は何になるのか。昨年は、インフルエンザが冬を待たずに流行し、東京都では9月中旬までに小中高校合わせて200校以上が学級閉鎖になるなど、翌年1月末までに900万人以上が感染した。
年末からはインフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、マイコプラズマ肺炎の3つが同時期に流行し、「複合感染(トリプル感染)」が社会問題化。子どもたちが何度も感染を繰り返す感染症ドミノを引き起こすことで、学級閉鎖や臨時休校が相次いだ。また、治療薬や検査キットの不足も深刻化し、不安をあおったのも記憶に新しい。
その中で、昨シーズンA型が流行したインフルエンザは、今年の冬はB型が流行することが予想されていた。だが、9月に入るとA型インフルエンザの感染者数が増え出し、青森県や福岡・北九州市などで学級閉鎖になる小中学校が現れるようになった。東京都も9月末には流行シーズンに入ったと発表するなど、昨年同時期と比べても、全国的に1カ月早い感染拡大を引き起こしており、しばらくはA型が流行していきそうだ。
こうした早期に流行している原因としては、猛暑による無睡眠不足などにより免疫力が低下していることや、エアコンの使用が続いて換気がおろそかになったことが挙げられている。また、インバウンドの増加による病原菌の持ち込みが、季節外れの流行と関係している可能性もあるという。このため、毎年10月頃から始まるインフルエンザのワクチン接種を前倒した病院も多くなった。
一方、インフルエンザB型は、A型よりも遅れて流行することが多いため、年が明けてから本格的に流行する恐れもある。感染力はA型ほど強くないが、特に子どもや若年層での感染が目立つ傾向にあるため、今後の感染状況に注意したい。
ワクチン接種と早期受診を促進する
冬季に増加する傾向にある新型コロナウイルスに加え、マイコプラズマ肺炎や百日咳などさまざまな感染症が同時に流行する可能性が指摘されている。昨年、過去最大級の流行となったマイコプラズマ肺炎は、すでに昨年と同様の感染状況の推移を見せている。症状としては、発熱や全身の倦怠感、頭痛、咳などで、咳は熱が下がった後も1ヶ月近くにわたって続くのが特徴。感染者の多くは気管支炎程度の軽い症状で済むが、肺炎を引き起こして重症化する場合もある。また、インフルエンザと見分けがつきにくく、同時感染するケースも見られる。
新型コロナウイルスは、既存のオミクロン系統からさらなる変異を経た株が世界的にも報告されており、国内でも流入・優勢化する可能性が想定されている。このため、従来の免疫(感染・ワクチン接種)だけでは「感染そのものを防ぐ」ことが難しい状況になっている。ただし、これらの感染症は、ワクチン接種や日常的な衛生習慣によって予防可能なものが多く、個人の意識と社会全体の協力が重要になるのは間違いない。
感染性胃腸炎は、脱水症にも注意

感染性胃腸炎は、おう吐や下痢が数日続くため、脱水症にも注意する
さらに、冬季にピークを迎えるのが感染性胃腸炎だ。感染性胃腸炎は、患者の排せつ物や吐しゃ物、ウイルスに汚染された食品などを通して感染し、おう吐や下痢、発熱などの症状を引き起こす。特にノロウイルスは極めて感染力が強く、わずかなウイルス量でも発症するため、学校での集団感染を引き起こしやすい。しかも、今年は3月にピークを迎えた後も継続的に発生するなど過去最多の水準で推移しており、各地の保育施設などで集団感染も相次いでいる。
こうしたことからも大切になるのが、早期の濃厚接触者特定と環境消毒だ。特に、学校内で子どもがおう吐した場合は、二次感染を防ぐため、「汚物処理キット」などを使って迅速かつ安全に処理しなければならない。
また、感染性胃腸炎に罹患すると、おう吐や下痢が数日間続く場合があり、体内の水分や電解質(塩分など)が大量に失われる。その結果、脱水症を起こし、場合によっては命に関わる重症化に至ることもある。脱水のサインとして、口の渇き、尿量減少、涙が出ない、ぐったりしているなどが見られた場合は、早急に医療機関を受診することが必要である。その中で、応急的な対処として有効なのが、学校でも保健室等への常備が進んでいる経口補水液だ。
経口補水液は、水分とともにナトリウムやカリウムなどの電解質、糖分をバランスよく含んでおり、体内への吸収が速い点が特徴。摂取の際は、一度に多量を飲ませるとおう吐を誘発することがあるため、少量ずつ、頻回に与えることが原則である。目安としては、1回あたりスプーン1杯から始め、5~10分おきに徐々に量を増やす。特におう吐直後は、胃腸が刺激に弱いため、30分程度は無理に飲ませず、落ち着いてから再開するようにしたい。
学校で実施したい予防対策
冬季の感染拡大を防ぐため、学校で講じるべき具体的な対策としては、次のようなものが挙げられる。
①ワクチン接種の促進:学内周知(保護者向け文書、学級配信)でインフルエンザワクチンの接種推奨と接種時期(例:11~12月まで)を明示する。重症化リスクの高い子ども・教職員は、早期接種を促す。
②体調不良時の出席停止運用:発熱・おう吐・下痢などの症状がある子どもは登校不可とし、症状消失後に登校許可(医師判断または指定日数経過)を明示する。学校行事の出欠基準を事前に定め、保護者と共有する。
③手洗い・咳エチケット・環境消毒:こまめな手洗い(石鹸による30秒程度)と、共用物の定期的な消毒(特に給食関連、ドアノブ、手すり、トイレ等)を徹底する。ノロウイルス対策では次亜塩素酸ナトリウムによる消毒が有効とされるため、消毒手順を整備する。
④換気の徹底と教室配置の工夫:定期的な窓開けや機械換気の運用を継続する。十分な換気が難しい場合は、授業形式の工夫(屋外活動、短時間授業)や児童間距離の確保を検討する。WHO等も感染予防として換気の重要性を強調している。
そのほか、感染時の連絡・保健室運用強化:発症者発生時の校内連絡フロー、保健所への報告基準、保健室での隔離手順を明確化する。保健師や医療連携先の確保、発熱時一時隔離スペースの準備が望ましい。教職員の健康管理と代替体制:教職員の発症による欠勤に備え、代替授業計画やICT活用(オンライン配信や課題提示)を日常的に整備しておく。保護者・地域への情報発信:地域の医療・保健所と連携し、流行状況や登校基準をタイムリーに発信することなどが重要になる。
学校は児童生徒の健康を守る「最前線」
感染症の流行は季節性の枠組みが変容しており、従来の“冬だけ警戒”では不十分になっている。学校は児童生徒の健康を守る「最前線」であり、日常的な感染防止活動(手洗い、換気、症状時の登校制限)を当たり前に続けることが最も有効な対策になる。加えて、ワクチン接種や保健所・医療機関との連携体制を平常時から整備することが、学校活動の継続性を支える要になるのだ。
医薬品不足が子どもたちに及ぼす影響
感染症の流行期に備えて
2025年現在、日本では医療用医薬品の供給不足が深刻化している。特にジェネリック医薬品の製造停止や出荷調整が相次ぎ、解熱剤、咳止め、抗生剤など、感染症治療に不可欠な薬剤が入手困難な状況が続いている。こうした薬剤不足は、これからの季節に増加が予想されるインフルエンザや新型コロナウイルス、RSウイルスなどの感染症に対して、子どもたちの健康管理に大きな影響を及ぼす可能性がある。
まず、薬剤不足によって最も懸念されるのは、発症後の初期対応の遅れだ。子どもは体力や免疫力が成人に比べて弱く、感染症が重症化しやすい傾向がある。例えば、インフルエンザに罹患した場合、抗ウイルス薬の投与が遅れることで高熱が長引き、脳症や肺炎などの合併症リスクが高まる。また、咳止めや去痰剤が不足すれば、呼吸器症状が悪化し、喘息や気管支炎を併発する可能性もある。
さらに、医薬品不足は医療機関の診療体制にも影響を及ぼす。処方薬が確保できない場合、医師は代替薬を選択する必要があるが、子どもに適した用量や剤形がないケースも多く、治療の選択肢が限られる。特に乳幼児やアレルギー体質の児童に対しては、薬剤の変更が困難であり、治療の質が低下する懸念がある。
学校現場においても、薬剤不足は感染拡大防止の取り組みに影響を与える。発症児童の早期治療が難しくなることで、登校中の感染拡大リスクが高まり、学級閉鎖や臨時休校の判断が早まる可能性がある。また、保護者が市販薬を求めて複数の薬局を回るなど、家庭の負担も増加している。
このような状況下で求められるのは、学校・家庭・医療機関の連携による予防対策の強化である。ワクチン接種の促進、手洗い・うがいの徹底、校内の換気や消毒の継続的な実施は、感染症の発症自体を減らす有効な手段である。また、学校は保護者に対して、薬剤不足の現状や受診時の注意点を周知し、発症時の対応を事前に共有しておくことが重要である。
医薬品の安定供給は、子どもたちの健康と教育の継続に直結する課題である。今後の感染症流行期に備え、地域全体での情報共有と予防意識の向上が求められている。