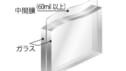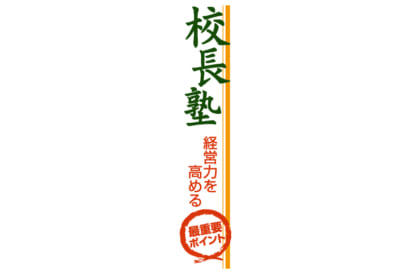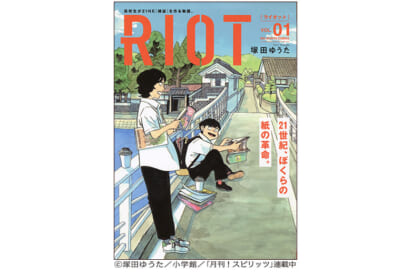理科で深める海洋リテラシー 単元の学習内容を発展的に活用した「海洋教育」の実践
7面記事
地中をモデル化した容器に泥水を入れ、ろ過する実験
四方を海に囲まれ、多くの恩恵を受けてきた日本において、海洋リテラシーは持続可能な社会を支える重要な基盤だ。しかし、小学校理科で海洋教育を実践するには、既存の単元内容と海の事象をどのように結びつけるかが課題となる。そこで、海洋教育指導資料『理科の学びを海につなぐ』(発行:大日本図書)を手がかりに、理科の学習内容と効果的に関連付けた小学校2校の授業を紹介する。
東京学芸大学附属小金井小学校
第4学年 雨水のゆくえ 河瀬正和 教諭
生活で使う水から海とのつながりを想起する

地層を確認する児童
◆雨水はどう海へ向かうのか
4年理科の単元「雨水のゆくえ」では、雨が地面にしみ込み、地下を通って川や海へと戻る流れを学ぶ。河瀬正和教諭による本単元最後の授業では、社会科で学んだ「水の循環」を振り返らせながら、山の土壌が果たす自然ろ過の働きと、都市部で水がろ過されず海に流れ込む状況を対比させ、児童が海への視点を持てるよう導くのがねらいである。
授業は、雨水由来の地下水と泥水の2種類を用意し、「どのような共通点と違いがあるか」を問題とした比較から始まった。児童は班ごとに重さや蒸発後の残留物の有無を調べ、「同じ量なのに泥水のほうが重い」「地下水は蒸発しても何も残らないが、泥水には土が残る」などの気づきを次々に共有し始めた。
続いて、土や砂を用いて作った「山の地層モデル」2セットにそれぞれの水を流し込み、自然のろ過作用を再現する実験へと発展した。その中の、目盛りがついているピストンを使えば、水の量や土の量を調整して調べられるというアイデアは児童から生まれたものであるという。
児童は透明度や流れ方の違いを丁寧に観察し、タブレットに結論を整理していく。河瀬教諭はクラウドで児童の記録を確認しながら、足りない点をアドバイスしたりヒントを与えたりする役割に徹していた。
◆自然の浄化プロセスを理解する
ろ過後の水を比較した結果、「泥水はろ過に時間がかかった」「山の地層を通すと、どちらもきれいな水になった」といった点が確認された。また、「泥水には土や砂が含まれるが、地下水は混ざり物が少ない」「ろ過しても地下水のほうがより透明だった」などの相違点も明確になり、自然の浄化プロセスへの理解が深まった。
さらに、地層の粒径の並べ方で成功と失敗が分かれた班もあり、物事を比較する際は条件をそろえる重要性も実感する機会となった。
授業の終盤、河瀬教諭は「山には土や砂、石が幾層にも重なり、地下水を自然に浄化しています。しかし都市部では、その層が十分でないまま海に流れる水もあります。皆さんの生活の水や雨水が、どのように海へ向かうのか想像してみましょう」と語りかけ、生活と海のつながり、そして環境への問題意識を促した。
今回の授業は、身近な理科の学びを、自然と海への理解へとつなげる取り組みであった。来年度は、学校の伝統である遠泳活動とも結び付け、自然との共生へ学びを広げていく意向である。
第6学年 水よう液の性質 蒲生 友作 教諭
「体験した記憶」を活かし、海水成分の違いを考察

リトマス紙で液性を調べる
◆海水と食塩水は何が違う?
6年理科の単元「水よう液の性質」と海洋教育を関連付けた蒲生友作教諭の授業では、学校の遠泳活動で勝浦の海を体験した子どもたちが、その海を科学的に捉え直し、場所による塩分濃度の違いや不純物などに気づかせることをねらいとした。
本時の問題は「食塩水と海水は何が違うのだろうか」だ。用意されたサンプルは3つ。勝浦の海水、東京湾のお台場の海水、そして市販の食塩から作った食塩水である。授業冒頭、蒲生教諭が「実はお台場に行って水を汲んできました」と語ると、教室にはどよめきが。「場所によって塩の量は違うの?」「海水には何が入っているのだろう?」といった疑問が自然に生まれ、学習への期待感を高める役割を果たした。
実験の方法は、班ごとに自主的に考えて決めるスタイルである。リトマス紙による液性の確認、海水を蒸発させて残る物質の観察、顕微鏡での結晶・不純物の観察など、これまでの理科学習で身につけた技能を自ら選び、組み合わせていく姿が見られた。


3種類の水溶液を加熱して蒸発させ、残った固形物を観察する
◆理科の知識から海につなげる
実験後、各班は記録用スライドにまとめ、気づきを共有した。「蒸発させると食塩水が、一番たくさん結晶が残った」「勝浦とお台場で塩の量が違うかもしれない」「海水には”変なもの“が混ざっていた」など。児童が言う”変なもの“とは、細かな沈殿物や不純物だ。顕微鏡で観察した班もあり、海水の複雑な成分に気づくきっかけとなった。
また、いくつかの班からは液性(pH)の違いに着目した報告があった。海水の中にも酸性やアルカリ性の幅があることに驚く姿が見られ、蒲生教諭は「次回は酸性・中性・アルカリ性を全体で整理し、なぜ違いが出るのか掘り下げたい」と話す。次時の学びを見通せる構成が、理解の深化につながっている。
今回の授業で特徴的なのは、勝浦の海を「体験した記憶」として持つ児童が、理科の実験でそれを再検討できる点だった。「遠泳で入ったあの海の水」という実感が、科学的探究のモチベーションを高めている。さらに、東京湾の海水を比較対象として扱うことで、海の環境が地域によって異なるといった視点も広がる。
蒲生教諭は「習った理科の知識から海につなげるという点を最も大切にした」と語る。海水の成分の違いという理科の学びを通じて、子どもたちは海をより立体的に捉えて、考える機会を得た。
学校法人立教学院 立教小学校
第3学年 カニは昆虫といえるのか 小林 靖隆 教諭
海の生物の観察を通して、昆虫との違いを理解する

実物のカニを見せると、子どもたちの関心は一気に高まった
3年理科「昆虫の育ち方・植物の育ち方」の学習内容を踏まえ、小林靖隆教諭は「カニは昆虫といえるのか」をテーマに、観察と理由付けにもとづく授業を展開した。
昆虫の基本構造(足6本、頭・胸・腹、外骨格、羽など)を整理した上で、海の生物との共通点や差異点から昆虫の定義について理解を深めるのが本時のねらいである。まず、児童に昆虫の特徴を振り返らせ、カニが昆虫に分類されるかどうかを予想させた。
予想の発表では、大半の児童が「カニの足は8本」であることを根拠に、昆虫ではないと主張した。その一方で、「飛べない」「食べられる」といった、分類根拠としては不十分な理由を挙げる児童もいた。小林教諭は、飛翔能力や食文化は分類とは直結しないと助言し、あらためて定義にもとづく観察の必要性を示した。
ここで小林教諭は、事前に用意したカニを取り出した。実物のカニを前に、児童の関心は一気に高まる。色や形、動きの細部に目を向け、定規で大きさを測ったり、足の数や体の構造を丁寧に観察したりした。タブレットで拡大撮影し、気づいた点を仲間と共有する児童もおり、教室は活気に包まれた。

ミルソー(透明観察そう)に入れたカニを観察
◆比較から生まれる発見
再度の発表では、「足が8本である」「頭・胸・腹の区別がなく、一体化している」などの所見が多く挙がった。これらは昆虫の条件(足6本・三分節)と明確に異なるため、クラス全体で「カニは昆虫ではない」との結論に至った。
授業の終盤にはフナムシの画像を提示し、さらに箱からイセエビの実物を取り出して驚かせる演出も披露。その上で、「海にはこうした生き物がたくさんいるよ」と投げかけ、海には多様な生物が存在することを示し、生物への関心をさらに広げて授業を締めくくった。
小林教諭は今日の授業を振り返り、「昆虫の学習にとどまらず、カニとの比較によって体のつくりと形の意味を考えさせることができた」と手ごたえを口にする。生きた教材を用いたことが興味関心を大きく引き出し、「頭・胸・腹がくっついていることに気づいた」「カニの腹の模様を見つけられてうれしかった」といった児童の声にもつながったという。
同校では5年生でグローバルエクスカーションという四万十川や屋久島などへの自然体験学習が予定されている。本授業は、こうした今後の学びにもつながる海洋教育への導入として、大きな意義をもつ取り組みである。
日常生活や社会の事物・現象と結びつける理科の「深い学び」
有本 淳 氏 国立教育政策研究所 教育課程調査官・学力調査官

次期学習指導要領の改定では、これまで以上に「主体的・対話的で深い学び」の実装が重視されるようになります。中でもクローズアップされている「深い学び」とは、身につけた知識を日常生活や社会の場面で活用できるようにすることであり、理科でもその視点が重要になります。したがって、学年や単元を超えた横断的な学び、探究的な学びへと展開していくことも望まれているところです。
そうした点からも、発展的な扱いとして、理科教育と海洋教育とを連携させることは、子どもたちの「深い学び」を促す上で非常に効果的であると考えます。例えば、今回の授業(東京学芸大学附属小金井小学校6年「水溶液の性質」)で行った”食塩水と海水の比較“は、5年「ものの溶け方」などでこれまで学んだ内容を活用しつつ、水溶液の性質と日常生活や社会の事物・現象と結びつけるために理科の学びに海という視点を取り入れた良い実践だと感じました。
しかも、授業では子どもたちが自分の判断で「観察・実験」の方法を選択して問題解決に取り組み、これまでに身につけた資質・能力を活かしていた点が評価できます。さらに、析出物の結晶の違いや食塩水と海水の匂いに気づいた児童がいたように、諸感覚を使って観察することは「深い学び」につながる大事な要素になると再認識しました。
「理科の学びを海につなぐ」の監修者・著作者から 海とともに生きてきた日本
日置 光久 氏 (公財)笹川平和財団海洋政策研究所 客員研究員(本指導書監修)

本書は、これまでの「海洋教育指導資料」とは異なり、タイトルの通り「理科の学びを海につなぐ」ことを目的に制作した、新しいタイプの指導資料です。本書では、学習指導要領に基づく小学校理科の学習を基盤として、海の自然現象や環境問題への理解を深められるように工夫された11の単元が具体的に示されています。1つの単元は8ページで構成され、前半4ページでは通常の理科の学習の内容とその展開が中心として扱われ、後半4ページではその学習の海への発展、生活とのつながり、環境問題への広がりなど、授業を「海」へ橋渡しする内容が扱われています。
とりわけ、各単元の8ページ目で扱われている「海洋リテラシー」のページは、世界的に普及が進められている“OceanLiteracy”との関係から本単元の内容とのつながりについて考察しており、これは本書の一つの特徴だと考えております。
日本は海に囲まれており、海に大きな影響を受け歴史や文化を育んできた国です。しかし近代以降、安全面の懸念や価値観の変化などから、子どもたちが海から遠ざかってきています。地球温暖化や海洋環境の悪化など、現代の諸課題を考える上で、海を科学的に理解し、海から地球全体のつながりを考える力を子どもたちに育成することは、一層重要になってきています。先生方の理科の授業づくりが、「海」という視点を加えることにより、一層の広がりと深まりをもってくるという実感を、本書は感じさせてくれるものと信じています。
自然に海への関心が広がる構成
三井 寿哉 氏 帝京平成大学人文社会学部 准教授(本指導書編著)

本書を執筆するにあたり、最も重視したのは「理科の授業を通して、子どもたちをどこまで海に近づけられるか」という視点でした。普段から海との関わりが少ない子どもたちに意識を向けさせることは容易ではありませんが、授業の導入や展開の工夫次第で海との関連付けは十分に可能だと考えます。そのため海の学びを景初から強調するのではなく、理科の内容を基盤とし、そこから自然に海への関心が広がる構成を大切にしました。
今回の理科授業では、本書に対応した単元の中で海とのつながりを示そうとする工夫が見られ、子どもたちが海を意識して学ぶ場面もありました。一方で、海に関する自分なりの疑問や課題を深めていく段階にはまだ至っておらず、今後の課題として受け止めています。
こうした点を踏まえ、授業の最初に海との関連を示しておくことで、子どもたちが予想を立てやすくなり、学習の見通しも持ちやすくなるのではないかとも感じました。先生方には、本書の中で「これならできそう」と思う部分だけを取り入れてもよく、理科が得意な先生であれば、発展的な実験に広げられる魅力もあります。特に海から離れた地域の学校が、授業の中で少しでも実践してもらえたら嬉しいですね。