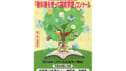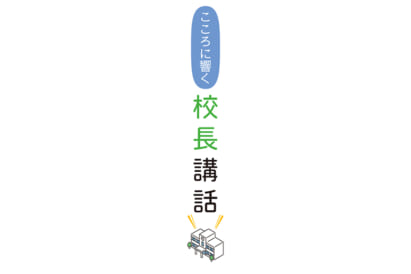知らず知らずに発症する「梅雨型熱中症」に注意!
9面記事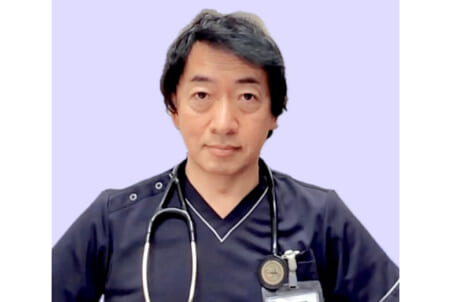
埼玉慈恵病院 藤永 剛 氏
梅雨の時期特有の「湿度の高さ」が引き金に
近年の気温上昇に伴い、梅雨の時期から熱中症で搬送される患者が多くなっている―。そう警鐘を鳴らすのが、「日本一暑いまち」として知られる熊谷市で25年以上にわたり、熱中症の救急患者を診療してきた埼玉慈恵病院の藤永剛副院長だ。そこで、この「梅雨型熱中症」が起こるメカニズムや予防法について解説してもらった。
室内で発症することが多く、教室でも注意が必要
以前は真夏の病気と思われていた熱中症ですが、現在では4月から10月頃まで患者さんの救急搬送があります。中でも、近年増えているのが「梅雨型熱中症」です。
「梅雨型熱中症」とは、梅雨の時期の高温多湿な環境で発症する熱中症です。これには、この季節特有の「湿度の高さ」が大きく関与しています。
(1)汗が蒸発しにくいため熱がこもり「体温が上昇」。
(2)体温を下げるため発汗し「脱水」傾向に。
(3)多湿だと口渇を感じにくいため、水分補給がおろそかになることで「脱水」が進行。体温調節機能が低下し、さらに「体温が上昇」する。
つまり、「体温上昇」と「脱水」が組み合わさって「熱中症」を引き起こすのです。
しかも、まだ体が暑さに慣れていない時期であることや、「真夏じゃないから」といった油断も加わることによって、より熱中症を起こしやすくなります。厳しい暑熱環境下で起こる熱中症とは異なり、知らず知らずに発症し、じわじわ進行するのが特徴なため、周囲の人はもちろん本人も熱中症とすぐには気づかない場合があります。
室内で発症することが多く、学校の教室でも注意が必要です。先生方にはこうしたタイプの熱中症もあることを知ってもらい、湿度が高いときには迷わずエアコンを稼働させ、サーキュレーターなどで十分な換気を図るとともに、子どもたちに水分補給を促すことが大切になります。
経口補水液の活用方法
一方、年々猛暑が厳しくなる中で、学校の運動部などでも経口補水液を活用するようになっていると聞いています。確かに電解質を効率的に補給できる経口補水液は、脱水症や熱中症の対処に有用ですが、摂取の仕方を間違うと塩分過多になってしまうため正しい知識が必要です。
経口補水液は脱水症や激しい運動後、熱中症の疑いがあるときに使用するもので、普段の水分補給(水やお茶がわり)には適していません。したがって、学校においては熱中症や脱水症の生徒のために備えておくこと、体育や部活動での運動中に熱中症が疑われる症状(めまい、立ちくらみ、筋肉痛など)があった際に摂取することが大事になります。ただし、症状が重篤でうまく飲水できなかったり意識がなくなったりした場合は、誤嚥(ごえん)の可能性があるため無理に飲ませることは危険です。このような場合は、速やかに医療機関を受診させてください。
自ら熱中症予防の行動がとれる子どもに
梅雨の時期は湿度が高く気候も変化しやすいため、ただでさえ子どもたちが体調を崩しやすい時期です。しかも、その先にはもっと暑い夏が待ち構えています。子どもたちの健康と命を守るため、学校の先生方には熱中症に対する正しい知識を得て実践し、それを子どもたちに教えていただきたい。そして、自ら熱中症予防の行動をとる習慣を身に付けて欲しいと期待しています。