サトー先生の「きょういく日めくり」~きょうも楽しく学校へ行くために~【第31回】
NEWS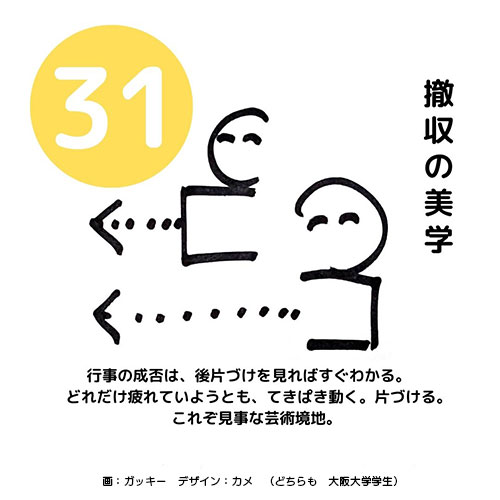
撤収の美学
「行事やイベントの成功不成功は、その後片づけを見ればすぐわかる。成功したクラスは、どれだけ疲れていようとも見事なまでにてきぱき動き、片づけが素早い。これぞ、『撤収の美学』という」
研究会の盟友、N先生の持論が、これ。
なるほど。文化祭終了後、教室に行くと、さっきまで壁面が見えないほどだった装飾品が、見事に跡形もなくなっていることに何度か驚かされた。確かにそのクラスの企画は大成功で、皆、いい顔してたよなあ。
以来、「撤収の美学」ということばはぼくの中にストンと落ちている。
いっぽうで、ぼくは、別の意の「撤収の美学」も何度か経験している。
最初バラバラだったクラスが、皆で文化祭を取り組むなかで一致団結─ドラマではよくある光景だが、現実はなかなかそうはいかない。皆の力が合わされば合わさるほど、仲間に入りきれない人が必ず現れ、関係が悪くなってしまう。
その点、廃材利用の巨大壁画や本格演劇などの「巨大企画」に取り組んだとき、準備段階で出遅れた人が、後片づけ=撤収時に大活躍することがある。
かつてペットボトル数千個で体育館の壁一面に壁画をつくったクラスで、途中、部活を調整できず作業に入れなかったSくんが、撤収時、疲れて腰の重いクラスメートたちを横目に、「まかせとけ」とばかりに片づけ作業を引っ張った。
「いいよ。今まで充分休ませてもらったから」
Sくんの姿に、クラスのメンバーたちが再奮起、あっと言う間に撤収終了。
「やっとぼくもクラスの一員になれました」
Sくんの笑顔がいい。これぞ「協働」のもつ力、もう1つの『撤収の美学』。
なかなかたどりつけない場所にある連載ながら、7ヶ月の長きに渡りご愛読いただきありがとうございました。
いつか本当に“日めくり”となり、出勤前のユウウツな朝に一歩踏み出す助けになれば、と夢見ています。
戦後80年にちなみ、今夏6月にはおまかせHR研究会の仲間たちと『全国平和スポットへのいざない』(かもがわ出版)という書籍を刊行します。
次回はぜひそちらでお会いしましょう……とか、くどくど言わないのが、“撤収の美学”。
きょうも明日も元気に学校へ!
佐藤功(さとう・いさお。大阪大学人間科学研究科元教授)
大阪府立高校教員として33年。酒と温泉と生徒ワイワイ……「生涯現場の一担任」のはずが、生徒や保護者とのわちゃわちゃ大好きを見込まれ、気がついたら大阪大学教職担当初代教授(人間科学研究科所属)。教職志望の学生たちと地域活動やら探究活動やら、日本全国を駆けまわり、現職は「一般社団法人NEOのむら」理事。最近、「旅行業務主任」の資格も取ったらしい。著書に『教室の裏ワザ100連発』『気がついたらボランティア』(学事出版)『はじめてつくる「探究」の授業(編著)』(大阪大学出版会)など。「おまかせHR研究会」主宰。


