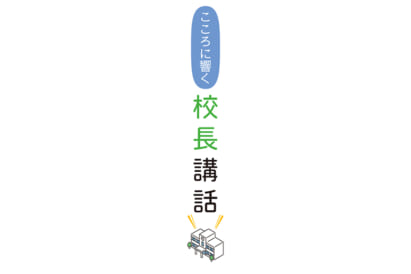使いやすく、分かりやすい指導要領へ 記述をスリム化・教育課程、柔軟に
8面記事
奈須正裕・教育課程部会長の下、9日に専門部会の設置を決めた
中央教育審議会で、次期学習指導要領に向けた検討が1月から進んでいる。「主体的・対話的で深い学び」による授業改善を目指した現在の学習指導要領から、どう変わるのか。文科省では、各教科の目標や内容の構造化を進め、学びの質を高めると同時に、教育課程の実施に伴う教員の負担軽減も両立させたい考えだ。
今回の改訂でまず強調されたのは学校現場にとっての「使いやすさ」や「分かりやすさ」をどう高めるかだ。
現在の学習指導要領は、育成を目指す資質・能力として「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「学びに向かう力・人間性等」の三つの柱を設定。各教科の目標・内容もそれに基づいて整理した。
ただ、中教審の特別部会では、そうした構造によって知識・技能の深まりや、資質・能力を一体的に育成することのイメージを持ちにくくなっていると課題を指摘。改善の方向性として、教科の目標・内容を「中核的な概念」を中心に構造化することとした他、「知識・技能」と「中核的な概念」との関係を表形式で示して記述もスリム化することなどを提案した。
数学を例に取れば「比例・反比例の理解」と「関数を使うことにより未知の状況を予測できる」こととの関係などがそれに当たるという。
小・中学校の教育課程編成の柔軟化も促す。不登校や日本語指導、学習の遅れなどへの対応が求められる中、柔軟な教育を実施できるように、教科間で一定の幅を上限に授業時数を振り替える時数調整の制度を導入する。その中で子どもの課題に応じた教科を開設したり、教員の研究活動に充てたりできる「裁量的な時間」(仮称)をつくることを提案した。現在の特例校制度の利用校が増加していることを受けて、特例の枠を外し、学校の判断での実施を認める。特例校では振り替えの上限は各教科の授業時数の1割。新たな時数調整の制度でこれを増やすのかどうかは今後の焦点の一つだ。
各教科の改訂は専門部会で検討されることになるが、デジタル化が急速に進展する中、情報活用能力については特別部会で事前に取り上げて方向性が示された。文科省の提案では、中学校の「技術・家庭科」を二つの教科に分割し、新たな技術科では全体を通じて情報技術に関わる内容や生成AIの仕組みなどを扱うこととしている。それとともに小中高を通じた探究的な学びの質も高める考えだ。
学習評価見直し教員負担軽減
指導の改善と教員の負担軽減を図るため、学習評価の在り方も見直す。
現在の3観点のうち「主体的に学習に取り組む態度」(学習態度)は評定には反映せず、総合所見欄に記載する方針だ。学習態度を目標準拠で評価するために評価材料を集めるのが教員にとっての負担になっていたり、「挙手の回数」などの不適当な方法で評価が行われていたりしたためだという。
総合所見欄の学習態度は、育成を目指す資質・能力の柱の一つである「学びに向かう力・人間性等」として、子どもの長所や成長に重点を置いた「個人内評価」で見取るとしている。また観点別評価の「思考・判断・表現」と関連付け、特に良かった場合に○(マル)を付けるとする考えも示した。
高校では令和4年度に観点別評価が導入されており、新たな観点への対応が求められることになる。
一方、年間を通じた学習評価の役割の見直しも視野に入れる。学年末には評定を出すことを明らかにした上で、学期ごとでは学習改善に軸足を置いた評価とするよう促していく方針だ。評価場面を精選し、評定の作成にかかる教員の負担を減らす狙いがある。
「中核的概念」で構造化図る
栗山和大・文科省教育課程企画室長
前回の改訂から現在に至るまで、国際調査でも日本の子どもの学力の高さが明らかになった。一方で自律的に学ぶ自信のない子どもの割合の高さが課題となっている。労働市場の流動性が高まり、人生がマルチステージとなる時代に心配すべき傾向だ。
学習指導に引き付ければ、各教科等の内容を指導するだけではなく、学びを将来につなげる視点を育て、各教科等の本質的な意義を捉えた、固有の見方や考え方が身に付く指導をできるかが問われている。このため学校の指導では、個別の知識の集積にとどまることなく、概念や深い意味理解を獲得できるようにする必要があり、その実現に資するよう「中核的な概念」を中心とした目標・内容の構造化を検討している。次期学習指導要領では構造化の他、視覚的に分かりやすい表形式化、教師が使いやすいデジタル化も進め、教科書の内容の精選も含め、「分かりやすい」「使いやすい」ものへと変えていきたい。