特別の教育課程、理数から 中教審特異な才能WG
1面記事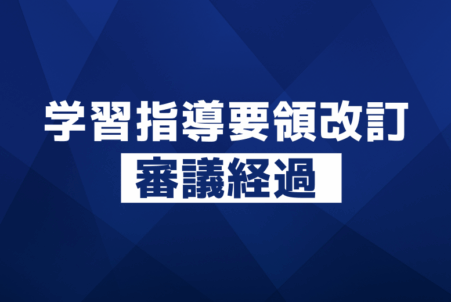
民間プログラム参加など提示 中央教育審議会教育課程部会の「特定分野に特異な才能のある児童生徒に係る特別の教育課程ワーキンググループ」は13日、第3回会合を開いた。特別の教育課程を理数教科から導入する...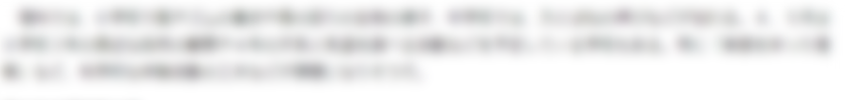
続きを読みたい方は、日本教育新聞電子版に会員登録する必要がございます。
日本最大の教育専門全国紙・日本教育新聞がお届けする教育ニュースサイトです。
先生解決ネットサイトをリニューアル致しました。
リニューアルに際しユーザーの皆様に再登録して頂く必要がございます。
お手数ではございますが、何卒宜しくお願い致します。
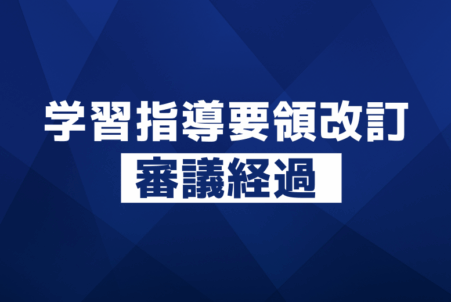
民間プログラム参加など提示 中央教育審議会教育課程部会の「特定分野に特異な才能のある児童生徒に係る特別の教育課程ワーキンググループ」は13日、第3回会合を開いた。特別の教育課程を理数教科から導入する...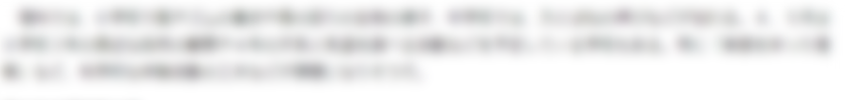
続きを読みたい方は、日本教育新聞電子版に会員登録する必要がございます。